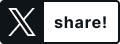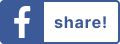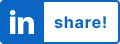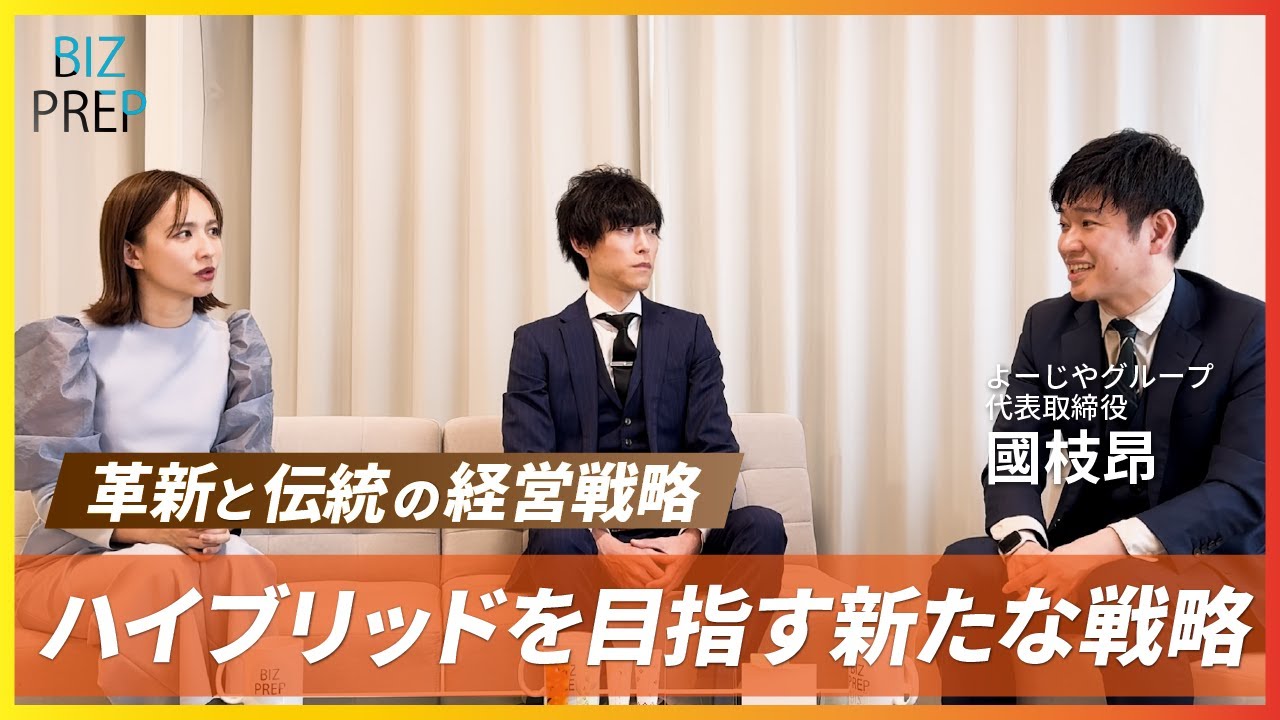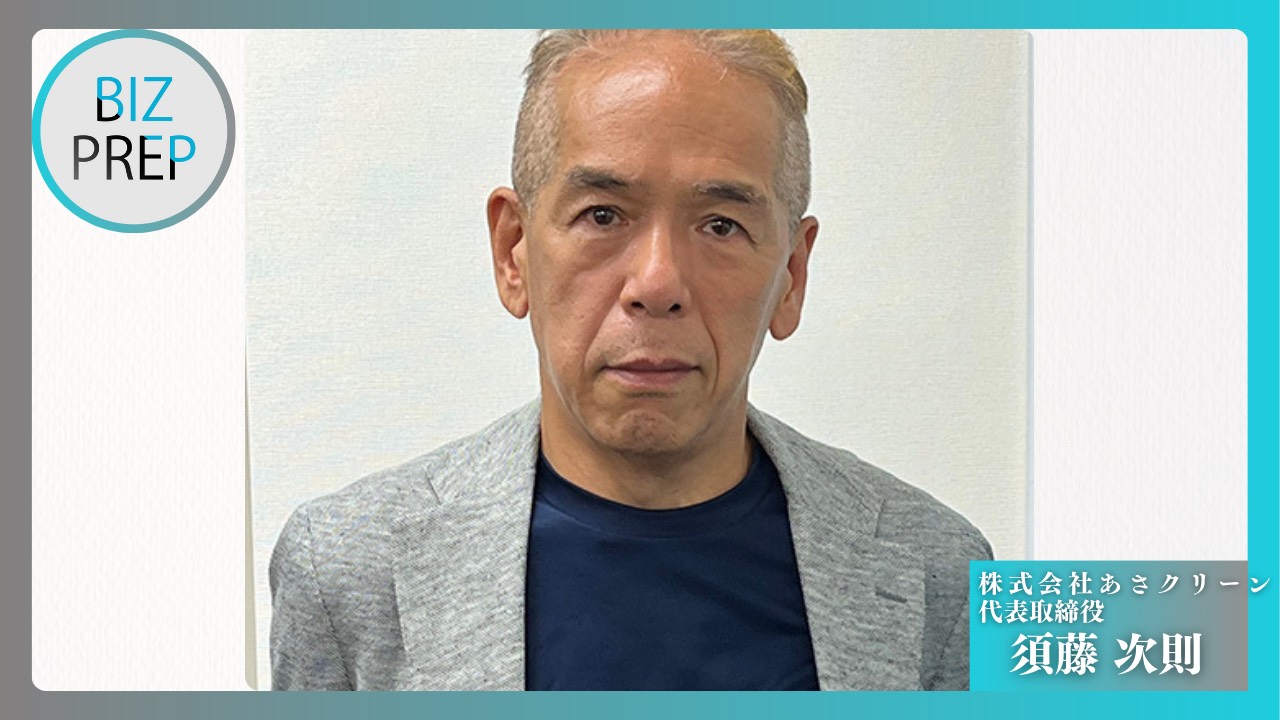目次
創業の原点とは。家業を継ぐまでの歩み
株式会社ふらここはどのように誕生したのでしょうか?
株式会社ふらここは、私が「お客様が本当に求めている雛人形や五月人形を形にしたい」という思いから、約17年前に創業しました。
もともと家業として伝統的な人形作りに関わっていたものの、業界全体が重厚で立派なものを良しとする風潮の中で、私自身は「もっと赤ちゃんのように愛らしく、柔らかい表情を持つお人形を作りたい」という強い想いを抱いていました。
しかし、家業内ではその提案は「迎合だ」と退けられ、ならば自分で形にしてみようと考えたのがきっかけです。
最初は、家業の第2ブランドとして始めるつもりでしたが、職人たちの激しい反発に遭い、自分自身が本当にやりたいものを追求するために独立しました。
家業を継ぐまでの経緯について教えてください。
私はもともと家業を継ぐ気は全く無く、大学卒業後は出版社に勤め、作家になる夢を持っていました。
しかし入社2年目に父が急逝し、母1人では家業を続けられないという状況になったことで、半ば強制的に戻ることになりました。 戻った当初は、夢を失った喪失感でいっぱいで、やる気も持てませんでしたが、「このままではダメだ」と自分で心を立て直し、子どもの健やかな成長を願う親の気持ちに寄り添える仕事なんだと気づき、この仕事に意義を見出して、必死に経営の勉強を始めました。
最初は知識も経験もなく、悩んでばかりでしたが、一歩ずつ学び続けることで、自分自身の中に「ものづくりへの使命感」が芽生え、それが今の私の原点になっています。
家業を継ぐ決意はどのように生まれたのか

なぜ家業を継ぐことに抵抗があったのでしょうか?
私はもともと、自分の人生は自分で選びたいという思いが強く、出版社に就職して作家を目指していました。家業に戻ることは、自分の夢を諦めることでもあり、「決められた道」を進むような感覚があったため、強い抵抗を感じていました。
さらに、当時の家業は伝統を守る姿勢が強く、自分のやりたいことや新しい提案は一蹴されるような環境だったため、「ここで自分がやりたいことを実現することはできないのでは」と感じていたことも理由の1つです。
経営者としての自覚はどのように芽生えたのでしょうか?
経営者としての自覚が芽生えたのは、専務取締役に就任してからも「何も分からない」「相談できる相手もいない」という孤独の中で必死にもがいていた時期です。
社員に「どうしたらいいですか?」と聞かれても答えられず、朝4時に起きてビジネス書を読み、土日はセミナーに通うという日々を続ける中で、「誰かに言われてやるのではなく、自分で決断し、責任を取らなければいけない立場なんだ」と少しずつ考えるようになりました。
そして何より、「自分が作るものを通じて誰かの心を癒し、幸せにできるかもしれない」という気づきが、自覚を持つきっかけになったと思います。
伝統と時代の変化をどう捉えたのか
雛人形市場の変化について、どのように考えておられますか?
昔は祖父母が、孫のために豪華な雛人形を選ぶケースが多かったのですが、時代が変わり、母親自身が選ぶように変化しました。そのため、伝統的で立派な雛人形よりも、小さくてかわいらしいデザインが好まれる傾向になったのだと思います。
最初は、新しいデザインを職人に提案しても拒否されることが多くて苦労しましたが、それでも、お客様の反応を信じて販売を続けました。
その結果、小さくかわいいデザインが時代に合った人形として受け入れられるようになりました。
コンパクト化やデザインの変革をどのように進めていったのでしょうか?
もともと家業では、重厚で大きな雛人形や五月人形が主流でしたが、時代の流れとともに住宅事情や消費者の好みが変わり、よりコンパクトで可愛らしいものが求められていると感じていました。
私自身も販売の現場で「赤ちゃんのお母さんが選ぶものは、もっと柔らかく優しいものを望んでいる」と肌で感じていたため、職人たちに企画提案を行いました。
しかし最初は大反対されましたので、一度は引き下がり、家業の第2ブランドとして試験的に商品を作って販売してみたんです。すると、お客様の反応は非常に良く、「かわいいものを求める声」を実証できたことで、徐々に自分の考えに確信が持てるようになりました。
なぜ独立という道を選んだのか
家業ではなく、独立を決断された理由を教えてください。
一番大きな理由は、家業の中ではどうしても「伝統を守る」という枠組みが強く、自分が感じていた「お客様が本当に欲しいもの」を自由に形にすることができなかったことです。
私としては自分の信じたものを貫くために、自分自身で責任を負って挑戦したいという気持ちが大きくなり、独立を決めました。
独立するため、資金調達はどのように行ったのでしょうか?
実は、誰からも資金援助を受けず、全て自分自身で準備した資金でスタートしました。
出版社時代からコツコツと積み立てていた貯金に加え、生命保険を解約して現金化した1,000万円と日本政策金融公庫(当時の国民金融公庫)から融資を受けた1,000万円の、合わせて2,000万円を元手に創業しました。
ものづくりのこだわりとは。職人たちとの挑戦

職人たちとの関係構築はどのように進めたのでしょうか?
独立の際、家業に迷惑をかけたくないという思いから、家業時代の職人には頼らず、自分自身で新しい職人を開拓しました。
何十件も職人のもとを訪ね歩きましたが、「おもちゃみたいなものは作れない」と半分以上の方に断られました。それでも、若い世代の職人の中には興味を持ってくれる方がいて、少しずつ信頼関係を築きました。
そして販売実績が積み上がっていくにつれ、職人の側からも声をかけてくれるようになり、自然と強いパートナーシップが生まれていきました。
ふらここの人形が従来のものと異なる点について教えてください。
私たちは母親が好む、優しく柔らかな表情を追求し、従来の人形とは差別化を図りました。 また顔のデザインには、業界初となる3D技術を使った点も、従来との違いの1つです。
手作業だけでは微妙な調整が難しく、職人の感覚頼みになりがちでしたが、3D技術を使うと細かな修正も簡単に行えます。 何種類もデータを作成し、お客様の声を直接取り入れながら人形を作り上げています。こうした新しい方法が他社との大きな違いとなりました。
販売戦略と市場開拓はどのように進めたのか
なぜネット販売を主軸に据えたのでしょうか?
創業当時は資金が限られ、実店舗を構える余裕が無かったため、オンラインでの販売を検討しました。
家賃や人件費の負担を抑えながら、多くの人に商品を届けられると考えたのです。
また、家業でネット販売を試した経験があり、成功の可能性を感じていました。
当時は「ネット販売は高額商品には向かない」と言われていましたが、雛人形250セットを用意し販売を開始。
すると、わずか2週間で完売し、大きな手応えを得ました。この結果に勇気づけられ、さらなる販売戦略を練りました。この成功を機に、ネット販売にさらに力を入れるようになりました。
創業当初はどのようにして顧客を獲得したのでしょうか?
創業当初は知名度が無く、まずネット広告を利用し、検索エンジンで目に留まりやすくしました。
当時はネット販売が一般的ではなく、高額商品の購入に不安を持つ人も多かったため、詳しい商品説明を掲載しました。安心して選んでもらえるよう、購入者の体験談やレビューを紹介し、信頼性を高める努力を続けました。
また広告だけに頼らず、購入者の口コミを重視し、自然に広がるよう意識しました。さらにSNSを利用して商品の魅力を発信し、共感を生むコンテンツ作りにも力を入れました。その結果、初年度に用意した雛人形は全て完売し、順調なスタートを切ることができました。
経営者として追及した「お客様が求めるもの」。試行錯誤の日々
事業を軌道に乗せるために必要だった学びとは何でしょうか?
一番初めに学んだことは、「自分が思う理想」や「職人としてのこだわり」だけでなく、「お客様が本当に何を望んでいるのか」を常に追求し続ける姿勢を持つことの大切さでした。
当初は「伝統を守るべきだ」「自分が良いと思うものを作ればいい」と考えてしまいがちでしたが、実際に市場に出したとき、お客様の反応を冷静に受け止め、次にどう活かすかを考えることが必要だと学びました。
また、ビジネスはものづくりだけでなく、集客・販売・組織運営の全てが揃って初めて成り立つことも早い段階で痛感し、地道な経営知識のインプットと実践を繰り返してきました。昨年には、雛人形ブランドの知名度3位を取ることができたのも、それらのおかげだと思っています。
20代での試行錯誤が現在の経営にどのように活きているのでしょうか?
20代の頃は、知識も経験も無い中で、どうしたらいいか分からない状態が日常でした。
朝4時に起きて本を読み、土日はセミナーに通い、会社に戻っては失敗を繰り返していましたが、その時の「分からないからこそ必死に学ぶ」「決断と責任を自分で持つ」という習慣が、今でも私の土台になっています。
経営は常に答えが無い世界ですし、新しい課題が次々に現れます。その時に自分で考え抜き、行動に移して検証するという思考力を身につけられたことが、今も会社を支える大きな力になっています。
ふらここが目指す未来とは――伝統工芸の継承と挑戦

これからのふらここが目指すものについて教えてください。
市場が縮小する中、新たな価値を生み出すには挑戦が欠かせません。
従来の技術を大切にしながら、現代の工法も取り入れ、独特で魅力的なデザインを追求しています。
さらに、若い世代にも伝統文化の魅力を伝えるため、幼稚園や保育園に、雛人形や五月人形を寄贈する等の取り組みを行なっています。
雛人形をより身近に感じてもらえるよう工夫を重ね、日本の文化を未来へ継承していきたいと考えています。
そのために、新たな商品開発や販売方法の工夫を続け、幅広い世代に親しまれるブランドを目指していきます。
日本の伝統工芸を次世代にどのように継承していくのでしょうか?
日本の伝統工芸を次の世代へ受け継ぐには、技術を守るだけでなく、新たな価値を生み出す工夫が欠かせません。ふらここでは、職人の技を大切にしながら、現代の暮らしに合った雛人形や五月人形を開発し、幅広い世代に親しまれるものづくりを続けています。従来の製法を活かしつつ、3D技術を活用することで、表現の幅を広げました。
さらに、伝統技術を学ぶ機会を増やし、若手職人が安心して技術を磨ける環境づくりにも力を注いでいます。
今後も新たな挑戦を続けながら、日本の文化とものづくりの価値を次世代へ継承して、より多くの人に伝統の魅力を感じてもらえるよう取り組んでいきます。