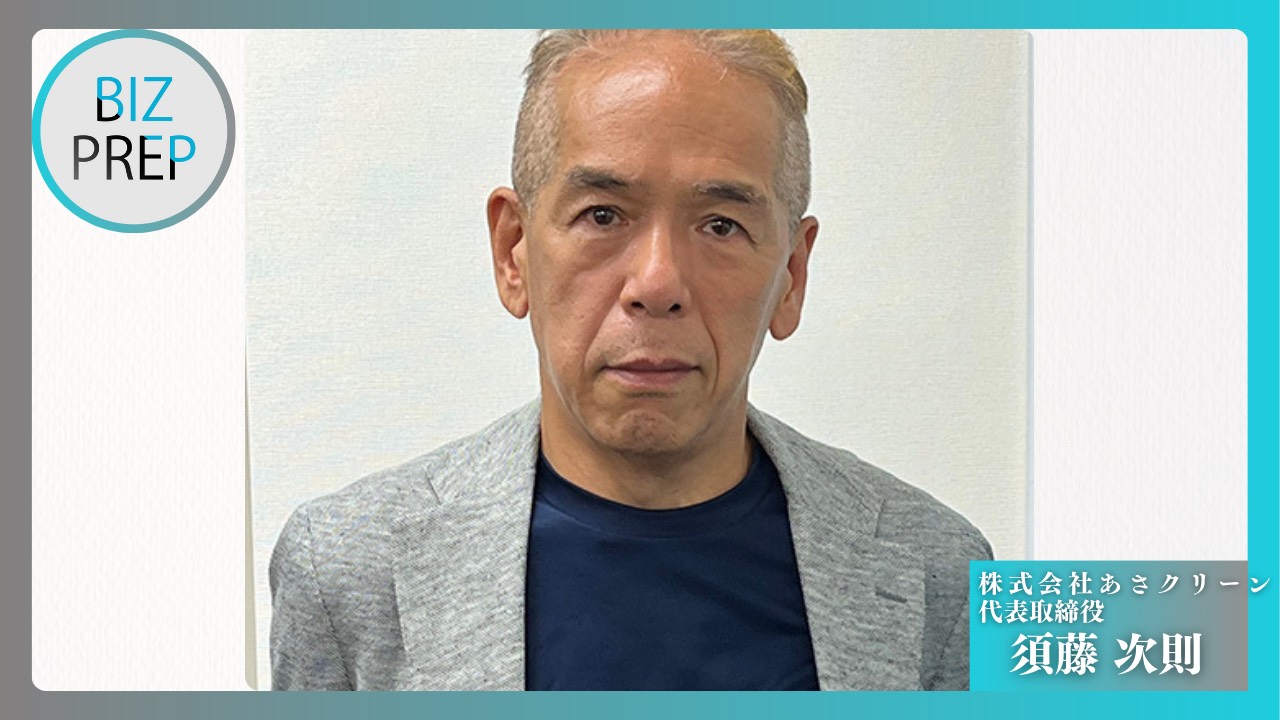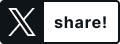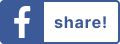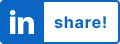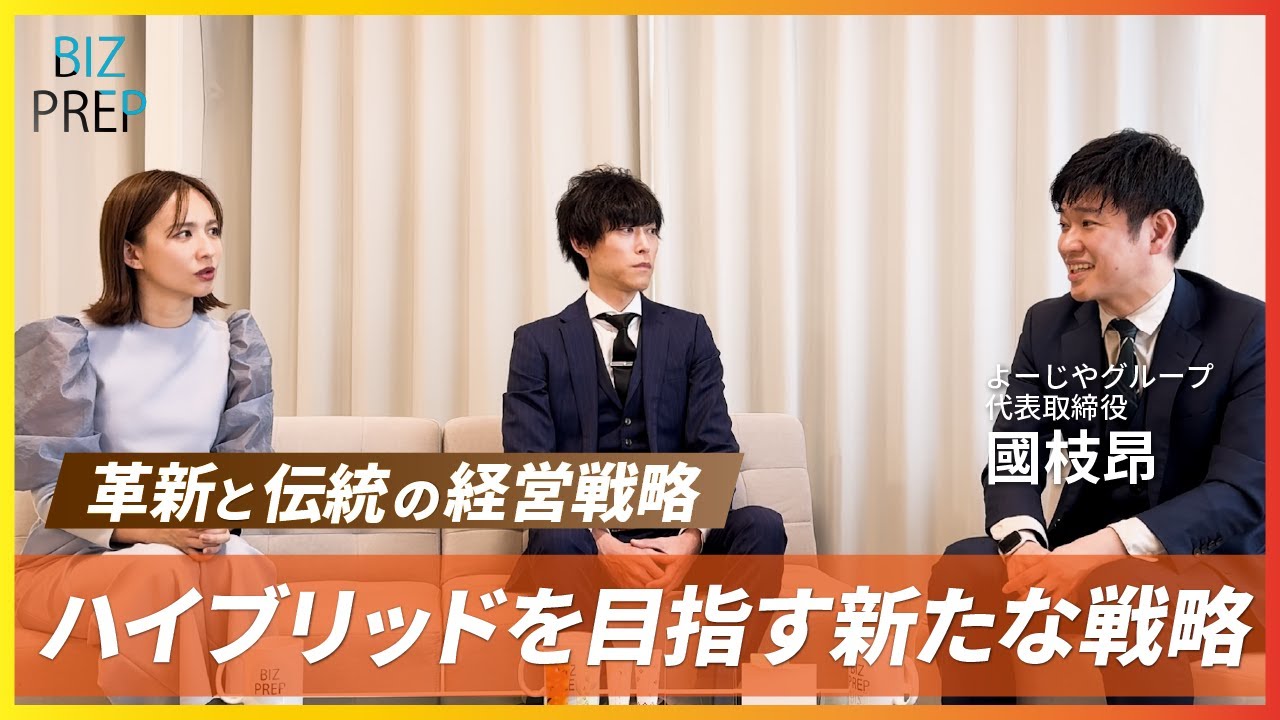目次
大企業退職からの起業 多くの失敗を乗り越えて
まず、御社の創業から今までの歩みと、社長個人の独立までのご経歴を教えていただけますでしょうか。
私は日本コカ・コーラに定年まで勤めていました。当時のコカ・コーラは、全国に17あったボトラー社を再編する大きな変革期にあり、私は主にコカ・コーラウエストジャパンを中心に、各エリアのボトラー再編に携わりました。
その中で、再編と同時にグループ会社の事業を切り離すことになり、私が定年を迎えるにあたり、その事業の引き継ぎを任せたいという要望をいただきました。これが、私が起業するに至った経緯です。
大手企業のグループ事業を引き継ぐ形で起業しました。しかし、当時の私は事業運営の厳しさを甘く見ていたのです。いちサラリーマンだった自分にそのビジネスを回していく能力が不足していることを痛感し、多くの失敗を経験することになりました。
起業当初はどのような苦労がありましたか。
定年後に起業する最大のデメリットは、人間関係が途切れてしまうことです。在職中であれば人脈を活かせますが、退職してしまうとそれまでのつながりは自然となくなってしまう、それが大きな壁でした。
さまざまなビジネスを経験する中で、私は大手企業と中小企業では、ビジネスの進め方が全く違うことを痛感しました。大手企業時代は、ブランド力や信用、そして組織のサポートがあるのが当然でしたしかし、起業後はその全てがない中で、多くの苦難を経験することになりました。
コロナ禍で発見した食品自動販売機の可能性

現在の自動販売機事業を始めるきっかけを教えてください。
様々な商材を扱う中、転機が訪れたのはコロナ禍でした。 世の中のだれしもが外出自粛を余儀なくされ、
不安な状況下で、富士電機さんから食品自動販売機の展開を持ちかけられたのです。これが、現在の事業を始めるきっかけとなりました。
当時、日本全国には約240万台の飲料系自動販売機がある一方で、食品の自動販売機はわずか6万台しかありませんでした。過去には、カップラーメンにお湯を注ぐタイプや、レトロな自販機も多かったのですが、それらはことごとく衰退していったのです。
その主な原因は、味の問題、コストの問題、そして消費者が抱く衛生面への懸念でした。こうした課題を解決できず、当時の食品自動販売機ビジネスは普及しなかったのです。
食品自動販売機の可能性に気づいたのはどのような体験からでしょうか。
富士電機さんからのお誘いがきっかけです。当初は何度もお断りしていたのですが、最終的に『見るだけでも』と依頼され、足を運んでみました。そこで目にしたのは、月に60〜70万円を売り上げる食品自販機でした。
「当時の飲料系自販機の年間平均売上が100万円ほどだったことを考えると、その数字は衝撃的でした。その場所だけでなく、他の事例も調査してみると、年間1000万円ほど売り上げるケースが平均的であることが分かり、その市場規模に驚かされました。
また、コロナ禍でも売上が落ちなかったことから、衛生面や非接触という点で、飲料系自販機から需要が移り、食品自動販売機が今後伸びていくと確信したのです。
その後の事業展開はいかがでしたか。
ちょうどその頃、サンデン・リテールシステム株式会社が、冷凍技術に優れた冷凍自動販売機「ど冷えもん」を発売しました。私はすぐにその九州代理店となり、販売を一気に広げることができたのです。それが、現在の事業へとつながっています。
顧客との信頼関係が事業を育てる。「設置後」から始まる真のビジネス

他社との一番の違いや、御社の最大の強みはどのような点でしょうか。
多くの自動販売機事業者は、機械を設置したらそこでビジネスが完結することが多いです。しかし、当社は「設置した後が本当のビジネス」だと考えています。
この考えは、私が飲料の自動販売機がまだ少なかった時代から培ってきた経験に基づいています。当時は、売れない自販機をどうすれば売れるようにできるか、試行錯誤を繰り返していました。その成功体験から、私は「設置後の継続的なビジネス」にこそ価値があるという信念を持つようになりました。これが、他社との最も大きな違いであり、当社の最大の強みと自負しています。
その考え方に至った背景には、どのような経験があったのでしょうか?
私がコカ・コーラにいた頃、コカ・コーラがグループ会社として、カナダドライ製品を扱っていた会社を買収しました。その立て直しのため、私が営業トップとして派遣されたことがあります。
コカ・コーラで培った営業手法を活用して、コカ・コーラの一日10万円売れている自動販売機の隣に、私が担当するカナダドライの自動販売機を設置しました。コカ・コーラグループの商品を参考に、それらに匹敵するような味のコーヒーを、独自のブランドとして展開したのです。
お店の方には「コカ・コーラが製造している会社なので間違い」ということで、私も自信をもって設置していただきました。
しかし、一週間後に巡回したところ、すべて補充されている状況でした。お店の方に「補充していただき、ありがとうございます」と申し上げたところ、「一本も売れていないのです」と言われたのです。「設置したばかりだから」と言い訳をして、次の巡回でも同じ状況が続きました。
売上実績を見ると、隣のコカ・コーラの自動販売機はよく売れているのに、私が担当する自動販売機は全く売れていませんでした。お店の方からは「あなたが勧めたから設置したのに、だめじゃないか」という厳しい言葉をいただき、当時は本当に苦しい思いをしました。
その状況をどのように乗り越えられたのですか?
ある店のオーナーさんが私の表情を見て「どうしたのか」と声をかけてくださいました。状況を説明すると、そのオーナーから「お前は自分が一番辛いと思っているだろう。でも一番辛いのは、お前を信じて置いてくれた店主だ。それに対して、それでいいのか」という言葉をいただきました。
その一言で、自分が現実逃避していたことに気づかされました。売れていない現実を見ても逃げずに、申し訳ないという気持ちで何かお役に立てることをしようと決心しました。
店の掃除をしたり、配達の手伝いをしたり、お客様への接客サポートなど、できることは何でもやりました。そうした取り組みを続ける中で、徐々に売上が伸びていったのです。
なぜ売上が伸びたのでしょうか?
店主さんが来店されるお客様に「この自動販売機の商品も試してみてください」と声をかけてくださるようになったからです。私たちの真摯な取り組みを見て、店主さんが営業を手伝ってくださったのです。
この経験から、「自動販売機を設置して終わりではなく、設置後のフォローとお客様との関係構築こそが重要だ」ということを学びました。デジタル化が進む中でも、アナログの部分、つまり人と人との繋がりが必要だと確信しています。
業界の課題と中国から学ぶイノベーション
自動販売機業界の将来と御社の戦略について教えてください。
まず、自動販売機業界の将来についてです。将来的には、地方のスーパーマーケットのフードコートは全て撤退していくと考えられます。
その理由は、人件費と配送コストが見合わないからです。遠隔地への配送や、近くに店舗がない地域では、特に採算が取れません。たとえば、ある地方では、1店舗しかないスーパーマーケットを維持するために大きな経費がかかっています。また、地方では人手不足も深刻で、従業員の確保が難しいのが現状です。
そのような状況の中で最も重要なのは、「無人販売」という、人を雇わないビジネスの拡大です。人件費やコストの問題を考えると、今後これがなければ経済が成り立たなくなります。これまでは大手チェーン店が各地域に出店していましたが、今後は地方での出店が難しくなるでしょう。そこで、セントラルキッチンで調理したメニューを無人販売で提供できるようにすることが不可欠です。
そうした状況において、人手不足と原材料の高騰は大きな課題です。さらに、今まで大企業から仕事を受けて経営を成り立たせていた多くの中小企業が、今、厳しい状況に直面しています。なぜなら、大企業自身が販路を失い、中小企業に依頼する仕事も減っているからです。これまでのように、大企業からの仕事だけに頼る経営は成り立ちません。今後、どういう戦略を取るべきか、誰もが明確な答えを見出せないでいます。中小企業は、自分たちで新たな販路を開拓していくことが重要な課題となっています。
海外の事例を参考にされているとお伺いしました。具体的にどのようなことから学ばれましたか?
はい、特に中国の自動販売機から多くのことを学びました。中国の自動販売機は、日本よりも数段進んでいます。
日本の自動販売機は、これまでコカ・コーラやサントリーといった飲料メーカーが中心となって発展してきました。メーカーはB2C戦略を飲料メーカーに任せ、買い取り制度を通して商品を開発・供給してきました。
しかし、食品に関しては、同じような形で事業を推進するメーカーがほとんどいません。なぜなら、大手外食チェーンなどにとって、自社の商品を自動販売機で販売するだけでは、ビジネスとして十分な満足を得ることが難しかったからです。
一方で、現在では新しいニーズが生まれています。たとえば、高速道路のサービスエリアで夜間に温かいものを食べたいという需要が増え、電子レンジ付きの自動販売機や、ピザが焼き上がる自動販売機など、多様なニーズに応えるものが求められています。
中国と比較してどのような点が参考になりますか。
偶然、中国に2、3回視察に行く機会があり、その際に日本の大きな遅れを感じました。例えば、中国では虎ノ門のような大規模なビジネス街でも、40階にある部屋からスマートフォンで食べ物を注文すると、ドローンやエレベーターを使って、部屋の前まで届けてくれるレベルに達しています。
一方、日本では様々な規制があり、個々の技術はあっても、それらを連携させてシステム全体を動かすことができません。これが大きな課題だと感じています。しかし、前職でこの地域のビジネスに携わってきた経験を活かし、そうした課題の解決に貢献できるのではないかと考えています。
地域密着型ビジネスモデルの構築

将来御社はどんな会社にしていかれたいという、中長期的な御社、どのような姿を目指していかれるのでしょうか。
中長期的に、私たちは「ブランド」を創造する会社を目指します。コカ・コーラでブランドの重要性を学んだ経験から、お客様が安心して欲しいものを買える、そのための確固たるブランドを築きたいと考えています。そのために、私たちは製造から販売まで一貫して関わるビジネスモデルを構築します。
具体的には、製造段階からメーカーと協力し、最新の冷凍技術などを提供して高品質な商品を作っていただきます。そして、私たちがその商品の販路を担うことで、お互いに協力し合える関係を築いていきます。日本には、何十年もかけて良いものを作り続けてきたにもかかわらず、販路を持たない中小企業がたくさんあります。一方で、私たちには販路があっても、良い商品がありません。そのような企業と手を組み、配送業者などとも連携することで、地域に密着した中小企業を中心とした一つのホールディングスを形成したいと考えています。
私自身が中小企業で働いた経験から、大企業との違いを痛感しました。日本の政策は中小企業に対して手厚くなく、十分な経営指導も行われていないのが現状です。だからこそ、当社だけで事業を行うのではなく、様々な地域の方々と連携し、共に経営に携わることで、地域経済の活性化にも貢献したいと考えています。これが、私たちの企業方針です。
今後の災害対策や地域支援について具体的な取り組みはありますか。
超高齢社会の中である現在、私たちは「買い物難民」と呼ばれる方々や、災害時に孤立してしまう方々を支援したいと考えています。
誰もが安心して買い物ができる環境をつくるため、コンテナ型の自動販売機を設置し、蓄電池や発電機をつなげて災害時でも利用できるようなビジネスを目指しています。
資金調達の課題と今後の展望
最後に、御社の今の課題や足りないものについて教えてください。
現在の最大の課題は資金調達です。銀行は実績がなければ融資してくれず、設備資金も全額は貸してくれません。例えば、3,000万円の融資を受けるには、1,000万円の自己資金を準備しなければなりません。
一度設備を設置しても、その売上だけで月々の返済を続けるのは厳しいのが現状です。多くの競合がいる中で、この点が私にとって一番の課題だと感じています。この課題を乗り越えるためには、各地域で共にビジネスを展開できるパートナーを見つけ、うまくマッチングしていくことが重要だと考えています。 また、各エリアに物流などの仕組みを提供し、当社のノウハウを活用しながら各企業で協力し合える体制を構築することが今後の目標です。