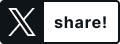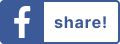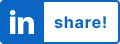目次
IT業界からもんじゃ業界へ転身した異色の経歴
まずは中村さんの簡単なご経歴を教えてください。
私は浅草生まれの月島育ちで、小学校5年生の時に月島に引っ越してまいりました。父が浅草、母が月島の出身という縁もあり、この土地に深い愛着を持っています。
高校1年生の時から地元のもんじゃ屋でアルバイトを始めました。当時の月島にはマクドナルド等いくつかのチェーン店しかなく、地元の高校生は皆、もんじゃ屋でアルバイトするという文化がありました。
私もサッカー部の活動と並行しながら、社会人になるまでの約10年間のうち、計5、6年間もんじゃ屋の仕事に携わってまいりました。
大学時代には、アルバイトでの実績を買われ新規もんじゃ店の立ち上げに参画させていただく機会をいただきました。これまでアルバイトとして教わる立場だった私が、初めて「作る立場」を経験し、ビジネスを構築することの面白さを実感しました。
新卒で大手IT企業に就職し、大手エンタープライズ向けのSaaSサービスやシステム受託開発、DX領域のコンサルティング支援領域において営業部長として全国を回っておりました。
delta創業後も8年間は会社員を続けながら副業として店舗運営を行うことでリスクを抑えて段階的に事業を拡大していく戦略を取りました。2024年7月からようやく専業として取り組むようになり、現在は専業として約1年余りという状況です。
物件探しに半年、手紙が繋いだ創業への道のり
ご創業のきっかけを教えてください。
大学の友人が私の働いていたもんじゃ店に来てくれた際、「もんじゃってどういうビジネスなの?」とよく質問されていました。その友人と「いつかそういうのをやってみたいね」と話していたのを覚えています。
お互いが社会人になって4、5年目、27、8歳のタイミングで、その友人から「学生時代に話していた件、今からやってみない?」と声をかけられたのが創業のきっかけです。
最初は私と友人の二人で始めようと考えていましたが、友人関係に傷がつくリスクを考慮し、3人で始めることにしました。さらに、私の地元での繋がりともんじゃ屋での経験を活かすため、地元の友人でもんじゃ屋での経験がある人材も加え、最終的に4人でスタートすることになりました。
創業当初、最も苦労したのが物件探しでした。月島には約80店舗程度のもんじゃ店がありますが、どこも経営が安定しており、新規参入の機会はほとんどありません。路面店の公開物件には20〜30社の申し込みが入るほど競争が激しく、不動産業界の知識もない私たちには非常に困難な状況でした。
そこで自分たちでチラシを作成し、商店街の既存店舗に直接お願いに伺いました。時には冷たくあしらわれることもありましたが、半年間粘り強く活動を続けました。
転機となったのは、月島もんじゃ振興会を設立されたオーナーさんとの出会いでした。私たちが書いた手紙には、「これからの月島はこうあるべきだ」という課題感やポテンシャル、目指すべき方向性を綴りました。そのオーナーさんは他人に店舗を貸すことに消極的でしたが、私たちの手紙を読んで「お前たちみたいな人に貸してみたい」と言ってくださり、何年かぶりに物件を貸していただけることになりました。

高級創作もんじゃで差別化を実現
創業当初はどのような状況だったのでしょうか?
「こぼれや」という店名で、具材がこぼれるほど載っているというコンセプトで始めました。しかし、4人で運営していると様々な意見が出て、ブランドコンセプトが一貫しない状況が続きました。最初の1年間は毎月の損益がギリギリか赤字という苦しい状況だったんですよね。
そんな中、化粧品会社のブランドマネージャーをしている友人から「ブランディングとはこういうものだ」「ここがおかしい」という指摘を受け、自分たちを否定する作業から始めて抜本的なリニューアルを行いました。そこから「高級もんじゃ路線」に舵を切ったのが、私たちの事業拡大への第一歩となりました。
他社さんとの差別化はどのように図られたのですか?
高級創作もんじゃという位置づけで、まず素材一つ一つにこだわりました。揚げ玉については、ミシュランガイドに掲載されている天ぷら屋さんの天かすを使用させていただいたり、明太子も博多の有名ブランドを使用したりするなど、価格以上の価値を提供できるよう工夫しました。
また、写真の見栄えにも力を入れ、SNSで映えるような魅力的な写真の撮り方、カメラマンさんの起用、盛り付け方、色使いなど、商品開発の段階でこれらの要素を組み込む仕組みを構築しました。
立地面では、私たちは当初は実績がないことから路面店の獲得は難しく空中店舗や路地裏など、通常選ばれないような場所に出店せざるを得ませんでした。よって、好立地ではない条件でもそこで勝てる戦略を取る必要があり、ネット市場での予約獲得に注力することにしました。ビジネスマンや食にこだわりのある方で比較的お金に余裕のある層をターゲットに、高級もんじゃの魅力を訴求してきました。

コロナ禍でのリスクテイクが成功を呼んだ
コロナ禍はどのような影響がありましたか?
順調に事業が進み、社員旅行でハワイに行けるまでになった矢先にコロナが始まりました。経営としては大打撃を受けたものの、幸運だったことは3店舗目の設計をしているタイミングであったことです。既に完成していた設計を全面的に見直し、オープンな席設計から個室型のもんじゃ店にコンセプトを変更しました。
WEBの自然検索で「月島 もんじゃ」の後に続く機能的ワードの最上位に「個室」が表示されていたことなど、コロナ禍の需要に「個室」というコンセプトがマッチしました。世の中の情勢をとらえた戦略をスピーディに取れたことによって、厳しい時期を乗り切ることができました。
経営者としての成功体験を教えてください。
最も大きな成功体験は、リスクのある時期に勝負をかけたことです。コロナ禍の終盤、収束が見えずリスクの高い誰もが投資を控えるタイミングで、収束を見越して表通りの大きな坪数の物件を取りにいきました。
その結果、会社全体の売上が300%以上増加し、さらなる事業拡大ができる土壌を形成することができました。まさにこれが私たちの事業拡大にとって大きな変革期となりました。リスクを恐れずに行動することの重要性を実感した体験でした。
経営者として学んだ失敗と成長の軌跡
一方で、失敗体験についても教えてください。
最も大きな失敗は、大企業での経験をそのまま小さな企業に当てはめようとしたことです。大企業が稟議制度や業務承認フローを設けている本質的な理由を理解せず、単純に仕組みを移植しようとした結果、リソースが限られた組織でスピード感を大きく損なってしまいました。
また、人材に対しても前職と同じレベルを求めてしまい、全く異なる背景を持つ人材とのコミュニケーション課題や摩擦を生んでしまいました。さらに、事業を成功させなければならないという強い使命感から損益に対して過度に敏感になり、その熱量をそのまま組織に向けてしまったため、メンバーに無理をさせてしまったことも反省点です。
どのようにしてその課題に気づかれたのですか?
創業メンバーの友人が、直接的に反抗するのではなく、日常の行動の中で批判的な態度を取ったり、陰で不満を言ったりしているのを察知したのがきっかけでした。友人関係だからこそ、私に対して何らかの課題感があることを理解し、自分が変わらなければならないと気づくことができました。
チームワークを重視した組織づくり
ビジネスにおいて大切にされている考え方について教えてください。
私が最も重視しているのは、個人の成功よりもチームの成功です。下町育ちという背景もあり、家族経営で事業を営んでいた両親の影響、そして一代で上場企業まで築き上げたオーナー経営者のもとで働いた経験が大きく影響しています。
営業時代には2、3千人と名刺交換をし、様々な企業の社風を見てまいりましたが、ドライな会社の話を聞いても全く面白そうに感じませんでした。いくら稼いでいるか、どんな仕事をしているかではなく、私は「誰と仕事をしているか」が最も重要だと考えています。主語を「I(私)」ではなく「We(私たち)」で語る方が楽しいと思っています。
創業当時から離職率が非常に低く、帰属意識の高い社員が残り続けているため、新しい人材が入ってきても良い企業文化が継承されています。他社と比べると「ウェット」な面があるかもしれませんが、そこが私たちの圧倒的な強みになっていると感じています。
人生を通じて仲間づくりをしていく、仲間がどんどん増えていくということに喜びを感じています。よく社員に話すのは「一緒の船をみんなで一緒に漕ごう」ということです。それが冒険をしているようで非常に楽しく感じています。

フランチャイズ化と海外展開を視野に描く未来図
もんじゃ業界の将来についてはどのようにお考えですか?
もんじゃの認知度は日本国内では大幅に向上していますが、実際に月島を訪れたことがある人、もんじゃを食べたことがある人はまだ少数です。これは大きなブルーオーシャン市場だと考えています。
最近では、吉祥寺、下北沢、名古屋、大阪など、これまでもんじゃ店がなかった地域に積極的に出店を進めいる企業もおり、確実にニーズがあることを実証しています。去年から一昨年にかけて、この業態の出店数が3、4倍に増加しており、業界全体が大きく成長している状況です。
最近の飲食業界では、チェーン店や総合居酒屋ではなく、専門店への関心が高まっています。よりグルメに興味を持つ消費者が増え、専門性のある業態が強くなってきました。もんじゃは専門性があり、観光飲食としてインバウンドや国内観光にも強いという特徴があるため、非常に魅力的な業態だと位置づけています。
都内でも月島以外ではまだまだもんじゃ店を見かけることは少なく、観光利用だけでなく、プライベートで利用される方も特に若い世代を中心に増加しています。商圏としてはまだまだ拡大の余地があると感じています。
御社の今後の事業展開について教えてください。
私たちは「Share the TEPPAN CULTURE」をミッションに掲げ、鉄板を囲む食体験を世界中に広め、一般化・大衆化していくことを目標としています。しかし、資金力や投資体力が限られている中で出店速度を上げることは困難なため、フランチャイズ化に注力していきたいと考えています。
もんじゃ業態は焼肉と同程度の初期投資が必要でありながら、単価は焼肉より低いという特徴があります。これまで新規参入が少なかった理由でもありますが、この状況を変えていく役割を担いたいと思っています。
将来的な資金調達や上場については、現在のところ明確に決めておりません。ミッションに向かって進むことは決まっていますが、その手段については柔軟に考えています。ただし、私たちが最も重要視していることの一つが従業員を大切にするということです。従業員と家族のように一緒にこの会社で生きていくことを大切にしているため、エクイティバイアウトには慎重にならざるを得ない面があります。上場すると資金調達は可能になり事業は加速しますが、同時に制約も生まれるため、メリットとデメリットを慎重に検討していく必要があると考えています。

地方食材との連携で地域創生に貢献
地域社会に対する取り組みについて教えてください。
私は地元を変えたいという強い思いを持っていますが、直接的な活動はまだ限定的です。現在取り組んでいるのは、地元にインバウンドを増やすことです。今後日本の人口減少が進む中、海外からの観光客を呼び込むことは非常に重要だと考えています。
そのために浅草店を出店したり、海外展開を進めることで、間接的に地元に貢献したいと考えています。また、地元で人気店であり続けることも一つの価値だと思っています。
ミッションの一部である「Save the JAPANFOOD」という言葉には、私が前職で地方銀行を訪問していた経験から感じた地方の衰退に対する思いが込められています。微力ながら日本の地方に貢献するため、地方食材をもんじゃに取り入れて提供することに取り組んでいます。
具体的には、高知県と共同で商品開発・キャンペーンに取り組んだことがあるほか、恒常的にメニューの食材として地方食材を使用した商品づくりを行っています。最近では佃煮の発祥地である佃にちなんで「佃煮もんじゃ」を開発し、テレビでも取り上げていただきました。仕入先の佃煮屋さんも紹介され、お互いにとって良い宣伝効果となりました。
今後も地方の優れた食材を多くの方に教えていただき、共同でその食材をPRしていければと考えています。また、私たちに共感していただける方がいらっしゃいましたら、地方での店舗運営にもご協力いただきたいと思っています。
最後に、読者の皆様へのメッセージをお願いします。
私たちは「世界中に鉄板を囲むよろこびを」というビジョンのもと、もんじゃ文化の普及に取り組んでいます。地方の素晴らしい食材を活用した商品開発や、フランチャイズでの事業拡大にご興味のある方は、ぜひお声がけください。共に日本の食文化を世界に発信していきましょう。