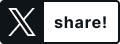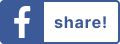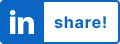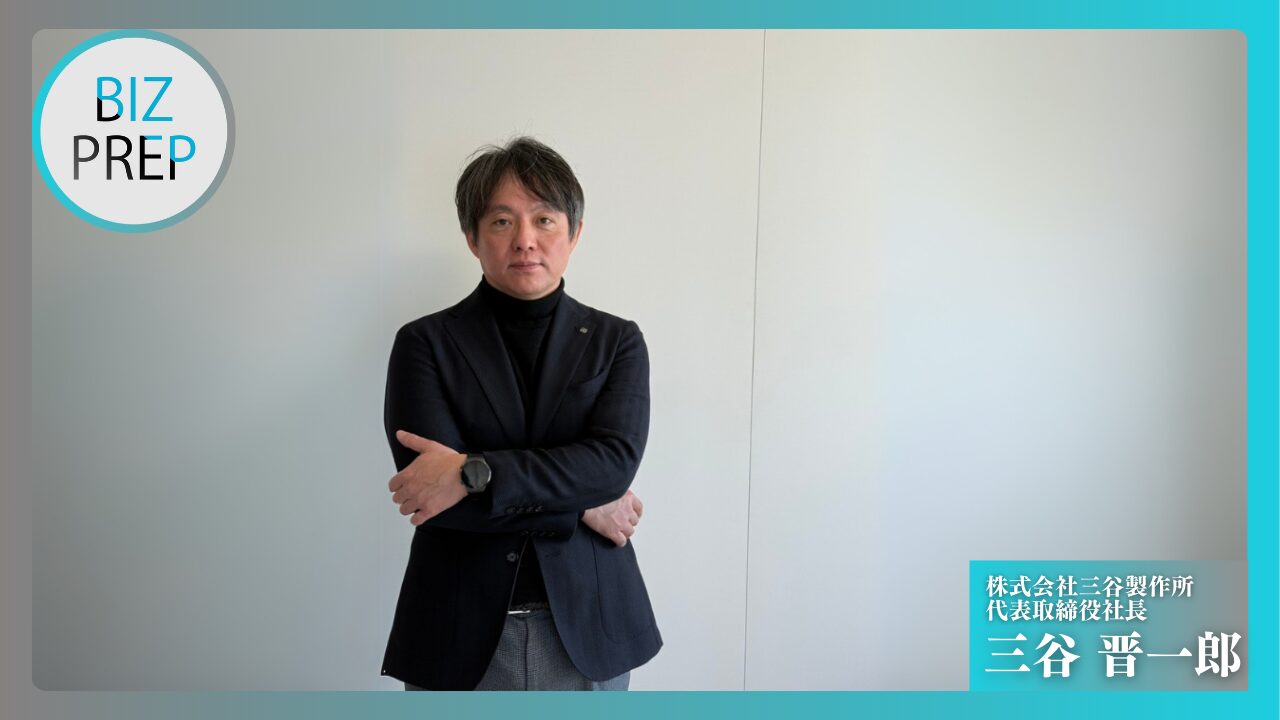目次
経営者への道はどのようにして拓かれたのか

まずは、増田社長のこれまでのキャリアについてお聞かせください。
私のキャリアは繊維業界から始まりました。大学卒業後、繊維商社で営業職として約7年間勤務し、新規取引先の開拓を主に担当しました。飛び込み営業なども経験する中で、社会人としての心得や業界の仕組みを学び、入社半年後には新規取引先との商売も始まり、順調な滑り出しでした。しかし、東京勤務を経て、業界特有の柵や体質、自身の待遇や働き方に対する不満から転職を考えるようになりました。そんな時に出会ったのが、後にディーブレスの共同経営者となる今井でした。
とはいえ、次の転職先に選んだのは菓子メーカーのカルビーでした。ポテトチップスやかっぱえびせんなど加えシリアル、グラノーラの営業を担当し、当時、袋スナック菓子で70%以上の店頭シェアを誇るカルビーで、転職組であり菓子業界の門外漢である私を電鉄系スーパーの営業担当に抜擢していただいたことに感謝しています。諸先輩方や同僚に助けてもらいながら、比較的スムーズに業務を行うことができました。株式上場の1年前ということもあり、社内向けのルールや業務が多かったことを覚えています。大企業ならではの仕組みや考え方を学べた一方で、個人の裁量が限られ、市場のニーズに即応できないもどかしさも感じていました。
その後、ディーブレスに合流し、まずは販路拡大に従事しました。繊維商社で学んだ知識、カルビーで培った店頭の棚割り、売り場管理や流通の知識を活かし、ディーブレスにとっての新たな売り方を開拓しました。展示会への出展を増やし、国内外の顧客との関係を築きながら、商社とメーカーの両視点を活かし、商品企画から販売戦略まで関与するようになりました。
現在は代表取締役として経営全般も担い、さらなる成長を目指しています。
創業の原点とは?たった一人の起業から始まった夢

ディーブレスの創業経緯についてお聞かせください。
2003年、千葉県市川市でディーブレスは誕生しました。
創業者の今井徳英が一人で事業を立ち上げ、前職で学んだ寝具業界の伝手、経験を活かして新たな挑戦をはじめました。
「企画者本人が納得した商品をみなさまにお届けする」という思いが原動力だったと聞いています。
創業当初は、寝具製品の企画と販売を中心に事業を展開。
当時はまだまだ会社規模が小さく、営業力が不十分で、ブランド認知度も低く、顧客との信頼関係を築くのに時間がかかる状況でした。
そのため、まずは仕入れ先との交渉に力を入れ、素材の特長、商品特長の伝え方などを一から再勉強することに注力しました。
創業当初に最も苦労したことは何ですか?
無借金経営を目指していました。そのため、最大の課題は資金繰りでした。
少ない資本で事業を運営する必要があったため、取引先との支払いサイクルを管理することが非常に重要でした。
また、品質にこだわりつつも、コストを抑えて売れる商品を作る工夫も不可欠でした。
仲間との出会いがもたらした成長と新たな挑戦

2008年以降の組織拡大について教えてください。
2008年、新たなメンバー(そのうちの一人が増田)が加わり、組織としての基盤を固める動きが加速しました。
それまで今井一人で運営していた会社は、チームとして動く体制へと変化していきます。
特に注力したのは、展示会への積極的な出展です。新たな顧客とのつながりを築き、販路を広げることに努め、その結果、国内市場にとどまらず、海外市場にも販路を拡大し、事業の幅は大きく広がりました。
また、社内の業務フローの見直し、品質管理、受注発注、適正在庫の管理など、各部門間の連携を強化し、経営体制の確立を目指しました。
海外展開を進める上での課題は何でしたか?
海外市場への進出は、文化や商習慣の違いという大きな壁にぶつかりながらの挑戦でした。
特に、現地の流通網や消費者ニーズが日本国内と全く異なることに戸惑い、多くの時間を費やしました。
なぜ東京へ?勝負をかけた拠点移転の決断

拠点を千葉から東京へ移した背景についてお聞かせください。
事業拡大に伴い、より利便性の高い環境が必要となりました。
業務効率化や取引の円滑化を考えると、立地の見直しは避けて通れない課題でした。
そこで、繊維企業が多く集まる東京・日本橋への移転を決断したのです。
なぜ日本橋を選んだのですか?
仕入れ先との接点を重視した結果、日本橋が最適だと判断しました。
業界の中心地に拠点を構えることで、仕入れの効率化と新たなビジネスチャンスの拡大を見込んだのです。
移転によってどのような変化がありましたか?
日本橋へのオフィス移転後、仕入れ先との打ち合わせや商談の頻度が格段に増え、新素材の情報収集や商品開発スピードが大幅に改善しました。
また、日本橋という立地は採用活動にも好影響を与え、人材が集まりやすくなったことで、社内の活性化にもつながりました。
さらに、オフィス環境の変化によって、社員同士のコミュニケーションが活発になり、業務効率も向上しています。
M&Aという選択が切り開いた新たな事業領域

2018年のM&Aについてお聞かせください。
2018年、ディーブレスは群馬県の寝具製造工場をM&Aで事業承継しました。
それまで企画と販売を主軸に展開していたため、製造業への参入は未知の領域でしたが、会社の成長を見据え、新たな一歩を踏み出すことを決断しました。
M&Aに至った背景は何だったのですか?
事業承継した工場は、以前から取引のあった企業が運営しており、当社の仕入れの約2割を担うパートナーでした。
しかし、経営状況が悪化し、事業の継続が困難になったため、当社に事業承継の話が持ち上がったのです。
M&Aをした決め手は何でしたか?
自社で生産体制を持つことで、品質管理を強化し、商品開発の自由度を高められると判断しました。そこで、新たな挑戦として工場運営に乗り出すことを決めたのです。
メーカーとしての挑戦と試行錯誤の日々

メーカー事業へ進出して、どのような課題に直面しましたか?
販売と製造では業務の進め方が大きく異なり、特に工場の運営には多くの課題がありました。
その中でも最大の課題は、工場の稼働率を安定させることでした。
繁忙期と閑散期で注文量が大きく変動するため、生産ラインにムラが生じやすく、その対策として、裁断や縫製といった加工賃商売や、一部の受託生産を導入しました。
メーカーとして成長するために、どのような取り組みをしましたか?
品質を強みとしつつ、肌触りにこだわった寝具など、他社にはない独自の企画・機能・素材を取り入れた製品づくりに挑戦してきました。
常に試行錯誤を繰り返し、新たな価値を生み出すことを追求しています。
経営のバトンタッチと突然訪れた試練

2021年の経営体制の変化について教えてください。
2021年1月末、創業者の今井が病気で倒れ、経営の第一線から退くことになりました。
突然の出来事により、社内は大きな不安に包まれましたが、事業を止めるわけにはいかず、私が経営を引き継ぐことになったのです。
どのように会社経営と向き合ってこられたのですか?
従業員や取引先の皆様に安心してもらえるように、事業の安定を最優先に経営に取り組みました。
特に、社内の結束を強めるために、ボトムアップの組織運営を重視しました。
経営方針をオープンに共有し、積極的に現場の意見を取り入れ、社員全員が同じ方向に向かって進める環境づくりに努めました。
また、新たなリーダーシップのもと、財務の健全化、情報の見える化、そして日々の業務改善を進め、組織全体のスキルアップにも力を入れています。
現在も経営の変革期ではありますが、ディーブレスはこれからも成長を続けてまいります。
ディーブレスが描く未来とこれからの展望

今後の展望についてお聞かせください。これからの成長に向けて、どのような戦略を考えていますか?
まずは、徹底した日本製へのこだわりを追求しています。
また、お客様のニーズに応えるべく、研究開発を強化し、新しい技術を取り入れた独自性あふれる商品開発を進めてまいります。
さらに、デジタルマーケティングを積極的に活用することで、より多くのお客様にブランドの魅力を伝えていきたいと考えています。将来的には、海外市場も視野に入れ、グローバルブランドとしての地位を確立することを目指します。
最後に、社員一人ひとりを大切にし、それぞれの能力を最大限に発揮できる環境を整えながら、常に新たな挑戦を続けてまいります。