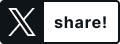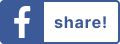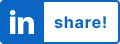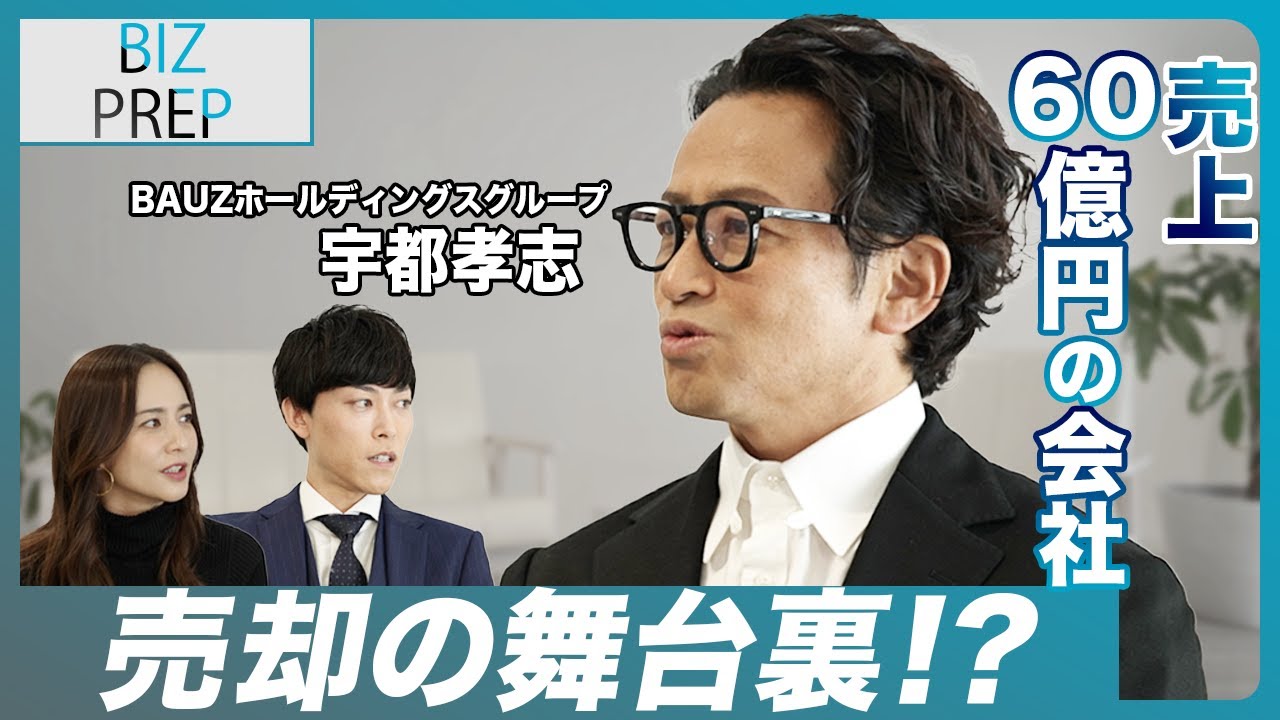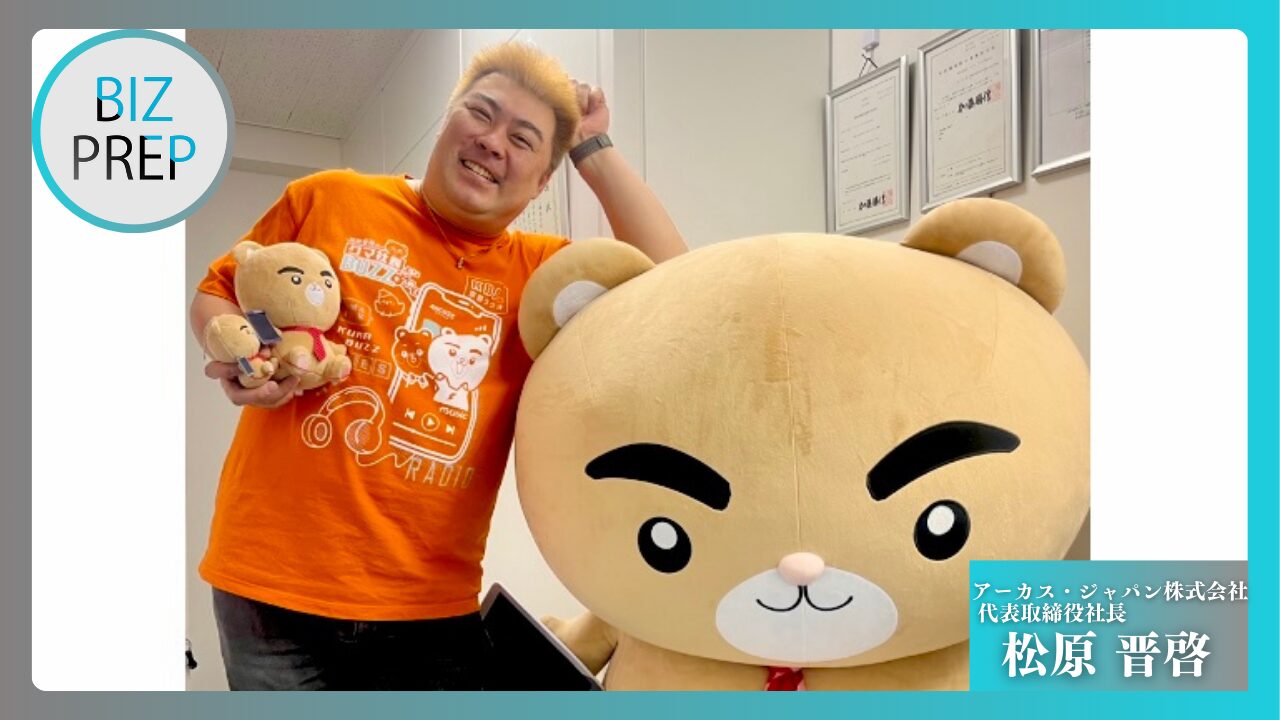目次
他社を知らずに社長就任、事業継承への覚悟
まずは西澤社長のご経歴と、ご創業に至った経緯を教えてください。
実は私、新卒入社後からずっとこの会社しか知らないのです。他の会社での勤務経験がありません。
もともと茨城県の出身ですが、実家の近くにあるつくば市は万博の時期から研究学園都市として発展してきた新しい街でした。周りには旅行好きの友人が多く、将来は地元で旅行会社をやってみたいという漠然とした思いがありました。
就職活動の時期は売り手市場で、誰もが知っているような大手旅行会社からも内定をいただいていました。しかし、この会社を選んだ理由は、とても小さな会社でしたが「本当に好きなことを何でもやらせてくれる」と感じたからです。
転機が訪れたのは2000年頃、私が30歳くらいの時でした。創業者から「会社を任せたい」と言われたのです。その時、「会社を潰そうが何をしようが構わない」とまでおっしゃいました。
しかし、逆にそう言われたことで、この会社を絶対に潰してはいけない、持続可能な企業として次の世代に渡していこうという強い信念が生まれました。
B2C激戦区での学びと限界
当初はどのような事業を展開されていたのでしょうか?
もともとは完全にB2Cで、格安航空券や格安ツアーを主力商品として展開していました。
しかし、その世界は想像以上に厳しいものでした。AB-ROAD(エイビーロード)といった紙媒体がオンラインのポータルサイトへと変化していった頃に1,000円単位ではなく、100円違うだけでお客様の流れが変わってしまうほどの過当競争でした。
確かに安くすればお客様は来ていただけます。しかし、それは値段だけの勝負です。旅行業は前受金制度なので、自転車操業で回してしまう構造になりがちです。忙しいけれども利益があまり出ない、そして社員が疲弊するだけという状態でした。
そんな中、お客様の何割かは出張でご利用いただいている方がいらっしゃいました。このような法人のお客様は積み上げ型で、サービスを評価して継続的にご利用いただけます。この気づきが、後の大きな転換点となりました。
2013年、B2Bへの大胆な事業転換

B2Bへの転換は、どのような経緯で決断されたのでしょうか?
2013年頃に、このB2CとB2Bの比率を完全に逆転させました。B2Bの法人出張市場には、いくつかの魅力的な特徴があることに気付いたのです。
まず、参入障壁があることです。基本的に全て売掛取引で、1〜2ヶ月程度の資金を寝かせる必要があります。そのため、キャッシュのない小さな企業は参入しにくく、B2Cほどの激しい料金競争は起こりません。
また、私たちにはネームバリューがありませんでしたので、米軍基地や官公庁への営業に力を入れました。そうした信頼性の高いお客様との取引実績を積み重ねることで、段階的に企業からの信用を獲得していったのです。
ただし、この段階でもまだ労働集約型のビジネスモデルでした。手数料もある程度高く設定せざるを得ず、使いたくても使えないお客様が存在していました。
その課題をどのように解決されたのでしょうか?
コロナ前の時期に、出張管理のデジタル化に着目しました。当時、法人出張でデジタル化が進んでいたのは、大手企業の一部に限られていました。
そこで私たちは、システムだけでなく人のサービスも融合させたソリューションを提供しようと考えました。なぜなら、出張業務は日時変更が当たり前で、海外出張では夜中の変更や土日の対応も必要になるからです。
純粋なOTA(オンライントラベルエージェント)では、そうした面倒な対応まで手厚くサポートするのは難しいのが現実です。私たちは、システムの利便性と人間のきめ細かいサービスを組み合わせることで、この市場のニーズに応えようと決意しました。
コロナ禍での試練と「Smart BTM」開発

上場準備中にコロナ禍が発生したと伺いました。
実は、コロナが発生した時期に上場準備の最終段階に入っていました。主幹事証券会社の審査部での審査も何度か通過し、年内には上場というタイミングでした。
当然、コロナの影響で一旦は上場を延期せざるを得ませんでした。しかし、私たちにはそれまでに蓄積した資金がありましたので、その資金を使って「Smart BTM」というクラウド出張手配システムの開発を継続したのです。
私たちは絶対にここでいけるという自信がありました。それまで当社は赤字になったことがなかったところ、さすがにコロナの時期は2期連続で赤字になりましたが、会社をスリム化すれば必ず黒字化できると確信していました。
その時の心境はいかがでしたか?
私たちは「ピンチはチャンス」という言葉をよく使ってきました。これは9.11事件の時から一貫している考え方です。
9.11事件が起こったのは、ちょうど私が社長になったばかりの時期で、10月決算の最後の月でした。それまで売上も利益も最高を記録し、「今期はなんとかなりそうだ」と思った矢先の出来事でした。
その時、他社の役員や社員が「テロだから仕方がない」と言い始めたのを見て、これでは絶対に前に進めないと感じました。テロを理由にしていては、社員も動かなくなってしまいます。
そこで私は「その理由を使わずに、今何ができるかを考えよう」と提起しました。その結果、海外旅行だけだった事業を国内旅行にも拡大し、米軍との取引も強化しました。その後SARS(重症急性呼吸器症候群)のアウトブレイクなど様々な危機が訪れましたが、社員たちが自発的に「何ができるか」を考えるようになったのです。
この経験がコロナを乗り切る力になったと確信しています。
デジタル×ヒューマンサービスで業界に新風

御社の競合他社との違いや強みを教えてください。
当社の最大の強みは、BTM(ビジネストラベルマネジメント)市場において、「デジタル×ヒューマンサービス」を融合させていることです。
まず、導入費用とランニングコストを無料にしています。他社のサービスの中には導入や毎月の利用でも多くの費用がかかるものがあります。当社は1件あたりの手数料をいただく形にすることで、中小企業の方にもデジタル化の恩恵を受けていただけるようにしました。
次に、24時間365日対応を自社社員で行っていることです。多くの競合他社はアウトソーシングや外注に依存していますが、当社は自社社員が直接対応します。
なぜ自社社員での対応にこだわるのでしょうか?
緊急時にその場で判断できることが決定的に重要だからです。緊急事態では1万円、2万円の話ではなく、10万円、20万円、30万円の判断が求められることもあります。そうした状況で、お客様のことを理解している担当者がその場で判断し、対応してさしあげることが何より大切です。
実際にあった事例ですが、海外出張中に変更が必要になった際、当社をご利用のA社は日曜日でも変更対応ができましたが、他社をご利用のB社は対応できませんでした。B社の担当者から当社に「A社の分と一緒に変更をお願いできないか」という相談もありましたが、他社の予約記録は操作できません。その結果、次の機会にB社からは新しくご契約いただけることになりました。
また、安価な手数料体系も特徴です。ただし、安いだけでは薄利多売になってしまいます。そこで、バックヤードの効率化に徹底的に投資し、1人あたりの生産性を向上させています。
その他のソリューションについても教えてください。
「Easy Booking」と「トラベルマネージャー」という追加サービスを提供しています。
Easy Bookingは、海外出張に特化したシンプルなセルフブッキングシステムです。個人事業主や病院の先生、大学の先生など、学会出張の多い方のご利用を想定しており、契約後は後払いでご利用いただけます。従来の立替払いが不要で、一括請求で処理できます。
トラベルマネージャーは、やや規模の大きい企業様向けで、稟議申請、危機管理機能、経費精算機能を備えています。どこに社員がいるかをリアルタイムで把握でき、緊急時の安否確認も可能です。これらもSmart BTMに連携可能でして、非常に安価でご提供しています。
さらに、導入後のコンサルティングサービスにも力を入れています。「こうすればもっとコストが下がる」といった提案や、特定の行き先への渡航が多い場合などは航空会社へ特別レートの交渉なども行います。このようなサービスを発券と併せてご提供することで、自然と顧客離れを防ぐ効果も生まれています。
そのため、当社では月間アクティブユーザー(MAU)を重要KPIに設定しています。契約企業数だけでは、実際に使われていない休眠契約も含まれてしまい、正確な実力が見えません。MAUによって、本当に動いているサービスの規模が明確になります。
2025年上場実現、海外展開への次なる挑戦

2025年4月7日に上場を果たされたんですね。
コロナ後、証券会社がなかなか引受けてくれない状況が続きました。彼らにとってもビジネスですから、ある程度の利益実績がないと判断が難しいのです。
最終的に東海東京証券だけが「ここまで来たのであればやりましょう」と言ってくださいました。本来であればもう一期後の方が数字的には良かったのですが、時代の変化は非常に早く、1ヶ月でも2ヶ月でも、まして1年も経てば状況が大きく変わってしまいます。
コロナ後、出張の体制が大きく変わりました。旅行業界から人材が大量に流出し、人手不足が深刻化しています。一方で、出張需要は早期に回復し、海外出張もコロナ前の7〜8割程度まで戻ってきています。このタイミングでシステムを導入していただくチャンスを逃すわけにはいかないと判断しました。
今後の成長戦略について教えてください。
国内市場は人口減少もあり、限界があることは認識しています。そこで現在力を入れているのが、海外発の日本向け出張需要です。
日本企業の海外子会社の方々が日本本社を訪問する際の出張管理や、第三国間での移動にSmart BTMを活用していただく戦略です。海外発のチケット手配は複雑で、現地では対応が困難なケースも多くあります。
これらの需要を取り込むことで、日本企業の本社にとってもガバナンス向上のメリットがあります。グループ全体の出張を一元管理できるからです。
最後に、今後のビジョンをお聞かせください。
私たちの目標は、出張手配をワンストップで完結させるサービスを実現することです。
日本企業の海外進出はますます加速していくと確信しています。そうした企業の皆様のお手伝いができれば、結果的に日本経済全体の発展にも貢献できると考えています。
旅行業界は確かに厳しい面もありますが、工夫次第でまだまだ成長の余地があります。特にB2B市場は、これまで使われていなかった潜在的なお客様がたくさんいらっしゃいます。そうした方々にデジタルとヒューマンサービスの融合によって、新しい価値を提供し続けていきたいと思っています。
私たちは今後も「ピンチはチャンス」の精神で、変化を恐れずに挑戦を続けてまいります。