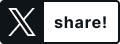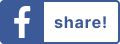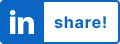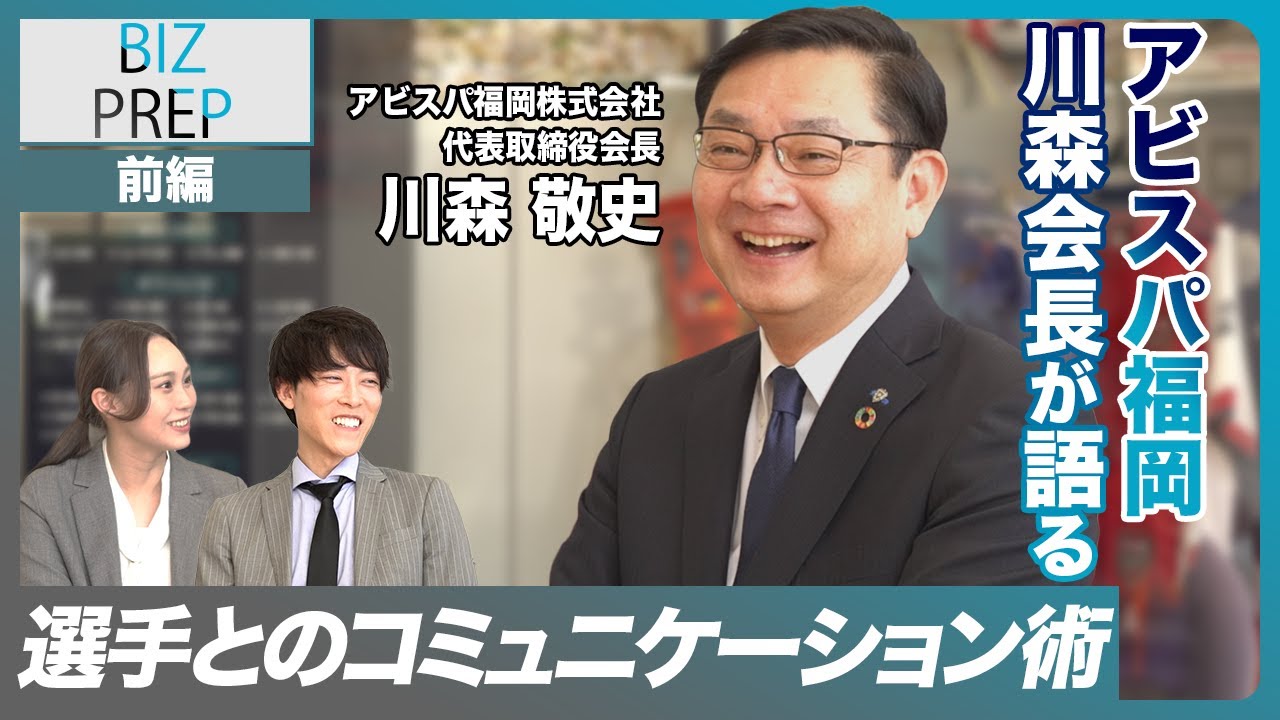目次
祖父から続く65年の歴史と業界の浮沈

まず、御社の創業から現在までの歴史と、中西さんご自身のご経歴を教えてください。
弊社は1961年の創業で、来年で創業65年を迎える会社です。会社法人化は1967年ですが、創業から数えるとまもなく65年という長い歴史があります。基本的にはゴルフの会員権の売買事業をメインに会社を経営してきました。
弊社の創業者は、私の祖父である中西弘安(2025年現在91歳)です。祖父がゴルフ関係の雑誌記者をしていた戦後間もない時期、日本国内でゴルフ場が徐々に開場され始めました。祖父はその機を捉え、ゴルフ場が募集する会員権の二次流通、すなわちセカンダリーマーケットを扱う事業を立ち上げたのです。
現在残っている会員権取扱会社の中で、弊社が最も歴史の長い企業となっています。
私は高校まで愛知県名古屋市で育ち、大学進学を機に上京しました。新卒では日本たばこ産業株式会社(JT)に入社しました。当時は加熱式タバコが市場の過渡期を迎えており、その販売チームで営業職として経験を積みました。
なぜJTから転職されることになったのでしょうか。
約1年半の勤務を経て、安定した大企業ではなく、IT分野や新しい領域に挑む小規模な企業で働きたいという思いが強くなりました。そこで転職したのは、フリーランスエンジニアをマッチングするポータルサイトを運営する企業です。従業員約50名規模で、業界内でも大きく成長している企業でした。
転職後半年ほどでエンジニアリングとマーケティング部門全体を統括する立場へと昇格。約10名の部下をマネジメントする立場になりました。その企業で約2年の経験を積んだ後、現在の家業である日本ゴルフ同友会に入社し、現在まで約3年が経過しています。
バブル崩壊後の30年間の厳しい時代を乗り越えて
ゴルフ会員権業界は、バブル期とその後で大きく変化したと聞いています。
はい、その通りです。高度経済成長期からバブル期にかけて、ゴルフ場が急激に増加しました。戦前は全国で100コース程度しかなかったのが、約30〜40年ほどで一気に3000〜4000コースまで膨れ上がったのです。それに伴い、会員権の市場も大きく拡大しました。
弊社もこの時期に急成長を遂げ、東京、大阪、福岡といった主要都市に拠点を拡大しました。さらに、各地の主要百貨店にサービスコーナーを設置するなど、事業の多角化も進めました。会員権の価格は不動産バブルと軌を一にして高騰し、超一流とされる首都圏のゴルフ場会員権が億単位の最高値を記録するなど、まさにバブル絶頂期を象徴する出来事でした。
しかし、1990年代から徐々に陰りが見え始め、株価や不動産の下落とともに会員権も大幅に値下がりしました。そこから2020年頃までの約30年間は、価格も右肩下がり、マーケットボリュームも縮小し続け、会員権を取り扱う会社も次々と廃業していくという厳しい時代でした。
その30年間の厳しい時代を、どのように乗り越えてこられたのでしょうか。
最も大きな要因は、東海地区での圧倒的なシェアを維持できたことです。名古屋から事業を始めたこともあり、ゴルフ場の立ち上げ時から関わっているケースも多く、東海地区は非常に狭い商圏なので人とのつながりが重要視される土地柄でもあります。
独自の情報網やつながり、長年培ってきた知識をお客様へ提供することで、高水準のシェアを維持してきました。
弊社の強みは、愛知県の企業、特に自動車産業をはじめとする製造業との長年にわたる深い信頼関係です。その結果、現在でも東海地区だけで10コース以上のゴルフ場について、弊社独自のネットワークを通じてのみ会員権を取り扱うことが可能です。これは、他社にはない圧倒的な優位性を築けていることを意味します。
そもそもゴルフ会員権の売買仲介は、そのサービス内容において業界全体の標準化が進んでおり、提供される情報の差も小さくなっているのが実情です。だからこそ、弊社は愛知県で築き上げた強固な基盤と顧客優先の理念を最大の武器とし、他の追随を許さない独自のネットワークを通じて、厳しい時代においても安定した売上と利益を確保し続けることができました。
コロナ禍で見えた新たなチャンス

2020年頃から市場が反転したとのことですが、どのような変化があったのでしょうか。
2019年頃を底として、ここ直近5、6年は市場が反転しています。会員権の価格も大幅に上昇し、ゴルフ人口も微増ではありますが増加に転じています。
最大のきっかけはコロナでした。密を回避できるスポーツとして、ゴルフに新規参入する方が急激に増えたのです。
その結果、ゴルフ場の予約が取りにくい状況が生まれ、「それならメンバーになろう」という意識が高まりました。この流れがゴルフ業界全体の活性化に繋がり、ゴルフ会員権市場も大きく拡大しています。この上昇基調は現在も継続しており、地域差はあれど、特に関東圏では顕著な価格上昇が見られます。
この市場回復の波に乗るために、どのような取り組みをされたのでしょうか。
私の入社は市場回復の波と見事に一致しました。私は前職でのIT企業の経験から、エンジニアリングとマーケティングの知見を活かし、Webによる顧客獲得を最重要課題と定めました。
業界全体が長年の慣習に頼り、デジタルシフトへの対応が遅れていた中で、私自身が新しい世代の経営層として、このWeb分野で負けるはずがないという強い確信を持ってイノベーションを推進しました。
IT企業出身者が持ち込んだデジタル戦略
具体的にはどのようなデジタル施策を実施されたのでしょうか。
まず、従来の看板広告からリスティングやバナー広告といったWeb広告へシフトしました。同時に、オウンドメディアの立ち上げやYouTubeチャンネルの開設を通じて情報発信を強化。SEO対策もしっかりと実施するなど、Web施策の基礎を徹底的に固めることから着手しました。
これらの施策は、他業界から見れば決して特別なものではありません。しかし、デジタル対応が遅れていた業界内では誰も手掛けていなかったため、短期間で大きな効果が現れたのです。結果として、Webからの集客は指数関数的に伸び、弊社の業績は大幅に拡大しました。
中でも特に効果的だったのがYouTubeチャンネルの運営です。ゴルフ会員権に関する継続的な情報発信により、現在では業界内で一定の認知を獲得し、多くの方にご視聴いただいています。これにより、業界内での存在感を確固たるものにすることができました。
従来は東海地区中心だった事業が、全国展開できるようになったということでしょうか。
その通りです。愛知県のシェアは従来から高く維持できていましたが、東京支店はそれまでほとんど売上が立っていない状況でした。しかし、Webでの集客により、基本的に関東圏のお客様を獲得できるようになり、東京支店の売上が大幅に伸長しました。
毎年20%〜30%以上の成長を続けており、現在では名古屋本社と東京支店の2拠点体制で、全国のゴルフ会員権の売買を手がけています。また、愛知県の松坂屋名古屋店内にサービスコーナーも設置しています。
東海地区での圧倒的シェアとその理由
東海地区で圧倒的なシェアを維持できている理由をもう少し詳しく教えてください。
東海地区、特に愛知県は地域が非常にコンパクトで、人とのつながりが重要視される特殊な商圏です。弊社は創業時からこの地域で事業を展開しており、多くのゴルフ場の立ち上げ段階から関与してきた歴史があります。
また、愛知県は自動車産業をはじめとする製造業が盛んで、そうした企業の経営層や役員の方々とは、ビジネスを超えた人間関係として長年にわたり深くお付き合いいただいています。
その結果、現在では東海地区だけで10コース以上のゴルフ場について、他社にはない特別な取り扱いをさせていただいています。これは、ゴルフ場側が弊社を指定して販売を任せてくださっているということであり、お客様にとっては、その会員権の購入に弊社を通す必要があるという、揺るぎない地位を築けていることを意味します。
――その強力な信頼関係は、どのようにして築かれてきたのでしょうか。
これは長年にわたる信頼関係の積み重ねに尽きます。ゴルフ場の経営者の方々にとって、会員権の販売は単なる仲介業務ではありません。弊社は、売買仲介だけでなく、ゴルフ場の運営に関するアドバイスや、会員の皆様へのきめ細やかなサポートも含めた総合的なサービスを提供してきました。
顧客本位の営業体制や経営姿勢が長きにわたり、多くのステークホルダー(顧客、ゴルフ場)に支持され、揺るぎない信頼へとつながったと考えております。
また、愛知県という地域特性も深く関わっています。新しい企業や外部の企業がいきなり参入しても、なかなか受け入れられにくい土地柄です。弊社は地元企業として長年の実績があり、地域の皆様から深く信頼していただいているからこそ、このような強い協力関係を築くことができたのだと考えています。
業界の二極化と今後の展望
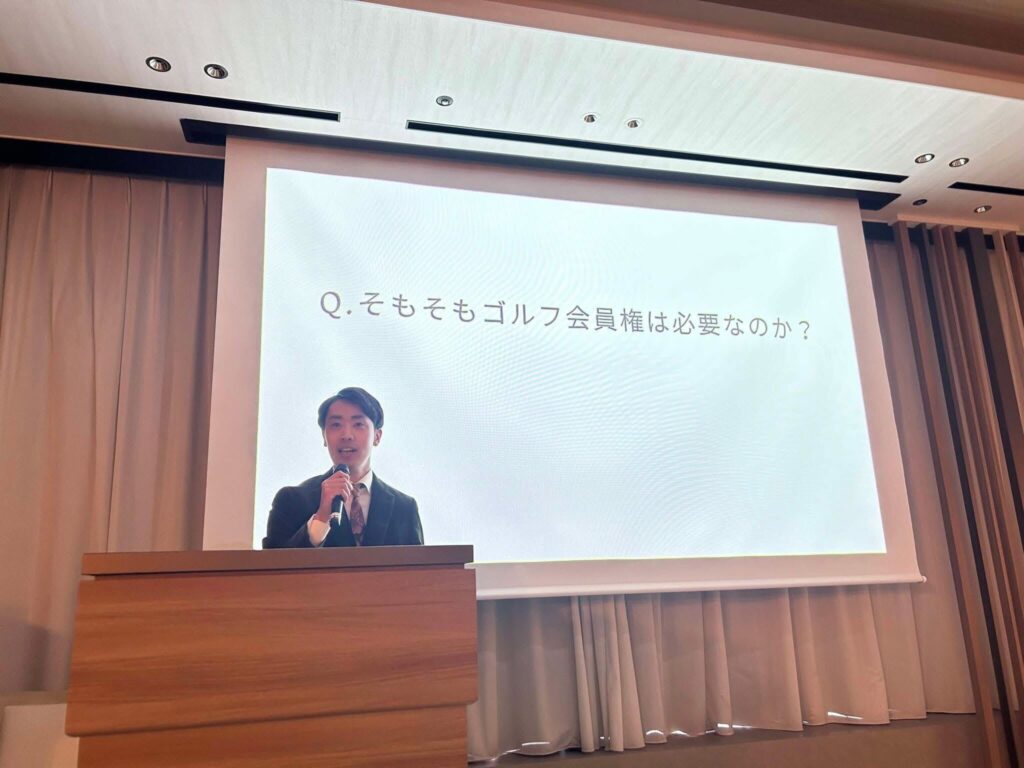
今後、ゴルフ会員権業界はどのように変化していくとお考えですか。
業界全体として、今後10年程度は成長が続くと楽観的に見ています。現在の価格上昇は投資目的ではなく実需に基づくものなので、急激に価格が崩れるようなことは考えにくいと思います。
ただし、ゴルフ場自体は大きく二極化していくでしょう。従来多くのゴルフ場がハイグレードなメンバー制として運営されていましたが、今後はより明確に分かれていくと予想しています。
弊社が主に取り扱うのは、全国約4,000コースのうち上位5%程度にあたる約200コースの優良ゴルフ場です。これらのコースは、富裕層や、一般的な大衆コースとは一線を画した高品質なゴルフ環境を求める方々に、今後も継続的に支持されていくでしょう。
一方で、市場全体を見ると、従来のメンバー制を維持することが難しいゴルフ場が増えています。中には事業形態を転換し、メガソーラーなどの代替事業へ移行するケースも見られます。また、富裕層が買収しプライベートコースとして運営する動きや、安価な料金でオープンプレー(非会員制)を中心とする営業に切り替えるゴルフ場も増加しています。
このような市場の二極化が進む中で、弊社が扱う優良コースの価値は、今後ますます高まっていくと確信しています。
御社のポジションとしては、どのような戦略を考えていらっしゃいますか。
会員権を取り扱う会社も同様の二極化が進むと考えています。インターネットが普及し、情報を簡単に取得できるようになったことで、サービスに大きな違いがない業界では、信頼性、過去の実績、担当者の知識、提供できるコンサルティング内容などで差別化を図る必要があります。
業界の約7〜8割は5人以下の小規模な会社や個人事業主のような形態で運営されています。特別な免許などが不要であったため、比較的容易に参入できる事業でした。その結果、多くの小規模事業者が乱立する競争の激しい市場環境が形成されていました。
しかし、今後は事業承継の問題や、規模の経済による競争力の差で、小規模事業者は厳しくなっていくでしょう。弊社としては、より多くのお客様にご満足いただけるよう、コンサルティング提案の内容をブラッシュアップし、弊社の魅力やお客様にとって有益なコンテンツをより積極的に発信していくことで、さらなる成長を目指していきます。
弊社の長年の歴史が証明しているとおり、顧客本位の営業は必ず報われると信じています。
webやYouTube、などのコンテンツ発信やこれからのサービス提供においてもこの姿勢は変わらず、真摯に顧客およびゴルフ業界の発展に寄与していきたいです。
老舗ベンチャーとして挑戦し続ける
御社が所属するコミュニティや地域社会に対して、特別な取り組みはありますか。
現在、特に大きな社会貢献事業は展開していませんが、今後はゴルフを通じたコミュニティの形成に取り組んでいきたいと考えています。
多くのゴルフ場会員権の購入には紹介者が必要であり、単に費用を支払うだけでは入会できないケースが少なくありません。ゴルフ場のメンバーシップは一つのコミュニティであるため、紹介者がいないために入会を諦めてしまう方も多くいらっしゃいます。
そこで弊社は、そうした方々同士を繋いだり、紹介者を適切にご紹介したりするマッチング機能を、新たなコミュニティとして発展させていきたいと考えています。定期的にコンペを開催するなど、単なる会員権の売買仲介を超えた付加価値の提供を目指します。
業界内で認知を獲得しているYouTubeチャンネルなどのプラットフォームも活用し、ゴルフを愛する皆様により豊かで充実したゴルフライフを提供できるよう、コミュニティ形成を推進してまいります。
最後に、御社のPRや今後の展望について教えてください。
弊社も他社同様、人材が不足しています。業績も順調に伸びており、まだまだやりたいことがたくさんあるなかで、積極的に採用を進めています。
弊社は長い歴史を持つ会社ですが、直近3年ほどは20〜30代のエネルギッシュで向上心にあふれた社員が多く加わっています。ゴルフ業界を会員権の視点からよりよくしていきたい、盛り上げていきたいという熱意を持った社員が集まっており、まさに「老舗ベンチャー」のような雰囲気があります。
ゴルフに興味があり、そうした環境で一緒に働きたいという方がいらっしゃれば、ぜひお声がけいただきたいと思います。ゴルフ経験の有無は問いませんが、新しいことに挑戦する意欲と、お客様に喜んでいただけるサービスを提供したいという気持ちを持った方と一緒に働けることを楽しみにしています。
私たちは単なる会員権の売買仲介業者ではなく、ゴルフを愛する皆様の豊かなゴルフライフをサポートするコンサルタントとして、今後も成長し続けていきたいと考えています。