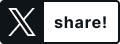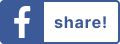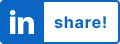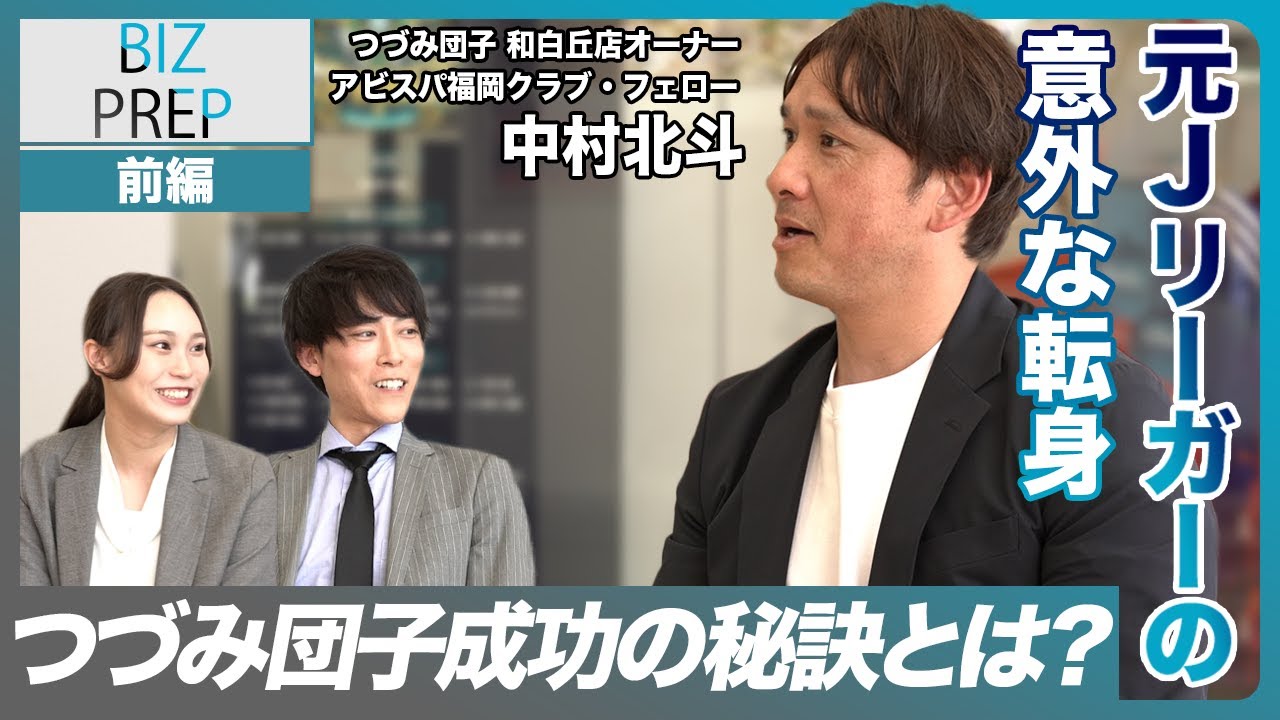目次
製薬会社MRからの転身。業界の課題に気づいた瞬間
まず、右高さんご自身の経歴と、起業に至った経緯を教えてください。
2019年に東京理科大学の薬学部を卒業後、田辺三菱製薬株式会社という製薬メーカーにMR(医薬情報担当者)として入社しました。薬学部出身者の多くは薬剤師になりますが、私は製薬メーカーの待遇面が魅力的だったのと、外に出ていろんな人に自分の価値を発揮したいと思い、営業の道を選びました。
入社当時、幸運にも営業として突出した成績を残すことができ、「自分ならこの業界を変えられるかもしれない」という、ある種の根拠のない自信が芽生えていました。
しかし同時に、MRという職業の将来に対する強い危機感も覚え始めていました。
どのような危機感だったのでしょうか?
MRは本来、医師に対して薬を紹介し、患者さんにとって最適な治療を提案する役割を担っています。しかし近年、規制が非常に厳しくなり、医師とのリレーションシップで薬が選ばれることを防ぐため、接待のようなものは一切禁止になりました。また、自社の製剤のエビデンスしか説明できなくなり、他社製品との比較も困難になったのです。
エビデンスは各社とも揃えていますから、結局どれが正しいかを営業個人で判断することができず、会社に言われた特徴だけを伝えるだけの存在になってしまいました。「これでは自分が介在する価値があるのだろうか」と強く感じたのです。医師側も同じように感じていたようで、面会を断られることも増えていきました。
この現状に対して、「何か新しいことを始めて、この業界を変えられるような人になりたい」という思いが強くなっていきました。
そこから起業までは、どのような道のりがあったのですか?
MRを2年ほど続けながら、まずはビジネスの基礎を学ぶ必要があると考え、経営学修士(MBA)を取得するため大学院に通い始めました。会計やマーケティングなど、経営に必要な知識を学ぶうちに、起業家や事業を作る人たちとのコミュニティができていったのは、今振り返ると自分にとって大きな財産になっていると考えています
まず、大企業に所属する人向けの起業支援プログラム「ONE JAPAN」に参加しました。当初は、医師間でやり取りされる紙の紹介状をデジタル化(DX)する事業を考えていました。しかし、試行錯誤を重ねた結果、医療機関と関わる中で、「人が足りない」という課題が非常に深刻であることに気づいたため最終的にSNSを活用した現在の採用支援事業へと辿り着きました。
現状では、人材を確保するには紹介会社を使うしかなく、一人あたり100万円ものコストがかかってしまいます。そこで、SNSで病院を紹介し、動画を見た看護師さんが「この病院ちょっと自分の目で見てみたいな」と思えるような、新しい採用モデルを開拓できるのではないかと考えました。
南海電鉄が支えた日本でもまだ珍しい出向起業モデル。大企業を飛び出し、新事業を生み出す舞台裏

株式会社メドエックスの設立経緯について教えてください。
実は、関西の鉄道会社である南海電鉄が事業の後ろ盾となっており、私は現在、南海電鉄の社員として出向起業という形態をとっています。
この事業は、南海電鉄の起業家支援プログラム「beyond the Border」を通じて実現しました。これは、外部の起業家が会社を辞めずに事業を推進できるよう、最大300万円の資金を支援するという仕組みで、私はこのプログラムに応募し、ステージゲート制で厳格な審査を受けました。
「そもそも解決すべき課題があるのか」という検証から始まり、最終的に「収益性があり、上場可能なマーケットサイズがあるのか」という判断の期間があり、昨年12月にやっと承認を得ることができました。そして今年3月に南海電鉄に転職し、4月に株式会社メドエックスを設立にいたったわけです。
非常に特殊なスキームですね。
大企業が外部から人材と事業を迎え入れ、出向という形で起業をさせる仕組みは、これまでほとんど例がありませんでした。新規事業を社内で立ち上げるケースは多いですが、すでに外部で挑戦している起業家を社員として迎え入れ、そのまま会社を設立させるという手法は極めて画期的だと思います。
しかも、株式のほとんどを私が保有しており、会社は非連結子会社という形態をとっています。つまり、自分の会社でありながら、南海電鉄の強固なバックアップを受けられるという、非常に恵まれた環境といえます。親会社の影響を受けない高い独立性がありながら、大企業の信用力も得られる。このスキームには本当に感謝していますし、今後も第3期、第4期と続いていく予定とのことですので、ぜひ起業を考えている方にはチャレンジしていただきたいですね。。
SNS採用支援における唯一無二の強み
医療機関向けのSNS採用支援を行う会社は他にもあると思いますが、メドエックスの最大の強みは何でしょうか?
大きく分けて2つの強みがあります。
1つ目は、「医療機関に特化したSNS運用のノウハウ」です。看護師さんに向けて、どういう発信をすれば再生数が伸びるのか、そしてそれが採用につながるのか、この二つの両立は非常に難しいポイントとなります。
例えば、介護施設などでもSNS代行業者が入っていて、10万再生、3万再生といった高い数字は出ているのですが、採用につながっていないという悩みを抱えています。それは、「あるある」のような伸びやすいコンテンツを作っているだけで、その施設や病院の特徴を伝えていないからです。視聴者は楽しめても、「ここで働きたい」とは思わないのです。
私たちは、病院の一日の流れや特徴をきちんと伝えながら、なおかつ再生数を伸ばすというバランスを実現しています。これができているのは、今のところ私たちだけだと自負しています。
2つ目は、「医療機関の実情に合わせた柔軟なオペレーション」です。
他の業種と違い、医療機関では広報活動は二の次、三の次になりがちです。。他の業種のように広報に力を入れたからといって売上が上がるわけではなく、常に患者様の治療を最優先しなければなりません。ですから、SNSコンテンツを作りたいという気持ちはあっても、そこに割けるリソースは非常に限られているのです。
他社の場合、月に1回撮影に行くといった定期的な対応が基本ですが、それでは医療機関の負担が大きすぎます。私たちは、病院の都合に合わせて最小限のリソースで運用できる仕組みを構築しています。
これが可能なのは、医療機関だけに特化しているからです。他の会社が同じオペレーションを組もうとすると、コストが高くなりすぎて採算が合わなくなってしまいます。医療機関に特化することで、このオペレーションと成果の両立を実現できています。
チームメンバーに医療経験者がいらっしゃるのですか?
はい。私自身が薬剤師免許を持っていますし、チームメンバーにも医療経験者がいます。この業界理解が非常に重要になります。
例えば、病院に撮影に入ったとき、カートがきちんと整理されているかどうか。これは看護部長経験がある人が見れば、「ここはしっかりしている」とすぐに分かるポイントなのですが、そういった細かいけれど重要な点をピックアップして、動画のコンセプトに落とし込むことができる。これが、通常のSNSバズ狙いの撮影とは決定的に違う点です。
医療業界では特に信頼が重要で、これまでは個人間の口コミで全てが決まってきました。しかし業界理解がある人間が発信に関わることで、SNSがその信頼を得るツールとなりえます。
メディッチというアカウントについても教えてください。
メディッチは、私たちが提供するSNSを活用した看護師特化型のマッチングサービスです。様々な病院を紹介するリール動画を作成し、そこから実際に看護師さんと病院がつながるという実績が出ています。
多くのSNS代行会社は、このような自社メディアを持っていません。これは私たちの大きな特徴です。メディッチで看護師さんとの接点を作り、認知を広げると同時に、現在はLINEを活用した新しい求人サイトも開発中です。TinderのUI(ユーザーインターフェース)のように、気軽に使えるマッチングアプリ形式を構想しています。
右にスワイプすればキープ、左にスワイプすればスキップといった、使いやすいインターフェースで、求職者だけでなく一般層にも広くリーチできるのがSNSの大きな強みです。従来の紹介会社が職を探している人しか対象にできなかったのに対し、私たちはより広い層にアプローチできるのです。
さらに、こうした自社サービスを持つことで得られたノウハウを、クライアントへの運用代行にも活かしています。この「サービス開発」と「運用代行」の両輪を回している点が、私たちの決定的な独自性です。
医療業界の未来を変える、潜在看護師70万人への挑戦
今後の展望について教えてください。
私たちの最終目標は、「医療従事者が笑顔で働ける世界を作る」ことです。
医療業界は離職率が非常に高く、労働集約型のビジネスです。人がいないと一人にかかる負荷が高くなり、さらに人が辞めていくという悪循環に陥っています。現在、潜在看護師と呼ばれる、資格を持ちながら現場で働いていない方が約70万人もいるとされています。
様々な理由で現場を離れている方々がいますが、このうちの5%の方でも現場に戻ってこられる仕組みを作れば、人手不足で病棟を閉鎖する、あるいは一人にかかる負担が多すぎて辞めてしまうような状況を変えられるのではないかと考えています。
具体的にはどのようなサービスを考えていらっしゃいますか?
現在、現場から遠ざかっている方々でも、安心して戻ってこられるようなサービスを開発しています。
SNSの良さは、求職者以外の一般の方にもリーチできることです。従来の紹介会社は、職を探している人しか登録していませんが、SNSを通じて「医療業界に興味がある」「スキマ時間で働けるなら」という潜在的なニーズを持つ人たちにもアプローチできます。
短時間・単発の労働に特化したスキマバイトサービスも医療業界への進出を試みていますが、業界理解が不足しているためうまくいっていません。私たちは、SNSというラフで気軽な入口を作りつつ、医療業界特有の信頼関係を大切にしながら、人材と医療機関のマッチングを実現させたいと考えています。
業界全体としては、今後どのような変化が予想されますか?
少子高齢化が進む中、働ける人材は限られています。海外から人材を受け入れ、高額な費用を支払ってでも人を集めなければならない状況は、今後さらに激しくなるでしょう。その結果、採用市場における病院側の立場は弱まり、「こんなに高い費用を払わないと人が来てくれないのか」「本当はこうした手段をとるのは気が進まないが、背に腹は代えられない」といった医療機関側の苦悩が悪化していくと考えられます。
地域医療では、人手不足で機能しなくなる場所も出てくるでしょう。私たちが取り組むべきは、日本に約70万人いる潜在看護師や、医療業界に関心を持つ外部人材をマッチングさせる仕組みを作ることです。
人が本当に足りなくなるという危機的な状況を阻止できるよう、私たちは今後も積極的に新しい仕組みを構築していきたいと考えています。
上場についてはどのようにお考えですか?
上場は一つの通過点として考えています。私自身、この医療業界を変えた人材として、「右高」という人がこの業界に貢献したと言われるような存在を目指しています。
私たちの目標は、今進めているSNS事業を売却して終えることではなく、医療業界に大きな変化をもたらす会社、そして人になることです。そのためには、メドエックスを大きく成長させる必要があります。例えば、採用に関するBPOが必要であれば、関連企業をM&Aで積極的に迎え入れるなど、多角的な手法で事業を広げていきたいと考えています。
会社を大きくし、医療業界になくてはならない存在になる。そのための一つの通過点として、上場があるのだと思っています。
受注よりも人材育成。医療知見とSNS運用、両輪を回す戦略

現在、最も注力されていることは何ですか?
受注よりも、案件をこなしていく力の強化です。つまり、人材育成ですね。
医療に知見があると同時にSNSの運用能力も持つ人材が必要です。ただ、両方を最初から持っている人は少ないため、医療機関での勤務経験がある方を採用し、SNS運用については私たちが教えていくという方針をとっています。
逆に、SNSの代行会社で経験を積んだ人が医療機関の支援経験もあるという場合、その方を採用してしまうとノウハウだけ渡して終わってしまい、競合になってしまうリスクがあります。
ですから、医療機関で働いていた方で、現場に対して「もっとこうしたい」という思いを持っている方、そしてこれから成長していく会社で働きたいという方を求めています。
業界理解を持つ人材の確保が最大の課題なのですね。
その通りです。ありがたいことに案件自体は口コミ含めて増えてきております。それをこなしていく体制作りが最大の課題です。
例えば、フリーランスの薬剤師がSNS運用に取り組んでいるケースもありますが、その場合、医療の知見はあっても、SNSを成長させるノウハウがありません。逆に、SNS運用は得意でも、医療に関する専門知識がない人もいます。
私たちは、医療の知見とSNS運用能力の両方を持つチームを作ることで、他社にはない価値を提供し続けられると考えています。編集も、できる人はたくさんいますが、あえて看護師さんにお願いするなど、業界理解を重視した体制を構築しています。
最後に、メドエックスの今後についてメッセージをお願いします。
医療従事者の方々は、本当に大変な環境で働いていらっしゃいます。人手不足で一人ひとりの負担が増え、それでも患者様のために歯を食いしばって毎日頑張っている。そんな方々が笑顔で働ける世界を作りたいというのが、私たちの原点です。
現在、採用に悩んでいる医療機関の方、また医療業界に興味があるけれど一歩踏み出せないでいる方、ブランクがあって不安を感じている潜在看護師の方々。メドエックスは、そんな皆さんをつなぐ架け橋になりたいと考えています。
SNSという新しい入口を通じて、医療業界に新しい風を吹き込み、誰もが笑顔で働ける未来を実現していきます。この思いに共感してくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひ一緒に医療業界の未来を変えていきましょう。