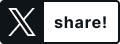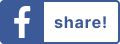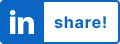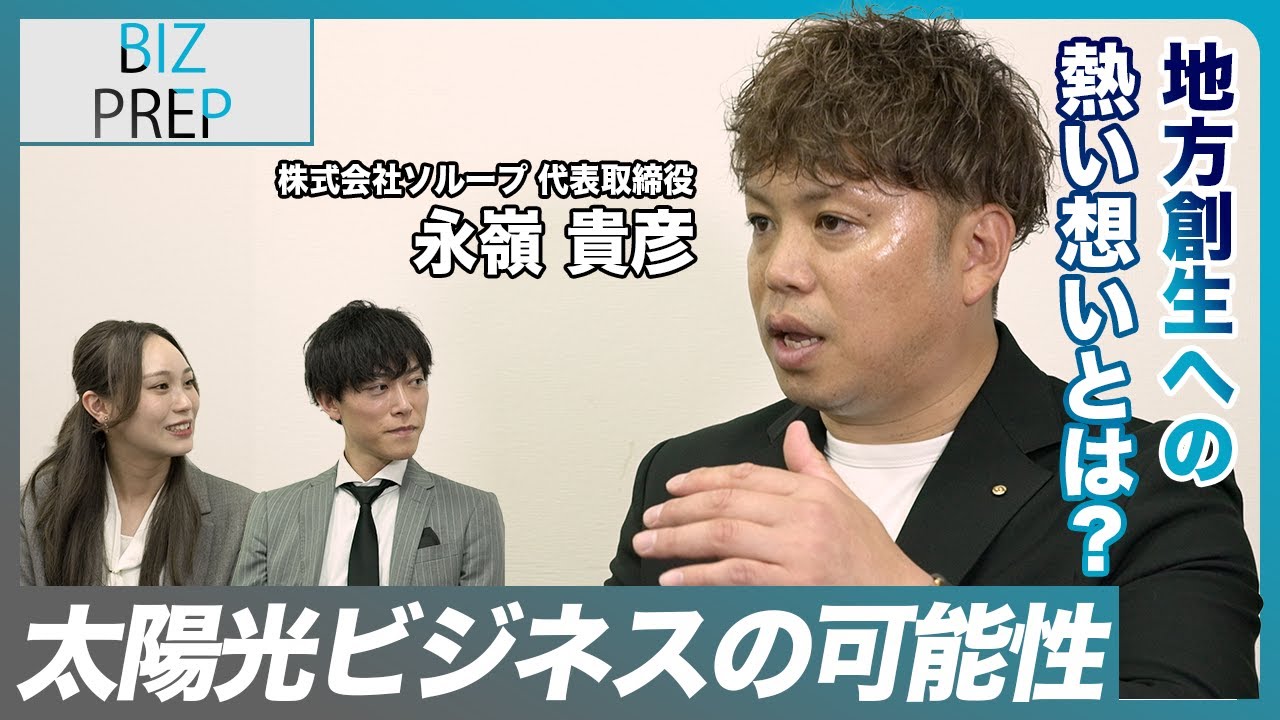目次
通信業界の変化を見据え、創業早期から携帯電話事業へ参入
まず、御社の創業から現在に至るまでの経緯と、社長ご自身の経歴について教えていただけますでしょうか。
弊社は昭和60年1月に、先代である私の父が創業いたしました。当時はまだNTT(日本電信電話公社)の民営化前でしたが、父はこの民営化をビジネスチャンスと捉え、通信業界で起業したのです。
当初はNTTの特約店として、ビジネスフォンのレンタルから買取への変換サービスを手がけていました。当時、ビジネスフォンはレンタル制が一般的でしたが、買取制はお客様にとって有利な条件だったため、売上を順調に伸ばすことができました。
その後、NTTからNTT移動通信網の九州エリア(現在のNTTドコモ)の商材として、ポケットベルや車載電話の販売も始めるようになりました。この流れから、平成6年2月にドコモショップ小倉北店を1号店としてオープンしたのです。
私自身は平成13年に社長に就任いたしました。先代が体調を崩したため、比較的早い段階で経営を引き継ぐことになったのです。当時の私の役目は、携帯電話の急速な普及に合わせて店舗を拡大していくことでした。
携帯電話事業が順調に拡大していく中で、印象に残っているエピソードはありますか?
一番印象深いのは、平成15年に手がけたドコモショップとカフェのコラボレーション店舗ですね。これは私が社長になってから初めて大きく挑戦した事業でした。
当時、小倉の隣にリバーウォークという商業施設ができまして、ドコモさんから出店権利をいただいたのですが、条件が1階の路面店だったのです。ところがリバーウォークさんは、携帯ショップは3階・4階のインショップエリアで、1階はカフェやアパレルのエリアということで許可をいただけませんでした。
どうしてもドコモショップを出店したかった私は、「カフェとドコモのコラボレーション店舗」という提案をしたのです。そこから「フードサービス事業部」を立ち上げることになりました。
カフェとドコモショップの革新的コラボレーションで新たな挑戦

そのコラボレーション店舗は、どのようなコンセプトで作られたのでしょうか?
店舗デザインには相当こだわりました。Time & Styleという東京のデザイナーに店舗設計を全面的にお任せして、ショーケースからカフェ部分まで、統一感のある洗練されたデザインで仕上げたのです。
結果的に、その店舗は地元で非常に話題になりました。しかし、ケーキやサンドウィッチは自社で製造する技術がなかったため、知人の会社から仕入れていました。ところが、その仕入先が経営状況の悪化により立ち行かなくなってしまったのです。
そこでM&Aを決断されたということですね。その時の心境はいかがでしたか?
正直、大きな決断でした。しかし、せっかく軌道に乗り始めたカフェ事業を継続するためには、やるしかないと思ったのです。その会社はスイーツショップとカフェを運営していたため、買収により一気に3店舗体制となりました。
M&Aによって事業規模が拡大し、カフェだけでは月数百万円程度だった売上が、きちんとビジネスとして成り立つ規模まで成長させることができました。これが私にとって初めてのM&A経験で、後の経営判断にも大きな影響を与えました。
M&Aによる事業拡大と世界遺産登録を機に生まれた転機
スイーツ事業への本格参入はどのようなきっかけだったのでしょうか?
カフェ事業を3年ほど運営する中で、スイーツのお持ち帰り需要に可能性を感じました。地方のスイーツショップを分析してみると、パッケージデザインやブランディングにあまり投資していないことに気づいたのです。
そこで2005年に洋菓子店「グラン ダ ジュール」をオープンしました。デザインや品質にこだわることで、地域で差別化を図ることができました。ただし、オーナーパティシエではない私たちが5店舗、10店舗と拡大していくのは現実的ではないと感じ、メーカーになることを目指しました。
大きな転機となったのは、2015年7月に官営八幡製鉄所関連施設が世界文化遺産に登録されたことです。その際に「世界遺産のお土産を作ってみないか」というお話をいただき、「ネジチョコ」の製造・販売を開始しました。
「ネジチョコ」はどのような商品なのでしょうか?
これは、3Dプリンター技術を活用して作る、組み立て式のチョコレートです。単なるお土産ではなく、「感情を揺さぶるスイーツ作り」をテーマに開発しました。
お土産の本質は、コミュニケーションツールにあると私たちは考えています。従来のスイーツは、「見た目がいい」「味が美味しい」「かわいい」といった要素が中心でした。しかし、私たちが重視するのは、「面白い」「遊びたくなる」「人に教えたくなる」といった、人の感情を揺り動かす体験なのです。
30年の事業を手放す決断—携帯ショップ事業からの戦略的撤退
長年の主力事業から撤退された背景を、お聞かせいただけますか?
これは非常に悩んだ決断でした。最盛期は6店舗まで運営していましたが、撤退時には4店舗まで減っていました。
大きな要因は二つあります。一つは、携帯電話がオンライン中心になり、リアル店舗の必要性が今後なくなっていくだろうという予測でした。もう一つは、深刻な人材不足です。
地方では特に人材確保が厳しく、他の事業部には良い人材が集まるのですが、中小企業の携帯ショップには思うような人材が集まらなくなっていました。派遣スタッフで何とか運営していましたが、2〜3年先はともかく、10年スパンで考えた時に、中小企業では立ち行かないと判断せざるを得ませんでした。
30年間続けてきた事業を手放すのは、相当な決断だったと思います。
本当にそうでした。社員も50名ほどいましたし、みんな一生懸命働いてくれていました。だからこそ、社員に迷惑をかけないような形で撤退することを最優先に考えました。
全社員に対して現在の給与以上の条件で転職先をあっせんし、有給も全て買い取り、退職金もきちんとお支払いしました。まだ会社に体力があるうちに決断したからこそ、社員の皆さんに最大限の配慮ができたと思っています。
撤退により得られたメリットもあったのでしょうか?
はい。全店舗が自社店舗だったため、店舗をそのまま大手代理店に10年間の定期借地で貸し出すことで、安定的な不動産収入を確保できました。
この収入基盤ができたことで、成長事業であるスイーツ事業とシステム事業に経営資源を集中できるようになったのです。
この「選択と集中」により、今では両事業とも大幅に売上を伸ばしています。時々「もう少し携帯事業を続けていても良かったのでは」と思うこともありますが、あの時の決断に後悔はしていません。
3Dプリンターで創る「感情を揺さぶるスイーツ」の差別化戦略
改めて、現在のスイーツ事業の特徴的な取り組みについて詳しく教えてください。
弊社のスイーツ事業は「ネジチョコラボラトリー」を軸に、3つの事業で構成されています。ネジチョコ事業、コラボレーション事業、エモーショナルスイーツ事業です。
「感情を揺さぶるものづくりを未来へ」というビジョンのもと、単に美味しいスイーツを作るのではなく、お客様の心を動かす体験を提供することを重視しています。
3Dプリンター技術を活用することで、従来では不可能だった形状のチョコレートを製造できるのが大きな強みです。最近では、トヨタさんやJALさんといった大手企業からもコラボレーションのお話をいただいています。
他社との差別化ポイントはどこにあるのでしょうか?
最大の差別化要素は、商品開発のスピードです。多くの企業から「こんなに早く商品化できるのは驚きだ」という評価をいただいています。
また、小ロットで安価にオリジナル商品を製造できる点も強みです。大手メーカーでは対応が難しい案件でも、弊社なら柔軟に対応できます。
技術的な面では、私自身がパティシエ出身ではないからこそ、新しいテクノロジーを積極的に取り入れることに抵抗がありませんでした。この発想の転換が、従来のスイーツ業界にはない商品を生み出す原動力となっています。
現在の事業規模や今後の展開について教えてください。
スイーツ事業は現在、組み立て式チョコレートの「ネジチョコ」を軸に、全国の空港や土産物店で販売しています。羽田空港、沖縄の那覇空港など、北九州以外の地域でも順調に売上を伸ばしています。
今後は海外展開も視野に入れており、現在はアメリカ、香港、オーストラリアで販売を開始しています。先日も中国を訪問し、現地での合弁事業について協議を進めました。中国では冷凍スイーツの製造・販売を計画しています。
北九州から世界へ—地方企業が描く海外展開戦略

地方企業として海外展開を進める理由と戦略について教えてください。
北九州だけでビジネスを続けるのは限界があると感じています。地方都市はどんどん人口が減少していくため、ターゲット市場が縮小していくのです。インバウンド需要がある地域は別ですが、北九州の場合は地域だけでの商売は難しくなっていくでしょう。
そこで「ネジチョコ」を北九州以外でも違和感なく販売できるよう、組み立てて飛行機になる「飛行機サブレ」を開発しました。これにより羽田空港でも販売できるようになったのです。
さらに、トヨタさんとのコラボレーションで組み立て式の車やサーキット関連商品も製造しており、地域に依存しない商品開発を進めています。
システム事業の方はいかがでしょうか?
システム事業は現在、NTTの代理店として順調に成長しています。中小企業の人材不足による生産性向上ニーズやセキュリティ対策の需要増加により、市場全体が拡大している状況です。
現在は代理店6社と連携しており、今後はM&Aによる事業拡大も検討しています。業績が振るわない小規模事業者の買収について、メーカーにも相談を持ちかけているところです。
他社との差別化としては、飲食事業も手がけているという新規性や、若い営業スタッフによる親しみやすいアプローチが評価されています。お客様からの紹介案件が非常に多く、地域でのイメージも良好です。
副業推奨とアスリート支援で築く独自の企業文化
人材採用や社員の働き方について、特徴的な取り組みはありますか?
弊社の大きな特徴は、副業を積極的に推奨していることです。
実は私自身がトライアスロンに取り組んでおり、明日から北海道でアイアンマンレース(水泳3.8km、自転車180km、ランニング42.2kmの過酷なレース)に参加します。
社員の中にも日本代表を目指すトライアスロン選手がおり、今朝も午前5時45分から、みんなで3kmのスイム練習を行いました。私たちは、こうした社員一人ひとりの夢や目標を、会社として全面的にサポートしています。
採用はどのような方法で行っているのでしょうか?
実は、NPO法人など地域活動をしている団体から採用することが多いのです。一緒に地域活動をしたり、トライアスロンで汗をかいたりしている中で、「この人と一緒に働きたい」と思える人に声をかけています。
現在、システム事業部に1名、スイーツ事業部に2名のアスリートが在籍しており、今後もこうした採用を拡大していきたいと考えています。
仕事と趣味・夢の両立についてはどのようにお考えですか?
私はよく「仕事と趣味を融合させる」と言っています。例えば、今回の北海道レースでも、現地でロイズ(ROYCE’)の工場見学をしたり、JALグループの北海道地区の会社さんとの打ち合わせを入れたりしています。
個人の夢や目標がある人の方が、仕事でも高いパフォーマンスを発揮する傾向があります。だからこそ、売上だけでなく個人の夢も尊重し、フォローしていく方針を取っています。
結果的に、優秀な人材が集まってきていますし、社員のモチベーションも非常に高い状態を維持できています。
今後、どのような人材を求めていらっしゃいますか?
現在、特に求めているのはマネージャークラスの人材です。システム事業部では、代理店展開を加速し、独立支援ができるような営業経験者を募集しています。一方、スイーツ事業部では、3年以内の工場移転と見学施設化の計画があるため、食品製造の専門知識を持つ40代前後の方を求めています。
いずれのポジションも、単に業務をこなすだけでなく、弊社の理念である「感情を揺さぶるものづくり」に共感し、一緒に新しいことに挑戦していける方を歓迎します。副業を認め、社員の夢や目標を全面的にサポートする当社は、「自分の夢も追いかけながら働きたい」という方にとって、理想的な環境だと確信しています。