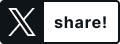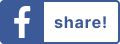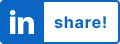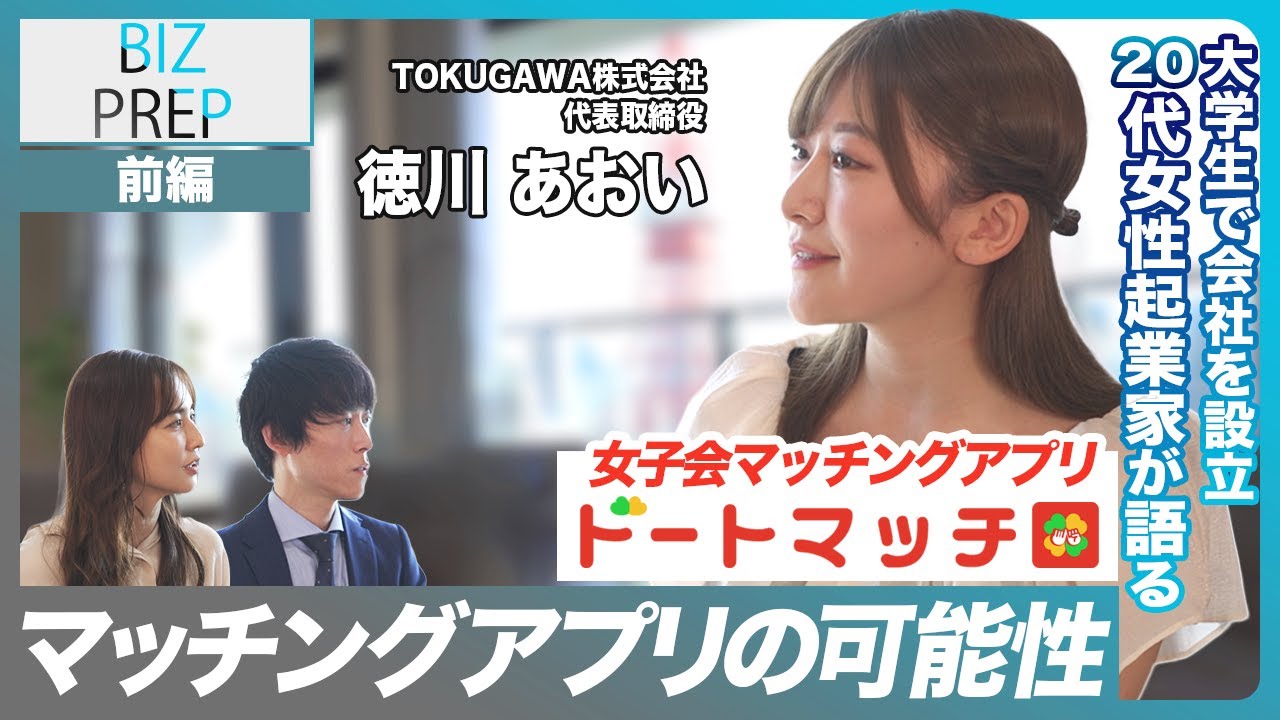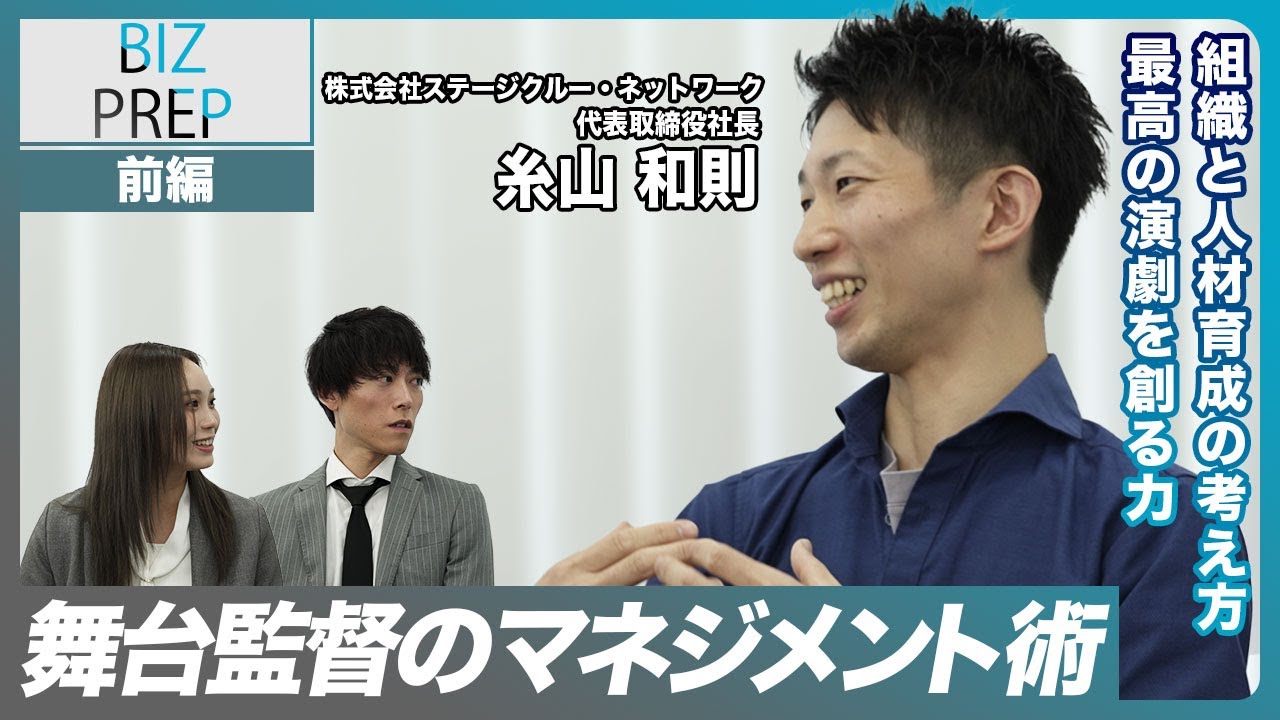目次
祖父の創業から続く70年の歴史、OEMではなく自社ブランドを貫く

まずは御社の創業から現在に至るまでの経緯を教えていただけますか。
弊社は1953年に私の祖父が創業いたしました。創業当時は「南出商会」という名前でしたが、後に「南出メリヤス」に変更しています。
戦後間もない頃でしたので、とにかく安くて良いものを提供するということで、肌着などを製造し、世の中に供給していくところから始まりました。
時代が進むにつれて、下着だけではなく、一枚で着られるカットソーなどデザイン性の高いものを作っていこうという方向に舵を切りました。現在の社長である私の父が会社に入った頃から、この方向転換が始まったのです。
弊社が昔から大切にしてきたことの一つに「OEMに頼らない」ということがあります。最近はOEMから脱却して自社ブランドを立ち上げる流れが一般的ですが、弊社は昔から自分たちで作ったものを自分たちのネームで販売することを貫いてきました。
製造から小売りへの進出、自社ブランド展開への方針転換は、どなたの発案だったのでしょうか。
父と私が一緒に考えて進めました。これは世の中の流れでもありましたし、私自身もそう思っていたからです。
現在は、もともとのカットソー工場に加えて、セーター工場や洗い加工工場など、様々な工場を持っているため、あらゆるアイテムを日本製で提供することができます。コロナの1〜2年前にはオンラインストアも立ち上げ、現在は小売りと卸売りの両方で事業を展開しています。
大学卒業後すぐに入社、ゼロからの営業開拓
南出専務の個人的な経歴についても教えていただけますか。
私は大学で経済学を学んでいたので、その知識を活かして会社に貢献したいと考え、卒業後すぐに実家の会社に入社いたしました。
入社前からいろいろな可能性を感じていましたし、父と話をする中で「これから面白くなりそうだ」という感触があったからです。
入社後はすぐに営業を担当することになりました。当時はお客様のリストがない状態でしたので、自分でインターネットで調べて、アプローチして、一件ずつ仕事を獲得していくという感じでした。
自分で合同展示会を探して積極的に参加し、お客様や同業メーカーなど多くの繋がりを作ることが出来ました。その時できたつながりは今でも大切にしています。
またコロナの数年前には営業から離れ、ネット販売の立ち上げにも挑戦してきました。初めてのことで難しいことも多かったですが、プログラミングや画像編集ソフトなど多くの事を勉強でき、とてもいい経験でした。
自社工場を持つ強み「物語のあるものづくり」
同業他社との差別化や御社の魅力について、どのようにお考えですか。
工場を持っているということが、一番大きな違いだと思います。
現在、ファクトリーブランドも増えていますが、多くのファクトリーブランドは特定のアイテムしか作っていません。靴下のファクトリーブランドなら靴下だけ、TシャツのファクトリーブランドならTシャツだけという具合です。それはそれで強みだと思いますし、海外に販売する際も分かりやすく受け入れられます。
しかし、弊社の場合は、セーターの工場、カットソーの工場など、すべての工場を持っているため、お客様が求めるあらゆるアイテムを日本製で提供することができます。うちのテイストにハマった方は、弊社のブランドで買い物をすれば日本製のあらゆるアイテムが手に入るという独自性があります。
工場を持っていることの最大の利点は何でしょうか。
スピードなどもちろんありますが、一番は「物語があること」だと思います。自社工場があることで歴史が生まれます。
品質の話をすると、外注で作っていても、外注先が品質に協力してくれれば良いものは作れます。また自社工場でも良いものを作ろうという意志がなければ、良いものは作れません。また品質はあくまでも物のレベルの話に過ぎません。
物が良いという前提の上で、さらに工場を持っていることの強みは、そこに「物語」が生まれることだと思います。これが弊社の大きな差別化要因です。
実店舗の失敗からECサイト成功へ、コロナ禍が追い風に

これまでの事業で印象に残っている成功体験と失敗体験を教えてください。
大きな失敗は、今から10数年前に京都の寺町に出店したリアル店舗ですね。
当時はまだノーブランドの状態で、価格で勝負しに行ったのですが、そこで失敗してしまい、店舗を閉めることになりました。おそらく一番痛い失敗だったと思います。
この失敗の教訓から、現在も父はリアル店舗の出店に反対しています。
一方で、5年ほど前に始めたネットショップは非常にうまくいっています。結果としてリアルで失敗してウェブで成功したため、今はウェブ重視の戦略になっていました。しかしちょうどコロナの1〜2年前にウェブサイトを立ち上げていたので、運が良かっただけかもしれません。
ECサイトが出来たとこでは変わった点はありますか。
ECサイトの最大の効果は、情報発信の仕組みができたことだと思います。
例えば、卸販売だけでは広告費を回収できないですが、自社オンラインストアがあることで、YouTube広告や雑誌広告なども積極的に活用できるようになりました。
オンラインストアがあるからSNSでの発信も効果的になり、発信量が増えることでファンも増えるという好循環が生まれています。これが売上以上に大きな貢献をしていると感じています。
EC開始時に社内から反対はありませんでしたか。
リアル店舗の失敗があったため、「ウェブしかない」という感じで父が判断し、大きな反対はありませんでした。
ただし、大変だったのは、当時卸営業が私ともう一人の2人しかいなかったことです。2人で数億円の売上を担っていたので、新しく入った営業にこの売上を引き継ぐのは、会社の屋台骨を任せるようなもので、かなり緊張感がありました。
消費者目線を大切にした経営姿勢
日々の経営で大切にされている考え方や心構えを教えてください。
どれだけ消費者の気持ちを考えられるかだと思っています。
ECサイトを立ち上げるまでは卸売り販売しかしていなかったので、お客様はバイヤーでした。しかし、自分で小売りを始めると、お客様が消費者になります。
例えば、以前なら「このくらいの商品なら、このくらいの価格であれば大丈夫だろう。」と思って値段を決めることもありました。またバイヤー様から「ちょっと縫製が曲がっているから返品したい。」と言われても「このくらいで許してくれよ。」と思う時もありました。
しかし、自分が実際に消費者様と接するようになると「ちょっと縫製が曲がっているだけでも、やはり嫌なものは嫌だ」ということが心底分かるようになりました。
また、お客様がどういうことに喜ぶか、どういう言葉をかけるべきか、「ありがとう」と言われた時にどう返すかなど、そういう言葉一つでお客様がブランドのファンになるかどうかが決まるという事も実感しました。
それを自分で体感したからこそ、お客様目線でいることがとても大事だと今は思っています。この視点を大切にこれからも経営していきたいと考えています。
産地創造を目指す未来への挑戦

今後、業界と御社はどのように変化していくとお考えですか。
アパレル業界は世界で見ると人口が増えているのでしばらくは成長産業ですが、日本では確実に衰退産業です。特に日本国内のものづくりは如実に小さくなってきており、現場では60歳以上の方々が中心となっているような年齢構成になってきています。これは本当に困ったことで、このままでは日本で服が作れなくなってしまうということをよく話しています。
私は、そこに一石を投じたいと思っています。若い人が働きたいと思うような日本の服づくりの現場にしていかなければ、産業として成り立たなくなります。これは誰かがやってくれると思っていたら、絶対にやってくれません。
実際、弊社がある泉州産地には、若手経営者が少なく、あきらめムードが漂っている会社も少なくありません。だから私たちがやるしかないのです。そうでなければ産業がなくなってしまいます。
若い人がアパレル業界に興味を持つような、かっこいいアパレル現場を作ることが、私の目標です。
将来的にはどのような会社にしていきたいとお考えですか。
産業・文化の創造が私のやりたいことです。
純粋に日本の文化がなくなることはとても悲しいと思います。今まで作れていた日本の服を作れなくなる、産地の生産基盤がなくなることは本当に悲しいことです。
そうならないためには日本だけでなく海外にも当然進出しなければなりません。日本だけで少ししか売れていないブランドでは、若い人たちは魅力を感じませんし、かっこよくありません。やはり日本でも人気があり、海外でも人気があるから憧れるのです。
産業を作ろうと思ったら、売上も一定規模になる必要があります。10億円程度では産業として回りません。100億円くらいの売上があって、初めて産業として成り立ちます。
これは弊社だけではなく、この産地全体を100億円を超える新たなアパレル産地として成り立たせていくことが、私の使命だと考えています。
最後に、御社のPRをお願いします。
弊社のビジョンは「産地の創造」です。産地を作るところからやりたいという人を求めています。
単に「ものづくりが好きで、自分でものづくりをやってみたい」という人はあまり向いていません。そういう人はやってみて「思っていたのと違う」となってしまう可能性があります。
そうではなく、「一緒に地域を良くしていきましょう!」「日本の文化を守っていきましょう!」「日本製ファッションで日本や世界の未来を明るくしましょう!」という考えに共感できる人、自分で考えて行動していく人には、とても向いていると思います。
そう言う人にとっては非常に面白い仕事だと思いますので、ぜひ一緒にやりましょう。
個人の方だけでなく、同じビジョンを持つ法人の方との連携も大歓迎です。