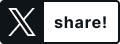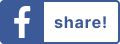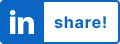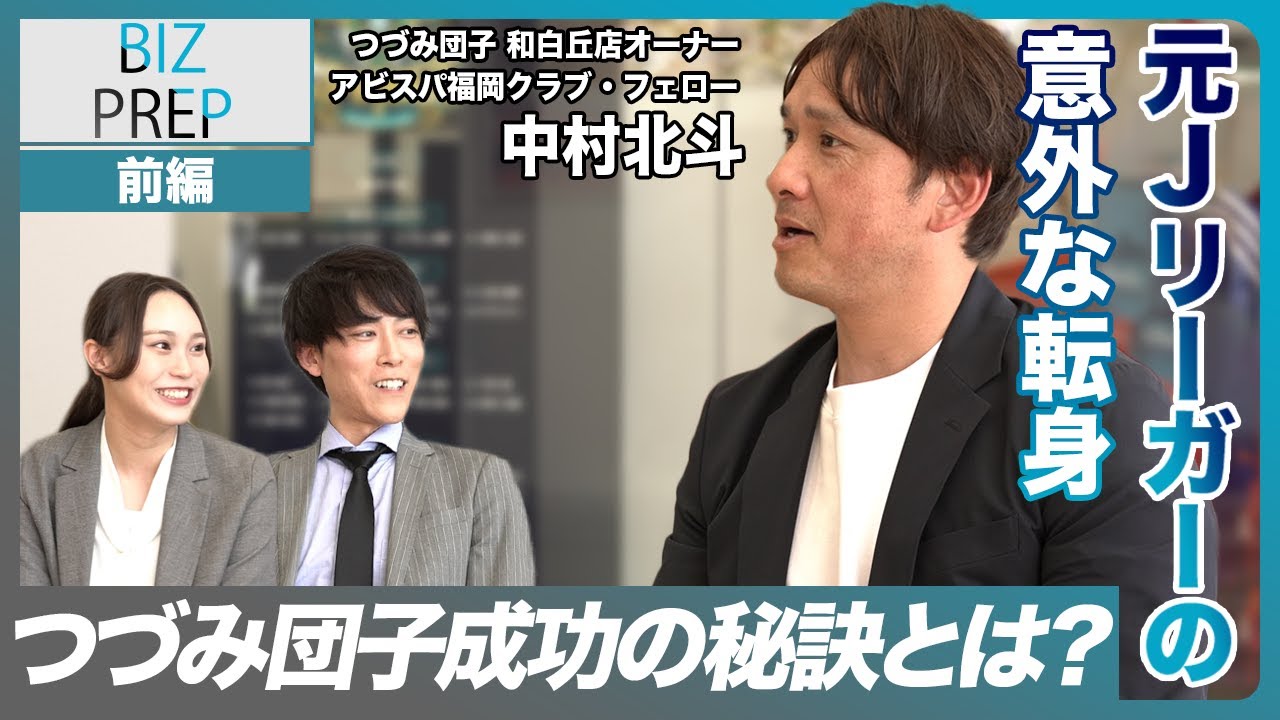目次
インターネット広告黎明期から始まったデジタルマーケティングの歩み
まずは、大学卒業後から現在に至るまでのキャリアについて詳しくお聞かせください。
大学卒業後は、インターネット広告がまさに黎明期を迎えていたタイミングで、急成長中だったデジタルエージェンシーに入社し、アカウントプランナーとしてデジタルマーケティングの営業やプロジェクトマネジメントを担当しました。
当時はまだWeb広告という概念自体が浸透しておらず、手法や技術も確立されていない時代。毎日が試行錯誤の連続で、分析環境も今のように整っていなかった分、自分の仮説と実行力、そして工夫が成果に直結していました。まさに“地殻変動の中に身を置く”ような日々だったと思います。
型や分業が整っていない、属人的で泥臭い時代でしたが、その分、若手でも責任あるポジションを任され、実戦で鍛えられた8年間でした。昼夜問わず働き続けるような日々ではありましたが、その濃密な経験が、今の自分の土台を築いたと実感しています。変化を恐れず、手を動かしながら思考し続ける──そんなスタイルは、この時代に培われたものです。
その激動の中で、どのような成果を上げられたのですか。
ありがたいことに、ほぼ全ての社内のアワードを受賞したり、歴代の達成記録を塗り替えたりと、一定の成果を残すことができました。
特に印象的だったのは、あるクライアントの売上を大きく伸ばすことができたプロジェクトです。当時は、データ分析の手法も今のように洗練されておらず、ツールも限られていました。そうした制約の中で、自分なりの仮説を立て、広告設計や配信ロジックを徹底的に作り込み、PDCAを何度も回す──まさに“創意工夫と執念”のプロジェクトでした。
そうした実行フェーズのやりがいは非常に大きかった一方で、長く同じ環境で経験を重ねるうちに、「もっと企業の意思決定そのものに踏み込みたい」「戦略レベルから関与したい」という思いが芽生えるようになりました。広告運用やマーケ施策の“その先”にある、経営や事業の在り方そのものに興味が広がっていった感覚です。
外資系コンサルティングファームでの上流工程経験がもたらした視野の拡大
その後のキャリアの転換点について教えてください。
2015年頃、より上流から企業課題に関わりたいという思いを実現すべく、外資系の総合コンサルティングファームに転職しました。ちょうど国内でも「デジタルトランスフォーメーション(DX)」という概念が広まり始めたタイミングで、私はその波の先端に立つ形で、デジタル変革を専門とする新組織の立ち上げ期に参画しました。
ここでは、これまでの広告や施策実行といった“手段の最適化”とは異なり、企業全体のビジネスモデルや戦略そのものを描く視座が求められました。マーケティング戦略の設計はもちろん、CDO(Chief Digital Officer)直下での全社DXプロジェクトの推進や、組織構造そのものの再設計にも関わることができたのは、大きな転機でした。
経営層と向き合いながら、事業や組織の在り方そのものを問い直す経験を通じて、「手を動かすことに強みがある自分だからこそ、経営レイヤーの意思決定を現場で“実装できる力”が重要だ」と強く感じました。
この経験が、のちにMassive Actを立ち上げる際の思想──“変革の起点を創る”というミッション──に直結しています。
そこでの経験で、特に印象深かったことはありますか。
最も学びが大きかったのは、「正しいこと」が常に「実行されること」ではない、という現実です。
一つの施策を実行するにも、複数の部門や役員、時には社外のステークホルダーとの調整が必要で、たとえ技術的・論理的に“正解”があっても、組織内の力学や政治的背景によって方向性が大きく変わる。コンサルティングという立場で、経営層と現場の間に立つからこそ、こうした「組織のリアル」に向き合うことになりました。
この経験を通じて痛感したのは、デジタルや戦略の知識だけでは物事は動かせないということ。人を巻き込み、共に進める力──つまり“実行推進力”がプロジェクトを成否を分ける鍵になるという視点を得られたのは、自分の中で非常に大きな転換点でした。
この気づきが、のちに独立して事業を創る際にも大きな指針となりました。どんなに優れた戦略も、現場に実装されなければ意味がない。だからこそ、戦略と実行の間に橋を架けること。それが自分の役割だと、今も強く思っています。

設立1社目の成功と挫折から学んだ組織運営の本質
独立への道のりはどのようなものだったのでしょうか。
2社目のコンサルティングファームを退職後、これまでの経験とご縁を活かし、Web広告代理店を立ち上げました。
もちろん、初めからうまくいったわけではありません。コンサルティングファームでの経験はあったとはいえ、実際に自分で組織をつくり、売上をつくり、人を束ねていく──それはまったく別次元の挑戦でした。
正直、不安も大きかったですが、結果的には1年半で売上11億円を達成することができ、一定の成果は出せたと思っています。ただ、順調な数字の裏には、いくつもの壁や苦い経験もありました。
特に痛感したのは、「組織は仕組みだけでは動かない」ということ。制度や目標を整えるだけではなく、個々人の想いや相互理解、人としての信頼関係こそが組織の推進力になるという、当たり前だけど本質的な気づきを得たのがこの時期でした。
この成功と挫折の両面が、現在のMassive Actの組織づくりや経営方針のベースになっています。
その成功の要因は何だったのでしょうか。
一番大きかったのは、デジタルマーケティング業界で積み重ねてきた経験と人脈です。
クライアントの課題解決に向けて、業界構造を深く理解したうえで提案・実行まで伴走できたこと、またスピード感と柔軟性を持って案件を動かせたことが、短期間での信頼獲得と事業拡大につながったのだと思います。
ただ、今振り返ると、この成功が自分を大きく狂わせた側面もありました。事業が軌道に乗るにつれ、「成果を出すこと」や「利益を最大化すること」ばかりに意識が向き、最も大切にすべきメンバーとの関係を疎かにしてしまったんです。ともに立ち上げを支えてくれたメンバーが、私自身の変化─言い換えれば慢心や独善─に耐えきれず、最終的には全員が離れていきました。
あのとき、どれだけ数字の上では成功していたとしても、信頼が崩れた組織に本当の意味での持続性はないということを、身をもって知りました。この失敗が、今の「メンバードリブン経営」の根底にある考え方──仲間の存在を第一に考えるという思想──につながっています。
その時の心境を詳しくお聞かせください。
当時は業績も好調で、数字という目に見える成果に手応えを感じていたぶん、「組織として今、何を大切にすべきか」を見つめ直すことを、どこか後回しにしていた自覚があります。
そんな中で、あるメンバーから投げかけられたひと言が強烈に刺さりました。
「僕たちは、どこを目指しているんですか? 何のために、ここにいるんですか?」
正直、その瞬間、明確に答えられなかった自分がいました。給料も出している、仕事の成果も出ている──でも、それだけでは人はついてこない。むしろ、数字だけを評価軸にしてしまったことで、“一緒に進む意味”を伝えられていなかったんだということを、痛烈に思い知らされました。
この経験は、経営者としての私にとって、最も重たい原体験の一つです。それ以来、「組織として何を目指すか」「メンバーがどんな状態で働けるか」といった“内側の問い”を、自分に課し続けるようになりました。
事業の成否だけでなく、“誰と、どんな想いで成し遂げるか”を定義し続けること──それが、今の私の経営スタイルの出発点になっています。
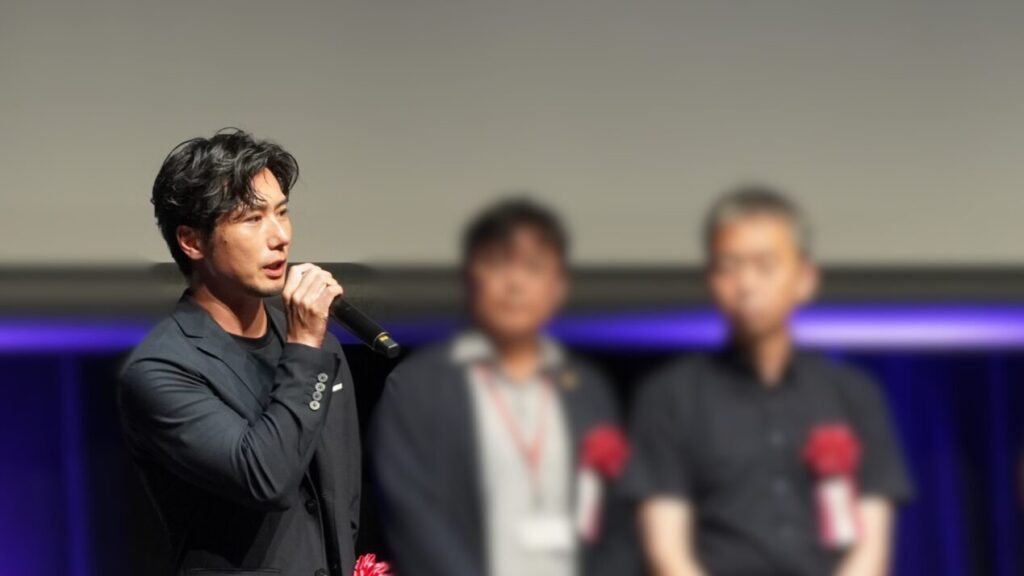
みなし残業ゼロで追求する真の生産性向上への取り組み
その失敗を経て、現在の会社を立ち上げられたのですね。
はい。前職での苦い経験を踏まえ、「もう一度、人を大切にする組織を自分の手でつくろう」と決意し、完全自己資本で現在の会社(Massive Act)を設立しました。
当初は個人事務所のような形でコンサルティング業を行っていましたが、2021年から本格的に法人化し、組織としての体制を整え始めました。
この会社では、利益至上主義を完全に排除し、メンバーが安心して力を発揮できる環境づくりを何よりも優先しています。たとえば、残業時間や有休消化率は徹底的に管理し、また就業規則や労務管理も、弁護士・社労士・税理士と連携しながら法令順守と透明性を徹底しています。
私にとって、「本質的な生産性」とは、単に時間あたりのアウトプットを高めることではなく、メンバー一人ひとりが健やかに、納得感を持って働ける状態を保つことだと考えています。そうした環境こそが、結果的に企業としての持続性と成果を両立する──その確信があるからこそ、仕組みでそれを支えています。
御社の働き方について、特徴的な取り組みがあるとお聞きしました。
当社では、業界では一般的とされている「みなし残業制度」を一切採用していません。残業代は1分単位で全額支給し、時間に対する正当な対価をきちんと支払う仕組みを徹底しています。
この業界では、月45時間〜60時間程度の“みなし残業”を前提とした給与設計が多く見られますが、それは言い換えれば、他社は弊社と同じ給与で3か月分多く労働してもらうことが可能な構造でもあります。
私たちは、そうした前提に疑問を持ち、「限られた時間の中で、最大限の価値を出す」ことを本質的な生産性と定義しています。
単なる制度の違いではなく、「働く人の時間に誠実である」という文化的な選択です。だからこそ、1時間あたりのアウトプットには高い基準を求めますし、メンバーにも“時間で評価されるのではなく、価値で評価される”という意識が自然と根づいています。
結果として、健全かつ高密度な働き方が実現できており、それが組織としての強さにもつながっています。
そのアプローチは、どのような効果をもたらしているのでしょうか。
最も大きいのは、「時間あたりの価値創出」に対する意識が、全メンバーに自然と根づくことです。
残業前提の働き方を排除している分、限られた稼働時間の中で最大限の成果を出す必要があり、必然的に思考の質・解像度・設計力に磨きがかかります。私たちは、フレームワークや分析手法の高度化に日常的に取り組んでおり、“早くて浅い”ではなく、“早くて深い”提案ができることが強みです。
特にデジタルマーケティングやDXのプロジェクトでは、同じ数字を見ても「どう読み解き、どこに打ち手を置くか」で成果が大きく変わります。その解釈力や構造化力こそが、クライアントに提供できる本質的な価値だと思っています。
当社は決して大所帯ではありませんが、業界経験豊富なベテランと、高いポテンシャルを持つ若手が混在しており、一社ごとに深く向き合うスタイルを徹底できているのも大きな要素です。「短時間で成果を出すこと」に真剣に取り組むからこそ、他社と比較しても圧倒的な密度で、思考と実行を提供できていると自負しています。
具体的にはどのような違いが生まれているのですか。
一例を挙げると、他社では10の工数をかけて行うような分析業務を、私たちは1で完了させることができます。これは単なるスピードの問題ではなく、課題の構造化・仮説設計・検証プロセスの一つひとつが高度に設計されているからこそ実現できる成果です。
さらに、私たちは汎用的なオペレーションをなぞるのではなく、各クライアントの事業特性・顧客構造・組織状況にまで踏み込みながら、本質的な意思決定支援となるような提案を行っています。こうした深度のあるコンサルティングが可能になるのは、時間に対する厳密な設計と、個々のメンバーのプロ意識が両立しているからだと思います。
もちろん、こうしたスタイルにはトレードオフもあります。
高い基準での思考や成果が求められる分、ワークスタイルやカルチャーがフィットしない方にとっては、厳しい環境と感じられるかもしれません。
ただ、そのぶん私たちは「安易に拡大しない」という選択をしています。小規模でも、プロフェッショナルとしての誇りと成果の質にこだわる組織であること。それが、Massive Actの文化であり、競争優位の源泉だと考えています。

AI時代に必要な「人ならではの価値」を見極める人材戦略
業界の今後のトレンドについて、どのようにお考えですか。
今後は間違いなく、「人間にしかできない価値とは何か」が、あらゆる業界で問われる時代になると思っています。
当社ではそうした存在を「X人材」と呼んでいて、推進力・プロジェクトマネジメント力・コーディネート力・巻き込み力など、“複数の力を掛け合わせて価値を創る人材”を育てることに注力しています。
今後、型化された業務やルーティンワーク、定型的なレポート作成・メール文作成・データ集計などは、ほぼ確実にAIによって自動化されていきます。実際に、すでに多くの領域でAIの方が速く、正確に処理できるようになってきています。
ただ一方で、AIが出したデータを「どう読み解き」「どう動かし」「誰を巻き込み」「どんな未来に接続するか」──こうした意思決定と推進は、今もなお“人”にしか担えない領域です。
私たちは、そうした“人ならではの価値”を見極め、発揮できる人材こそが、AI時代の本当の競争力になると考えています。だからこそ、X人材の育成と評価を、組織戦略の中核に据えています。
人材育成において、重視されているポイントは何ですか。
まず大前提として、その人のパーソナリティや素養を最も重視しています。スキルは後からでも習得できますが、どんな環境でも周囲と誠実に向き合い、責任を持って物事を前に進められるか──そうした「人としての姿勢」が、最終的な成果を大きく左右すると考えているからです。
特にAI時代においては、「何をAIに任せて、何を自分で判断・実行するか」を見極められることが、人材としての本質的な価値になると思っています。
文章やメール作成、初期的な分析などはAIに任せられる時代ですが、プロジェクト全体の舵を取り、AIを適切に使いこなす“判断者”であり続けること──これこそが人間にしかできない役割です。
AIに任せるべき領域まで人が担ってしまえば、生産性は上がりません。一方で、判断や意思決定までAIに丸投げすれば、プロジェクトは簡単に崩れてしまう。
私たちが育てたいのは、AIを活用する“ハンドル”を自らの手で握り続けられる人材です。技術を理解しつつも、それに流されない軸を持った人。そのために、実務の中で「判断する経験」を重ねる機会を多く与えるようにしています。
御社での人材採用について教えてください。
かつてはポテンシャル採用にも積極的に取り組んでいましたが、現在は明確にキャリア採用に軸足を移しています。その背景には、当社の求めるアウトプット水準と、育成にかかる時間・工数とのバランスの課題がありました。
現在在籍しているメンバーの多くは、業界で15年以上の実績を持つプロフェッショナル人材です。彼らは管理職になることよりも、現場の第一線で専門性を研ぎ澄ませ続けることに価値を感じる志向を持っており、「プレイヤーとしてのプロフェッショナリズム」を貫いています。
単なるスキルだけでなく、長年の経験で培った直感・判断・巻き込み力を持ち合わせており、私たちが重視する「AIでは代替できない人ならではの価値」を体現してくれている存在だと感じています。
そうした背景もあり、当社のキャリア採用では、“職種や肩書ではなく、思考力と行動力の解像度をどこまで高められるか”を最重要視しています。組織の規模ではなく、成果の質で勝負したい──そんな思いを持つ方には、非常にフィットする環境だと思います。

拡大よりも質を重視する持続可能な経営スタイル
8年連続増収増益を達成されているとのことですが、成長の秘訣は何でしょうか。
実は、私たちは新規営業を一切行っていません。
成長の大半は、既存クライアントとの信頼関係の深化と、そこから生まれるご紹介や他部門展開によるものです。成果を認めていただいた上で「他の部署でもお願いしたい」「他社にも紹介したい」とお声がけいただける。そうした信頼の連鎖によって自然と事業が広がっていく構造が、私たちの成長スタイルです。
背景にあるのは、「一流の価値を提供し続けるために、自分たちも一流であり続ける」という強い意志です。目先の売上を追うのではなく、クライアントと長期的に伴走し、共に成果を創り出す関係性を重視しているからこそ、短期の拡大よりも、信頼に根差した成長を選んできました。
また、こうした安定した成長を支えているのが、私たちが掲げる「メンバードリブン経営」です。
メンバーの精神的・物理的満足度を経営の最優先事項と位置づけ、働きやすさと働きがいの両立に徹底的にこだわっています。その結果、信用調査会社や官公庁などからも高く評価され、財務的な健全性だけでなく、社会的な信頼性の面でも一定の実績を残すことができています。
これは単なる“好調な数字”以上に、私たちが「人を大切にすること」を軸にしながらも、競争力ある組織を実現していることの証明だと考えています。
次世代のDX人材育成と業界全体への貢献
今後の事業展開について教えてください。
現在注力しているのが、「人を巻き込む技術」の体系化です。
DX推進においては、技術やツールだけでなく、プロジェクトを動かし、関係者を巻き込み、成果に導く“人”の力が不可欠です。私たちはこれまでの現場経験から、DX人材に必要なコミュニケーションスキルやプロジェクト推進のノウハウを体系化・言語化する取り組みを進めており、将来的には誰もが活用できるワークスタイルとして定着させたいと考えています。
この取り組みの背景には、業界全体への貢献意識があります。多くのDXプロジェクトが失敗する原因は、技術不足ではなく、「人材と組織」の課題に起因しています。
私たちが培ってきたノウハウや再現性あるフレームワークを広く開放することで、プロジェクト成功の確率を高め、業界全体のDXレベルを底上げすることができれば、それが一番の社会的インパクトになると考えています。
今後は、そうしたナレッジの公開・提供や、次世代DX人材の育成プログラム構築にも力を入れていきたいと考えています。
具体的にはどのような形での展開を予定していますか。
現在、このノウハウを独立した新規事業として打ち出すタイミングを慎重に検討しています。
まずは既存クライアントとのプロジェクトの中で実証・検証を重ねながら、汎用性や再現性の高いパッケージへと進化させ、より多くの企業が自社のDX推進に活用できる仕組みとして提供していきたいと考えています。
将来的には、社外向けの研修・ワークショップ、eラーニング、あるいは他企業との共創型プログラムといった形で展開する可能性も視野に入れていますが、拡大ありきではなく、あくまで実践知に根ざした価値を丁寧に社会実装していくというスタンスは変わりません。
私たちはこれまで一貫して、「派手な成長より、信頼され続ける会社であること」を重視してきました。今後もその姿勢を大切にしながら、企業としての社会的責任を果たし、業界の健全な発展に貢献できるよう、足元を固めた展開を進めていきます。
業界へのメッセージはありますか。
AIが進化し、あらゆる業務が自動化されていく中でも、「自ら手を動かし、実行し続ける力」の価値は決して変わらないと確信しています。
優れたアイデアや理論を持つことは重要ですが、それを現場に落とし込み、成果に結びつける“実行力”がなければ、この業界では持続的な信頼は得られません。私たちは常に「まず動く」「実際にやってみる」ことを最優先にしており、これは組織全体に深く根づいている価値観です。
特にこれからの時代は、「考えたこと」ではなく「動かしたこと」が評価される時代です。理論と実行のバランスを持ち、意思を持って手を動かせるプロフェッショナルこそが、AI時代においても不可欠な存在であり続けるはずです。
私たち自身も、そうした姿勢を貫きながら、引き続き“成果を通じて信頼を得る”プロフェッショナル集団として、業界に価値を提供していきたいと考えています。

今後のビジョンと求める人材
最後に、今後のビジョンについてお聞かせください。
これからも私たちは、無理に拡大を目指すのではなく、丁寧に、誠実に、一つひとつの仕事に向き合いながら、組織とクライアントの成長を両立させていきたいと考えています。
業界ではいまだに「長く働くこと=頑張っていること」という価値観が残っていますが、私たちは、限られた時間の中で最大限の価値を発揮する働き方こそ、次の時代に求められるあり方だと思っています。
AIが急速に進化する中で、技術だけでなく、人としての判断力や思考力、他者と協働する力がこれまで以上に大切になっていきます。だからこそ、私たちは「技術×人間性」の両方を大切にできる組織でありたいと思っています。
一緒に働く方にも、経歴やスキル以上に、価値観を共有できるかどうかを大切にしています。静かでもいい、自分なりの意思を持って、誠実に物事に向き合える方と、長く一緒に仕事ができたら嬉しいです。
私たちの考え方や働き方に少しでも共感いただけるところがあれば、ぜひ気軽にお声がけください。焦らず、でも確かに、AI時代の新しい働き方を一緒につくっていけたらと思っています。