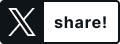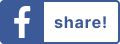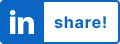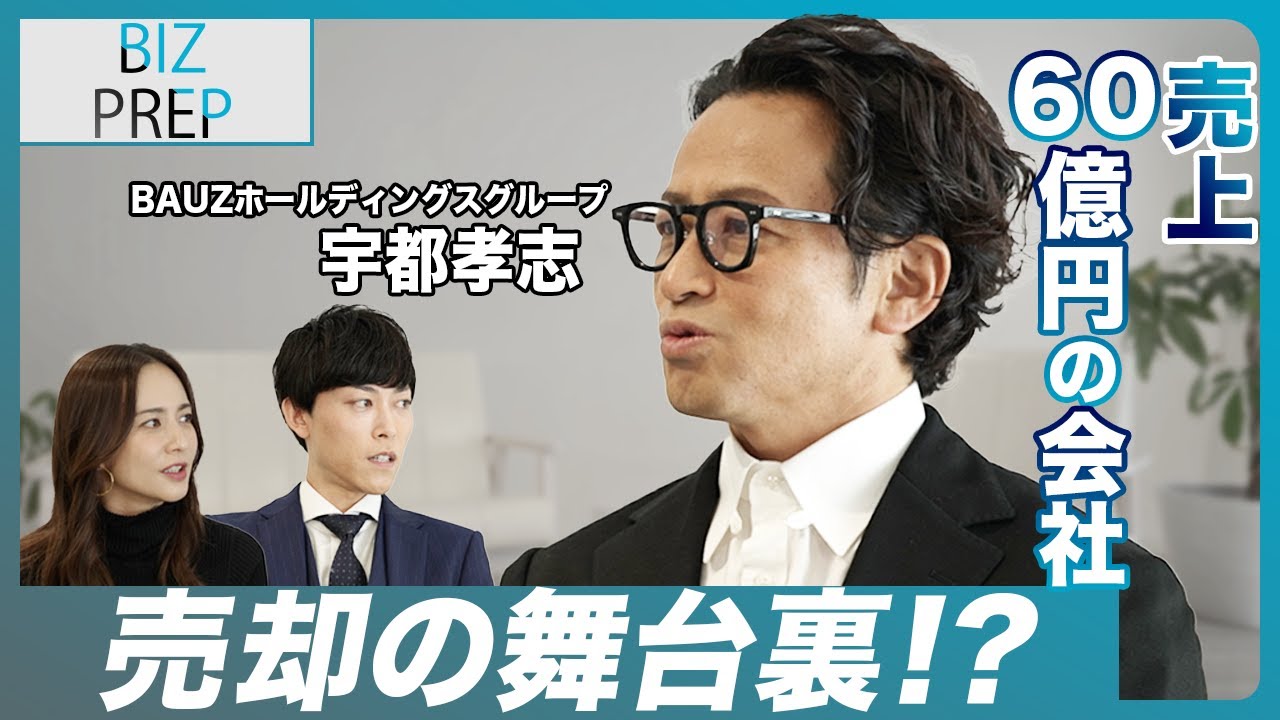目次
アパレル業界での原体験が起業の原点に
まずは田中社長の経歴と、御社設立までの経緯を教えてください。
大学進学のために上京し、4年間東京で過ごしました。就職活動では希望していた業界には行けませんでしたが、結果的にアパレル業界の会社に入社することになりました。1996年のことです。
その会社は、当時まだ珍しかったSPA(製造小売業)という新しい仕組みを取り入れた企業で、非常に勢いがありました。特に印象的だったのは、販売スタッフの売り方と商品の見せ方(VMD=Visual MerchanDisingの略)に圧倒的な力を入れていたことです。
どのような点が印象的でしたか?
人の手によって売り方と見せ方を変えるだけで、売上がこれほど変わるのかということを目の当たりにしたのです。商品の良さも大切ですが、販売スタッフの力によって業績が劇的に変わる。この経験が、後の人材事業への礎となりました。
ただ、その会社で一生働くかと考えた時、人生観の部分で合わない部分もあり、3年4ヶ月で退職を決意しました。そこで出会ったのが、その会社出身者が立ち上げたコンサルティング会社でした。5,000人規模の会社から4人の小さな会社に飛び込んで、アパレル企業向けのコンサルティングを始めたのです。
「人の力」で売上を劇的に変える衝撃体験

コンサルティング時代はどのような業務をされていたのですか?
主にアパレル企業に対する販売員教育とVMDのコンサルティングを行っていました。ちょうど小泉改革の時期で、2000年に派遣法の職種範囲が広がり、販売職も含まれるようになりました。
そこで人材派遣事業を立ち上げることになったのですが、様々な企業が前職の会社のノウハウを欲しがっていました。しかし、本社の人が理解しても、実践するのは現場の販売スタッフです。そこで、同じようなスキルを持った人材を派遣して、クライアント企業の業績向上をサポートしていきました。
その結果、もともと10億円程度だったブランドが、最大で300億円を超えるまでに成長したのです。この経験を通じて、店長の力や販売スタッフの力の重要性を改めて実感しました。
なぜ独立を決意されたのですか?
オーナー経営者と働く中で、「自分で創業してこれほど大きな会社を作れる人がいるんだ」という衝撃を受けました。それまでは皆がサラリーマンをするものだと思っていましたが、その常識が覆されたのです。
様々な個性のあるオーナー企業で働く中で、合わない部分もありました。しかし、合わないから嫌で辞めるというのは好きではありません。不満があるなら自分でやるしかないと思い、2005年10月に会社を設立しました。
ネットオークションから人材事業への転身
創業当初はどのような事業を手がけられたのですか?
資金も人脈もない状況でしたが、ファッション業界にいるメリットを活かそうと考えました。僕らはシーズンごとに不要になった洋服を、当時はRAGTAGなどで売っていたのですが、あまり良い買取り価格では売れていませんでした。
そんな中、起業のきっかけとなった出来事があります。いらないゲームソフトを中古ショップに売りに行ったところ、査定額が0円だったのです。それならまだ遊んだ方が良いと思って家に帰り、ネットオークションに出品してみたら2,700円で売れました。この価格差に衝撃を受け、インターネットを通じた商取引の可能性を感じました。
最初は委託でネットオークション販売を行い、お金が貯まってからは買取形式に変更しました。しかし1年ほど経った頃、人材派遣時代の会社から優秀な人材を派遣してほしいという依頼が来ました。
なぜ人材事業に集中することにしたのですか?
ファッション業界では常に「人が欲しい」という声が上がりますが、教育の仕組みが整っていませんでした。「店長を見習いなさい」「あの人を見習いなさい」という指導方法では、できている店長の下についた人とそうでない人で、運不運が決まってしまいます。それはフェアではありません。
この構造的な問題を解決しない限り、同じことが続くと思いました。そこで、ネットオークション事業は一緒に独立した仲間に任せ、自分は人材事業に集中することを決めたのです。
正社員雇用へのこだわりが生む圧倒的な差別化
御社の事業の特徴を教えてください。
最大の特徴は、一般的な登録型派遣ではなく、全員を正社員として雇用していることです。これは派遣を行う会社としては珍しく、雇用に対する責任の重さが全く違います。
登録型派遣であれば、仕事がなくなって継続できなくても責任はありませんが、当社の場合は仕事がなくなってもその後の責任があります。その分、販売スタッフとしてのプロフェッショナルになれるようにこだわって、カリキュラムを作成しています。
正社員雇用にこだわる理由は何ですか?
創業時から抱いていた想いがあります。ファッション業界に入ってくる人は皆、「自分のブランドを持ちたい」「セレクトショップをやりたい」「バイヤーとして世界に行きたい」といった夢を持っています。
人材事業を通じて、そういった夢を持つ人たちをたくさん輩出していきたいと考えました。そのためには、変な風習や属人的な指導ではなく、体系的な教育の仕組みづくりが必要だったのです。
競合他社との差別化はどのような点にありますか?
当社と取引のある企業では、派遣先の社員になってほしいと言われて転職になるパターンが非常に多いです。「すごくいい方だから」ということで、ある意味これは最高の褒め言葉ですね。
当社としては人材の損失にもなりますが、その人たちがその先で店長として活躍し、再び当社に派遣を依頼してくれるという好循環が生まれています。コロナ後には特にこの傾向が明確になり、1店舗5人いたら4人まとめてお願いしますといった依頼も増えています。
グループ参加で学んだ「言わない経営」の重要性
2013年にクリーク・アンド・リバーグループに参加された経緯を教えてください。
2012年頃から資金繰りという課題が出てきました。人材業界では避けて通れない問題のようでした。また、創業してまぐれでうまくいっていた部分もあり、自分の限界を感じていました。ファイナンスも含めて、もっと勉強できる環境に飛び込みたいと思っていたのです。
たまたま当社の社外取締役である公認会計士の知り合いが、クリーク・アンド・リバーでファッション事業を始めるということで、現在の会長である井川に紹介していただきました。話をする中で「一緒にやりましょう」ということになり、2013年12月にグループに参画しました。
グループ参画後はどのような変化がありましたか?
最初はこれまで通りがむしゃらに全力でやっていたのですが、一度業績が落ちました。上場企業でもあるため、仕組みづくりなどを変えていく必要があったのですが、自分のやり方が強すぎてついていけませんでした。
2016年に社長を一度降りることになったのですが、この期間が非常に良い経験となりました。他の方の経営を見ながら、異なる経営手法を学ばせていただきました。
2023年の社長復帰後の変化について教えてください。
復帰前の期間で大きな気づきがありました。それまではせっかちで、何でもすぐにやらないと気が済まなかったのですが、あまり焦らなくても結果的にうまくいくこともたくさんあるということが見えてきました。
復帰してからは細かいところまであれこれ言うのをやめています。色々な人が集まってくる中で、自分のような人間があれこれ言われるのは嫌だろうなと気づいたからです。
経営者としての失敗体験を教えてください。
やはりガミガミ言い過ぎることが失敗でした。言わないことが重要だと学びました。皆が会社に来るのは、仕事を通して何か成果を得たい、貢献したいと思っているからです。しかし、社長が細かく指示を出すことで、それを邪魔していたのです。
黙って見守っていると、意外と皆きちんとやりますし、成果も上げます。言わなくなってからの方が業績は伸びました。ただし、言わないことへの不安もあります。どこまで我慢すべきなのか、結果をどこまで待つべきなのか、日々悩んでいるところでもあります。
AIで実現する「売れなかった接客」の可視化

今後の事業展開について教えてください。
創業時から抱いていた課題があります。ファッション業界の販売スタッフに対する共通のノウハウがないのです。それを解決するため、「売れなかった接客」を可視化する取り組みを進めています。
お買い物に行くと分かると思いますが、必ずしも自分が買いたいものがすべてではありません。販売スタッフ側は売れなかった情報を基本的に記録しないのですが、この情報には大きな価値があります。
具体的にはどのような価値があるのでしょうか?
売れなかった情報には、その販売スタッフが能力開発できる可能性が詰まっています。また、何が売れなかったか、なぜ売れなかったかという情報は、次の出店のマーケティングにも役立ちます。
現在、専用のアプリを開発してデータ化を進めています。そのデータを読み取って、当社の教育担当者が販売スタッフそれぞれに個別指導を行うと、3ヶ月後には必ず売れるようになります。これは100%の実績があります。
今後はAIの活用も検討されているのですね。
現在、AIを組み込んだシステムの共同開発を進めています。データから教育担当者のロジックを学習させ、自動的にアウトプットできるようにします。さらに、その人の性格まで読み取って指導できるシステムを、あと3年ほどかけて完成させる予定です。
この仕組みは、極端な話、無償で開放しても良いと考えています。なぜなら、日本のGDP(国内総生産)を上げるためには競争ではなく、皆が良くならなければならないからです。特にファッション業界では、日本の製品を世界に持っていくことが重要ですが、そのためには日本で海外の方にどんどん買ってもらう必要があります。
業界全体の販売力を底上げしたい、それがこの仕組みで実現したい一番の想いです。
環境配慮ブランド立ち上げで社員の夢を実現

社員の方のブランド立ち上げについて教えてください。
昨年から「ブランドプロジェクト」を開始し、当社の社員の中から選抜してブランドを立ち上げる取り組みを始めました。最近ローンチした自社ブランドは、本人たちの夢を叶える初めてのアクションです。
このブランドでは日本製にこだわり、生地も工場もアイディアもすべて日本で作っています。また、ファッション業界は環境負荷の高い産業であるため、できる限り環境負荷を減らすことを重視しています。
具体的にはどのような環境配慮をされているのですか?
シャツとカットソーとバンダナは和紙を100%使用しています。元は紙で、それを糸に紡いで生地にしているため、土に埋めれば3ヶ月で自然に還ります。
デニムは岡山の倉敷で作っているのですが、通常デニムの染色には大量の水を使用し、環境負荷の問題となっています。当社のデニムは水の使用量を90%削減した染め方で染めています。
スラックスについては、染色後の乾燥に自然の風だけを使用しています。遠州風という地域の風で自然乾燥させることで、乾燥機を使わずに済み、また微細ですが風合いも変わってきます。
価格面での課題はありますか?
このような製法だと、どうしても価格に跳ね返ります。しかし、それが現実だということを多くの人が知らないのも事実です。安いものを買うことが悪いわけではありませんが、どこかで環境に全員がつながっている上で皆が暮らしているということを知るきっかけになれば良いと思っています。
単にブランドを作りたいという夢を叶えるだけでなく、業界が抱える問題に真摯に取り組んでいきたい、そういった想いで取り組んでいます。
最後にPRをお願いします。
重ねてにはなりますが、ローンチした自社ブランドは、日本のものづくりと環境配慮を両立させた、これまでにない取り組みです。シャツとカットソーには和紙100%を使用し、土に埋めれば3ヶ月で自然に還る素材を採用しています。デニムは水使用量を90%削減した染色技術で、スラックスは遠州風による自然乾燥で仕上げるなど、ファッション業界の環境負荷削減に真正面から取り組んでいます。
また、販売力向上のために開発中のAIシステムは、「売れなかった接客」を可視化し、個別指導を自動化する画期的な仕組みです。現在一部の企業で実証実験を行っており、3ヶ月で必ず結果が出る教育システムとして、将来的には業界全体に無償開放することも検討しています。
当社では、ファッション業界で夢を持つ方々、環境問題に関心のある企業様、販売力向上にお悩みの小売業の皆様とのご連携をお待ちしています。人の才能を最大限に引き出し、業界全体の底上げを図る。そんな想いに共感いただける方々と、ぜひ一緒に新しい価値を創造していきたいと思います。