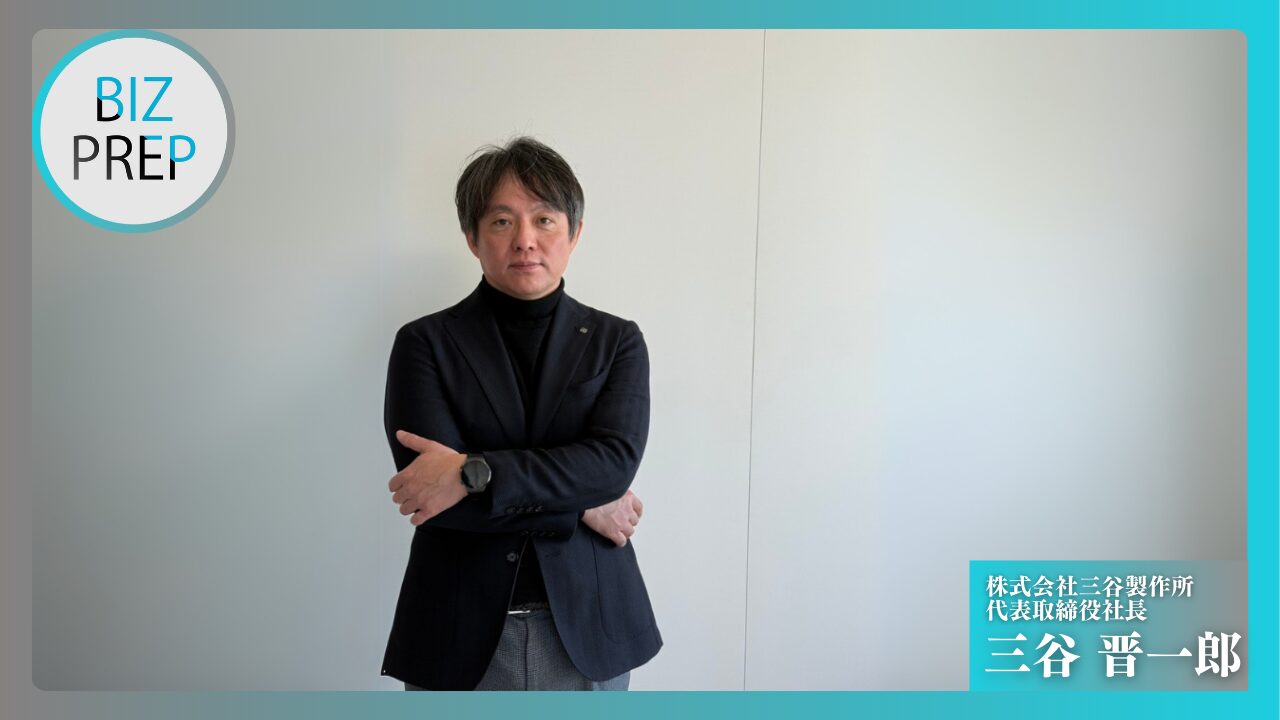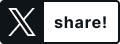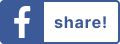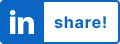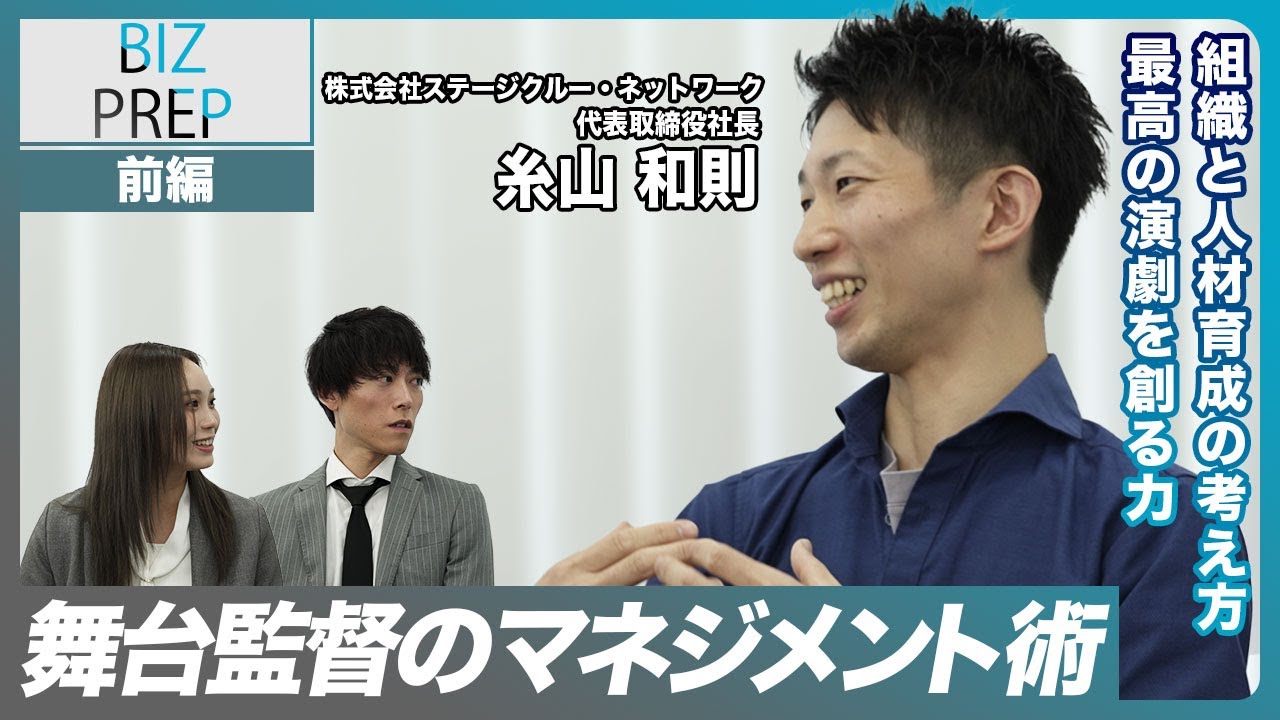目次
三谷製作所のルーツとは?小さな工場からの出発

そもそも三谷製作所はどのようにして創業されたのですか?
三谷製作所は、曾祖父の代に広島で小さな精米所としてスタートしました。
その後、農機具向け発動機の製造、船舶向け発動機の製造、精密部品の加工を始め、限られた設備と人員の中で少しずつ事業を拡大していきました。
戦後の復興期には需要が高まり、技術力を磨くことで信頼を獲得。地元の製造業と協力しながら成長していきました。
創業時の三谷製作所の強みは何だったのでしょうか?
創業当初から「品質第一」を掲げ、職人技を活かした精密加工を強みにしていました。
特に細部までこだわる姿勢が評価され、大手企業からの受注にもつながりました。
苦境の中で見つけた新たな道
三谷製作所はもともと船舶関連の事業を手がけていたそうですね。
三谷製作所は、創業以来、船舶関連の事業を中心に展開してきました。
かつては瀬戸内海を行き交う船の整備やエンジン販売を手がけ、安定した収益を確保していました。
しかし、車社会の発展により造船需要が低迷し、将来への不安が高まってきました。
造船業の低迷を受け、どのような決断をされたのでしょうか。
船の利用が減少していく中、経営の方向転換が求められる状況になりました。
転機となったのが、JFE(旧・日本鋼管)との取引開始です。
福山市にJFEの製鉄工場が建設されると、サプライヤーの募集が始まりました。
造船業の先行きが不透明な中、新たな市場に活路を見いだし、鉄鋼業界への参入を決意したのです。
未経験の分野に挑戦するのは簡単ではありませんでしたが、培ってきた技術を活かしながら加工業へと移行しました。
設備の導入や技術力の向上に取り組み、少しずつ実績を積み重ねることで、現在の三谷製作所の基盤が築かれています。
東京での学びとキャリアーー広島へ戻るかの決断
三谷氏は東京の大学を卒業後、広告業界で経験を積まれたのですね。なぜ家業ではなかったのでしょうか?
私は父から「何でもいいから社会経験を積め」と勧められていました。
その言葉に従い、広告代理店に就職したんです。
そこでプロモーションの仕事に魅力を感じ、当初5年の予定だった勤務期間は10年に延びました。
広告業界では営業やグラフィック制作に関わり、企業のブランド価値を高める方法を学びました。
この経験は、後に家業である製造業へ転身する際に役立ちました。
その後家業を継ぐ決断をされたとき、葛藤はありましたか?
そうですね、広島へ戻る決断は簡単ではありませんでした。
弟が中国での仕事にやりがいを感じていたため、家業を継ぐ人がいない状況だったんです。
兄弟で話し合いを重ねた結果、「誰かが継がなければならない」と決心しました。
広島への移住について、ご家族の反応はどうでしたか?
東京で築いた生活を離れる不安もありました。
特に妻の理解を得る必要がありました。
東京に憧れを持ち、苦労して都内での暮らしを手に入れた妻にとって、広島への移住は簡単ではありません。
それでも家族の未来を見据え、何度も話し合いを重ねました。
納得した上で移る決意を固め、2010年に私はついに帰郷。家業に身を投じ、新たな歩みを始めました。
入社直後に直面した経営の現実

広告業界から製造業に転身されて、最初に感じた違いは何でしたか?
まずは現場で学ぶよう指示されました。
しかし、実際に作業に携わると、想像以上の違いに戸惑いました。
営業中心の仕事をしていた広告業界とは異なり、工場では長年培われた職人技が求められます。
機械の操作一つ取っても簡単には習得できず、経験の重みを痛感しました。
現場ではどのような課題に直面しましたか?
現場には長年働くベテランの職人が多く、一方的な指示では動きません。
最初は意見を伝えるのに苦労しました。
しかし、職人の考えを尊重しながら対話を重ねることで、次第に信頼関係が築かれていきました。
現場の声を聞くことで課題が見え、運営がスムーズになりました。
会社の経営状況を初めて知ったときは、どのように感じましたか?
株主総会で初めて決算書を確認した際、会社が3年連続で赤字を出していると知り、大きな衝撃を受けました。
リーマン・ショックの影響で製造業全体が低迷し、新工場建設と設備投資の負担も重くのしかかっていました。
資金繰りが厳しくなり、存続すら危ぶまれる状況でした。
そんな中、営業への異動が決まりました。
お客様と直接向き合い、売上を伸ばすことが経営を立て直す手段だと確信しました。
「必ず黒字にする」と覚悟を決め、全力を注ぐ決意を固めました。
会社を守るための挑戦が、ここから始まります。
営業の第一歩。自ら動くことで見えた世界
営業に異動された際、どのような壁にぶつかりましたか?
入社から約1年後、営業に異動しましたが、当初は製造業の技術や製品について十分な知識がなく、具体的な話ができずに苦戦しました。
さらに、顧客の要求水準は高く、簡単に受注につながる状況ではありませんでした。
営業を通じて学んだことは何ですか?
何度も訪問を重ねるうちに、顧客との会話を通じて、製品を売るだけでなく、相手の課題を理解し、解決策を提案することが重要だと気づきました。
加工業は価格が一律ではなく、技術力や対応力によって評価が変わると知り、価格交渉や納期調整の工夫を学びました。
営業活動を通じて、市場の動向や顧客ニーズを把握し、長期的な視野で経営を捉える必要があると痛感しました。
現場と顧客の間に立つことで、ものづくりと経営のつながりが見え、会社の方向性を見極める力が養われました。
「三谷製作所だからできること」を追い求めて

競争の激しい製造業界の中で、どのような差別化を図っていますか?
大手企業と同じ分野で競うのではなく、独自の強みを活かす道を選択しました。
特に、大型の加工設備を利用し、長尺シャフトの製造に対応できる点が大きな武器です。
一般的な加工会社では扱えないサイズの製品を手がけることで、競争の少ない市場を開拓しました。
顧客との関係づくりについては、どのように考えていますか?
ただ製品を納品するのではなく、相手の課題を把握し、解決策を提案する姿勢を重視しています。
新規の取引先の多くは、「どこに依頼すればいいかわからない」と悩んでいました。
そうした声に耳を傾け、技術的な相談に応じながら信頼関係を築いていきました。
これからも市場の変化に適応しながら技術を磨き、より高度な加工にも対応できるよう努力を重ねています。
ただ製品を作るだけではなく、価値のあるものづくりを追求し続ける姿勢が、三谷製作所の成長を支えています。
これからの三谷製作所ーー未来への展望
今後の製造業の変化をどのように見ていますか?
人手不足が深刻化し、業界全体で自動化が加速する一方、職人の技術が必要とされる分野も依然として残っています。
特注品や精密な加工を求められる製品には、高度な技術力が欠かせません。
私たちは職人技と最新技術を融合させ、新たな可能性を追求していきます。
今後の展望についてお聞かせください。
培ってきた技術を守るだけでなく、新たな分野への挑戦を重ね、さらなる成長を目指しています。
国内だけでなく海外市場も視野に入れ、グローバル展開を進めることで、技術力と提案力を備えた企業を目指します。
ただ加工を請け負うだけではなく、顧客の課題を解決するパートナーとしての信頼を築くことが目標です。
時代の変化に対応しながら成長を続けていきます。