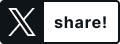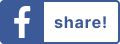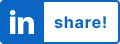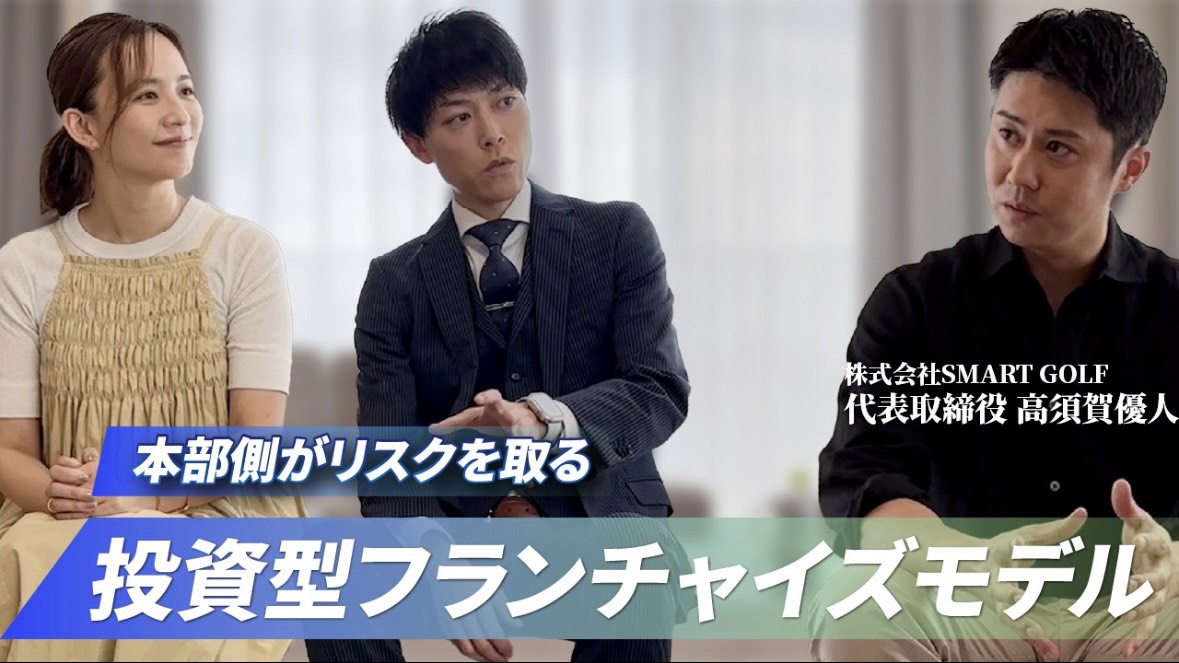目次
バンド活動と就職の狭間でーカナダで発見した「時間の流れ」という哲学
まず、波房さんご自身の経歴からお聞かせください。
大学卒業当時はちょうど就職氷河期で、周りも真剣に就職活動をしている人はほとんどいませんでした。私自身がバンドマンだったこともあり、とにかく働くことへの強い抵抗感があって、いかにして社会から距離を置けるかばかり考えていました。
最も性に合ったのが塾講師で、アルバイトをしながらバンド活動を続けていました。ただ、「このままではいけない」という焦りを感じ、次の道として大学院への進学を決めたのです。親を説得して、民俗学の研究を始めました。
大学院で2年間研究を続けましたが、修了が近づくと、また「就職」という現実が迫ってきました。そんな時期に、オーストラリアにいる当時お付き合いしていた女性と電話で話したときに、「あなたはワールドワイドじゃない」と振られました。
海外経験がなく、本当の意味で世界を知らない。そこで、ワーキングホリデーでカナダに行くことを決意したのです。
カナダでの経験についてお聞かせください。
カナダでは、まず語学学校に2〜3週間通った後、ファームステイをしながらフルーツファームで働きました。秋には、サケとイクラを扱う工場で働きました。そこはマイナス40℃という過酷な環境で、1日14時間労働という大変な仕事でした。
そこで出会ったおじさんが、私の人生最大の恩師になります。「とにかく働きたくない、逃げたい」と相談すると、おじさんは「この仕事は世間で言う3K(きつい、汚い、危険)だ。だから、これより辛いことがあったら、別に逃げていいぞ」と言ってくれました。
おじさんから教わったのは、「時間の流れ」についての哲学でした。通常、人間は過去→現在→未来という流れで時間を捉えます。しかし、おじさんは「実は逆だ」と言いました。
例えば、「弁護士になりたい」という未来の意思決定をすると、現在の時間の使い方や立ち位置が変わります。そして、その現在の積み重ねによって、過去という道筋ができあがる。だから、「お前は社会的落伍者でもない。帰ってきたら、何をしたいかという未来への意思決定をしろ」と言われたのです。
その教えを胸に、日本に帰国されたのですね。
カナダから帰国後、初めて本格的な就職活動をしました。大学院での経験を踏まえ、自分にとって最も能力を発揮できる分野は何かを考えたとき、それは「思考すること」と「書くこと」だと気づきました。そこで、執筆技術や編集能力を徹底的に磨こうと、編集プロダクションに就職することを決めたのです。
博報堂で学んだ「決裁権者を味方につける」戦術

編集プロダクションには、どれくらい在籍されたのですか。
実は1年で辞めました。その後は財団法人に勤め、定時勤務の生活を3年間続けました。9時から5時まで働いて、5時に帰宅したらボイストレーニングをして、夜は小説を書くという生活です。
しかし、当時お付き合いしていた女性に、「生活水準が低いから、私はセレブのもとにいく」と言われたのです。この言葉がとても悔しかったので、「セレブになってやる!」と思いました。そのとき、「セレブ」とは何かを深く考え、当時の社会で成功の象徴であり、影響力の頂点にあった大手広告代理店で働くことこそが、「セレブ」を実現することなのか、と思うようになったのです。
そこで博報堂を目指されたのですね。
当時は派遣社員が活躍できる時代でした自分の実力では正社員も契約社員も無理だと思い、派遣社員ならば可能性を広げられると考え、博報堂の子会社の派遣会社に登録しました。結果、環境省の「チーム・マイナス6%」の事務局立ち上げ業務に携わることになったのです。
最初の1年間は、自分を組織に欠かせない歯車にしようと、徹底的に働きました。過酷な労働でしたが、派遣社員だったため残業代が全て支給され、それまでの想像を遥かに超える高額な報酬を得ました。
そこから正社員になられたのですね。
派遣社員を経て、すぐに契約社員へと雇用形態が変わりました。博報堂には、契約社員として一定期間働くと正社員登用試験を受けられる制度があったのです。
私は、正社員登用のためにクリアすべき最重要課題を把握していました。そこで、その課題解決に直結する戦略的な一手を打ち、正社員の座を手にしました。
その戦略的な考え方が、その後の仕事にも活きたのでしょうか。
そうですね。戦略的な戦い方をするようになり、博報堂では公共系のキャンペーンを多く手がけました。結果として、社内でソーシャル系の困りごとの相談を受けるようになりました。
博報堂での代表的なプロジェクトを教えていただけますか。
2014年、北陸新幹線の開通を控え、福井県は新幹線が通らないことによる「陸の孤島」化の危機に直面していました。
そこで、「福井」の「井」に点を打つと、「丼」になるという発想が生まれ、「福丼県」として、福井県内の豊富な「丼(どんぶり)」に着目。ソースカツ丼、醤油カツ丼、海鮮丼、ボルガライスなど、多様な丼料理をフックに地域活性化を図る「福丼県プロジェクト」が立ち上がりました。
福井県知事は「今日から福井県は福丼県になります!」と宣言し、県を挙げて大々的なキャンペーンを実施しました。福井県全体を博覧会会場と見立て、各店舗をパビリオンとして、「福丼博」という企画(ガイドブック)を立ち上げたのです。
このキャンペーンは福井県内で知らない人がいないほどの高い認知度を獲得し、大きな成功を収めました。
日本財団との仕事、そして独立へ
博報堂からは、どのような経緯で独立されたのですか。
2015年、私は博報堂DYメディアパートナーズに異動し、そこから日本財団の業務に携わるようになりました。現在も、年間約200プロジェクトの活動を支援させていただいています。
大きな転機が訪れたのは2019年です。私が制作していたある作品について、知人の経営者からソーシャルゲーム化の提案があったのです。
その際、会社を設立して事業提携を結ぶ必要があると言われ、この件を社内に伝えたところ、副業禁止のため、やるならば会社を辞めるか、会社の仕事として受けるかどちらかということになり、私は、新しい挑戦を優先し、退社を決意しました。そして、この独立が、現在の会社の創業につながっています。
御社の事業内容について、改めて教えていただけますか。
私たちは、社会テーマを戦略的にクリエイティブする事業プロデュース会社です。
プランニングからイシュー開発、クリエイティブ、PR、イベント、制作物、アカウント業務までをワンストップで提供できるのが大きな強みです。
特に注力しているのが「イシュー開発」です。これは、世の中に存在する現象や共感に対し、社会的な言語を与えることで、それがメディア、コミュニティ、そして権威となるプロセスを設計するものです。
「イシュー開発」という独自の強み
「イシュー開発」について、詳しく教えていただけますか。
例えば、働きながら育児をする女性が「子どもを預ける場所がない」という現象は、多くの人の共感を呼ぶ問題です。
例えばこの現象に「待機児童」という社会言語を与えることで、解決すべき公共の課題へと昇華させます。
社会言語化されることで、行政や企業が動き出すきっかけになるのです。このように、イシューそのものを創り出し、新しい市場や課題解決分野を生み出すのが、私たちの得意とする事業です。
他社との差別化要因は、まさにその「イシュー開発」にあるのですね。
そうです。多くのソーシャルプロジェクトはすでに顕在化している課題(イシュー)をどう解決するかを考えます。しかし、私たちはイシューそのものを創り出すことからはじめます。この課題の源泉を生み出す力こそが、当社の圧倒的な差別化要因だと考えています。
この10年間、日本財団や行政機関と連携し、「海と日本プロジェクト」などの海洋事業を徹底的にプロデュースし、全国で年間何十万人もの人を動員する巨大なキャンペーンを指揮してきました。
当初は依頼された仕事でしたが、そのイシューを創り出す力によって、頼まれたことをそれなりに自分ごと化して、気づいたら自分がその中心にいることが、
当社の最大の強みです。
社会貢献経済圏を創る——ソーシャルプロジェクトの未来

今後の業界トレンドや、御社の方向性について教えていただけますか。
私たちの事業は「社会テーマ」を扱い、特にソーシャルな領域に注力しています。SDGsやESGといった市場を大きく捉え、私たちは「社会貢献経済圏」という巨大な市場が存在すると考えています。
現在、日本の個人寄付市場の推計総額は約1.2兆円ですが、アメリカにはその数十倍以上の市場規模があります。日本では富裕層が増える中で、資産を社会貢献に使いたいというニーズは確実に高まっており、大きな成長余地があると見ています。
その市場を開拓していくために、御社はどのような取り組みをされるのですか。
これまでは依頼されたプロジェクトが中心でしたが、今後は自社が本気で取り組みたいプロジェクトを推進していきます。例えば、海洋分野であれば、「海を文化資産として残し、日本に新しい海洋国家感を創る」といった大きなテーマです。
文化事業は「経済合理性が合わない」と言われがちです。しかし、プロジェクトの設計(立て付け)をしっかり行い、夢に高い具体性と解像度を持たせます。さらに、実行者(誰がやるか)や過去の実績(トラックレコード)を示すことで、ファイナンスの仕組みは必ず作れると考えています。
社会貢献経済圏を作るためには、どのような能力が必要ですか。
公益団体が世の中に良い事業を生み出すには、プロジェクトを具体的に実現する能力が必要です。日本では、その中核を担う「プログラムオフィサー」と呼ばれる人材が圧倒的に不足しています。
例えば、日本では海外に比べて、寄付文化がまだまだ浸透していませんよね。そんな中で、寄付が単に集まり、受け皿となる団体へお金が流れるだけでは、社会的なインパクト(ソーシャルインパクト)は生まれません。私たちは、その資金を真に社会に役立てるためのプロデュース能力が不可欠だと考えています。
村を経営する感覚で、持続可能な会社を目指す
御社の組織についてお伺いします。事業承継についてはどのようにお考えですか。
年間200ものプロジェクトをサポートするため、私はフレームワーク化を徹底しており、思考から企画書までをフォーマット化しています。フォーマット化することによって、PRやプランニングなど、各要素における優秀なプロデューサーが育っていることが当社の強みであると考えています
ソーシャルムーブメントを作る能力の再現性については、まだ社内メンバーへのインプットを進めている段階ですが、現在のメンバーで私がいなくともプロジェクトを回していける体制は十分に整っていると考えています。
IPOや規模拡大については、どのようにお考えですか。
正直なところ、上場や一攫千金にはあまり興味がありません。会社経営者として、どのような幸福圏を描くかが重要だと思っています。そして描いたビジョンをわかりやすく伝えるという意味でも、弊社には現在50名ほどのスタッフが在籍していますが、彼らとともに、「会社経営」というよりも「村を経営している」という感覚で捉えています。
私にとって何より大事なのは、この「村」が持続可能であることです。ここで働く人たちが自己実現でき、社会テーマを扱う仕事にやりがいを見出すことで、自分たちの信念と誇りを持って働くことができる・・・その経済圏が持続可能になることこそが、最も重要だと考えています。
最後に、PRしたいことや、読者へのメッセージをお願いします。
現在、私たちの会社は大きな転機を迎えています。これまでは「誰かの何かを実現したい」という願いを手助けすることに注力してきました。しかし今後は、自分たちの具現化能力を、自分たちが本当に実現したい社会的なテーマに注ぎたいと考えています。
社会貢献経済圏を広げるため、応援してくれる人たちとともに、主体的なソーシャルアクションを増やしていきます。私たちは、最もときめいてワクワクしている会社であり続け、多くの人が「一緒に夢を共有したい」と集まるようなコミュニケーションを目指します。
物語を作ることこそが、私のレガシーになると信じています。