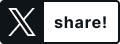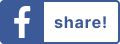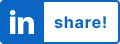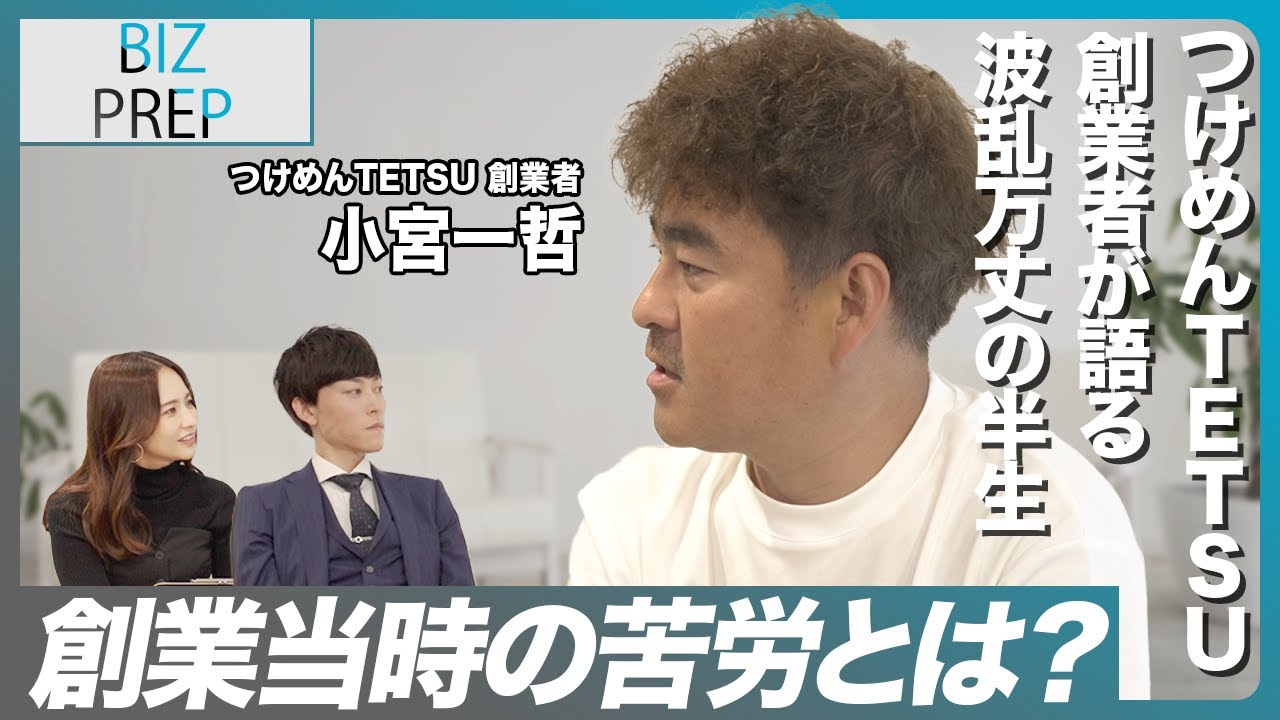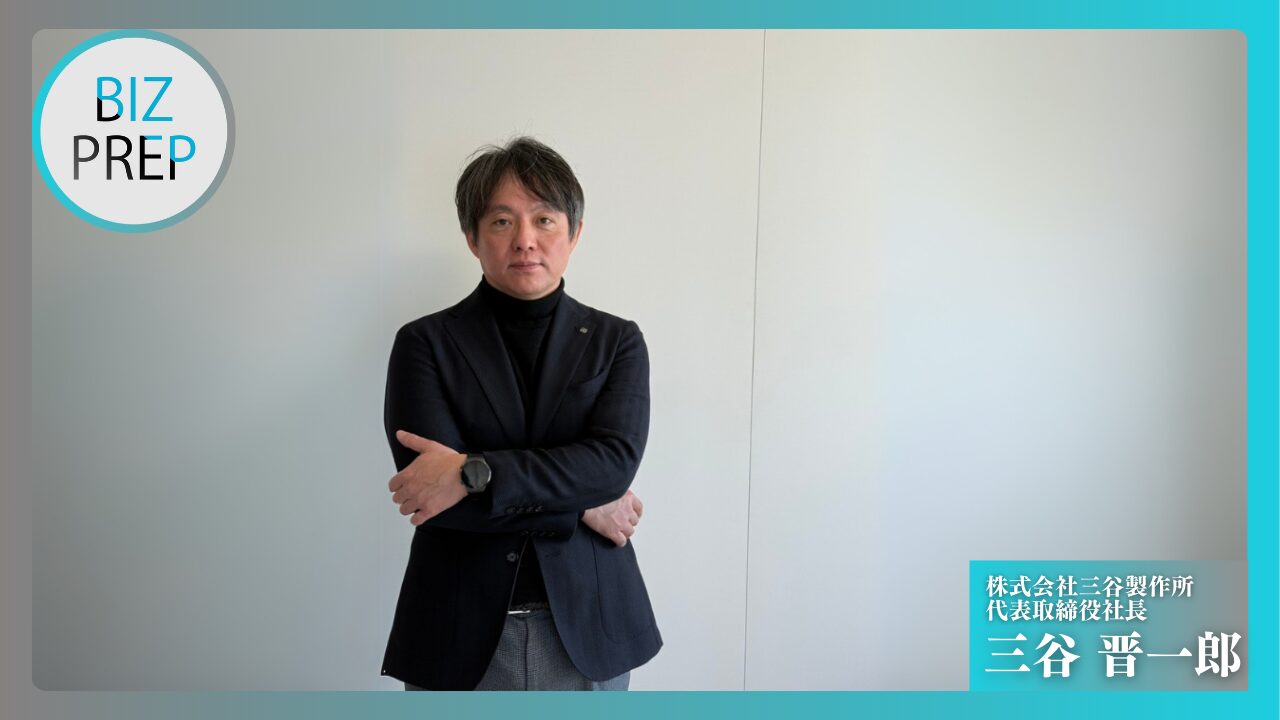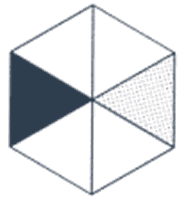目次
創業の原点とは?小さな町工場から始まった夢

ダイエー食品工業はどのように誕生したのですか?
弊社は昭和47年に創業しました。初代が発明家で、食品の鮮度保持や品質改良を目的とした食品原料の開発がメインだったようです。特許も複数持っていました。
その後、フランチャイズでうどん、そば屋を展開する中で、加盟店から「出汁」も共有してほしいと言われたのが出汁製造のきっかけです。
当時、社員旅行が盛んな時代で、加賀温泉などの宿泊施設では「夜中に小腹がすく」というニーズが多くあり、旅館側でも夜食用にうどんや雑炊を提供していたそうです。
弊社はその旅館向けに出汁を供給する事業から始めました。
創業当初の事業と、その発展の過程を教えてください。
創業当初は出汁の製造を中心に事業を展開していましたが、徐々にフランチャイズ展開や多様な取引を通じて規模を拡大していきました。
時代の移り変わりと共に、顧客の健康志向が高まる中で「体に良いものを届けたい」という思いが社内でも強くなり、健康食品事業へのチャレンジへと発展していきました。
この「良いものを作る」という姿勢が、その後の事業成長を支える軸となりました。
新たな市場を切り拓く – 事業の拡大と多角化戦略
どのような経緯で健康食品や化粧品事業に参入されたのですか?
健康食品事業は、初代社長がご自身の病気をきっかけに「健康を支える商品を作りたい」という強い想いからスタートしました。自身の体を使いながら研究開発を行い、次第にその取り組みが事業として広がっていきました。
また2代目の時代には「内側だけでなく外側からも健康を支える」という発想のもと、化粧品開発にも着手。現在、化粧品の製造部門は関連会社が担い、弊社は販売を続けています。
食品添加物やOEM事業にも取り組まれた背景を教えてください。
健康食品や食品事業を進める中で、お客様から依頼をいただくことが増えてきました。
そうしたニーズに応える形でOEM事業をスタートし、お客様のイメージを形にする開発力が弊社の強みとなっていきました。
また食品原料や食品添加物への取り組みも、自社開発力と品質へのこだわりを背景に発展してきたものです。全ては「安心で、体に良いものを世に送り出す」という理念に根ざしています。
経営のバトンを託す。第三者承継の決断

事業を引き継がれるまでの経緯をお聞かせください。
独立後、事業会社の経営に挑戦したいと考え、事業承継の機会を探していました。第三者承継を支援する機関に登録し、複数の企業と話を進める中で、ダイエー食品工業と出会いました。1年以上前の初めての面談では、タイミングが合わず、一度見送る形になりました。それでも経営者が待ってくださり、話し合いなどを進めた結果、引き継ぐ決断に至りました。信頼関係を深められた点が、経営を引き受ける上で大きな要因になったと感じています。
後継者として選ばれた理由や決め手は何だったのでしょうか?
他にも候補者がいましたが、経営者との相性が良かった点が大きかったです。初めて面談した際、経営に対する考えや事業への向き合い方に共感し、深く話し合いました。その後、一度は見送りましたが、再び機会をいただき、改めて話を進める中で信頼関係が深まりました。人柄や経営の方向性が一致していたこともあり、最終的に引き継ぐ形となりました。
事業承継の壁を乗り越えるために
事業承継において最も苦労された点は何でしたか?
最も苦労したのは「決断」そのものだったと思います。第三者承継という形で、私自身は全く別業界からのチャレンジであり、正直なところ、この会社を自分が本当に引き継いでやっていけるのか?と迷い続けた時期もありました。
また、単に後継者不足を社会課題として解決するという理屈だけでは決断しきれず、最後は自分がどれだけこの事業に対して情熱を持てるか、自分のやりたいことと重なるか、という点を何度も見つめ直しました。一度は保留させていただいたこともありましたが、結果として「自分がやりたいことだ」と思えたからこそ、決断に至れたと思います。
事業承継に向けた準備や、金融機関との調整はどのように進めましたか?
事業承継については、独立したタイミングからいずれは事業会社を経営したいという思いを持っていたので、事業承継引継ぎ支援センターなどの公的な窓口にも早期から登録していました。実際の金融機関との調整については、日本政策金融公庫の融資制度を利用し、全額融資で資金調達を行いました。無担保・無保証で借り入れできたのは、制度の存在と、会社側の財務状況が良好だったことが大きかったと思います。
また、保証協会をつければ金利は安くなるものの計画書提出など負担が増えるため、敢えて保証協会は付けずにスピード重視で進めました。銀行や支援機関も後継者不足を社会課題と捉えているという姿勢が強く、非常に前向きにサポートしていただけたことが心強かったです。
新たなリーダーとして歩み出す – 経営者の挑戦
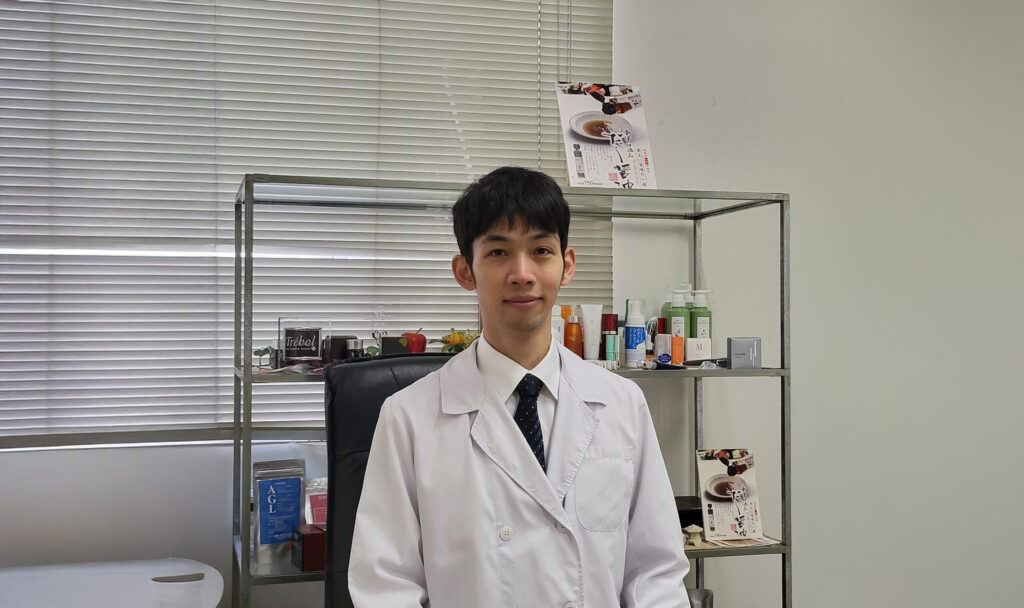
事業承継後、最も意識された経営のポイントは何ですか?
事業を引き継いだ後、まずは社内の状況の正確な把握に力を注ぎました。
食品業界の経験が無かったため、製造工程や品質管理の仕組みを学びながら、業務全体を理解する必要がありました。従業員との信頼関係を築くことも大切だと考え、現場の意見を聞きながら課題を整理します。また売上を安定させるため、既存の取引先との関係を維持しつつ、新たな販売戦略にも取り組みました。特に、ECやオンライン販売の強化を進め、より多くの顧客に商品を届けられる体制を整えました。
小規模だからこそ、柔軟な対応を活かしながら、事業の成長を目指しています。
前職の経験が現在の経営にどのように活かされていますか?
コンサルティング会社で働いた経験は、今の経営にとても活きています。業務の効率化や戦略づくりなど、これまで学んできたことを現場で試せる場面がたくさんあります。また中小企業向けのコンサルでは、課題を見つけて整理し、解決していく力をしっかり鍛えることができました。独立してからは、Webを使った集客に力を入れてきたことも大きな強みです。その経験を活かして、今はECやデジタル施策にも積極的に取り組み、売上アップにつなげようとしています。
経営者として大切にしている信念は何ですか?
私が大事にしているのは「自分が本当に楽しめるかどうか」ということです。
事業を伸ばしていくには、収益や戦略ももちろん必要ですが、結局はどれだけ本気で取り組めるかで結果が変わると思っています。興味が持てないと、途中でモチベーションを保つのが難しくなりますからね。 また、考えすぎずにまず行動すること意識しています。計画を立てるのは大切ですが、実行しなければ何も動きませんし、やりながら修正していく方が上手くいくことも多いです。
もちろん従業員とのコミュニケーションも欠かせません。現場の声をしっかり聞きながら意思決定を行い、みんなで同じ方向を向けるように心がけています。柔軟に変化に対応できる環境を整えることで、会社全体として持続的に成長できると信じています。
組織を育てるために。企業文化の継承と変革
従業員との関係構築で工夫されたことを教えてください。
事業を引き継いだ後、まずは従業員との信頼関係を築くことを優先しました。
新しい経営者として受け入れてもらうには、現場の声をしっかり聞き、理解する姿勢が欠かせません。一人ひとりと対話しながら業務の流れを把握し、これまでのやり方を尊重しつつ、改善すべき点を見極めました。
また、経営方針を共有する場を定期的に設け、会社の目指す方向を明らかにするよう努めました。さらに、従業員からの意見を積極的に取り入れ、働きやすい環境づくりにも力を入れています。長年築かれてきた企業文化を大切にしながら、新たな挑戦にも柔軟に対応できる組織を目指しています。
企業文化を維持しながら、新しい風を取り入れる工夫はありますか?
長年受け継がれてきた価値観を大切にしながら、新しい取り組みを進めるために、まずは社内の考え方の理解から始めました。従業員と積極的に対話し、これまでのやり方を尊重しながら、必要な変化を整理しました。
新しい視点を取り入れるため、定期的に経営会議を開き、従業員が意見を出しやすい環境を整えています。またオンライン販売の強化など、時代の変化に対応する取り組みを進めると同時に、社内での情報共有を活発にしました。伝統を守りつつ、新しい挑戦にも柔軟に対応できる組織を目指しています。
未来を見据えた成長戦略と新たな展望
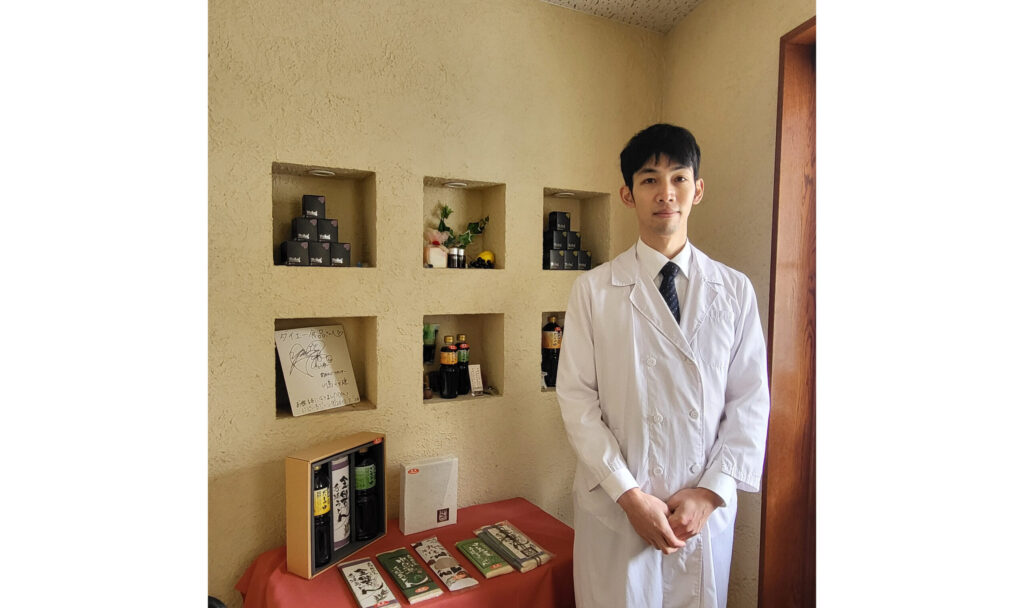
ダイエー食品工業の今後の展望についてお聞かせください。
健康食品市場は今も拡大を続けており、事業の幅をさらに広げていく予定です。特に機能性表示食品への対応や、新たな健康素材を取り入れた商品開発には力を入れているところです。食品事業との組み合わせで、より健康を意識したものづくりを進めていきたいと考えています。 また、販売チャネルの強化も重要なテーマです。既存のお取引先との信頼関係を大切にしつつ、ECやオンライン販売の取り組みも加速させ、新しい市場の開拓を目指しています。さらに、地域ならではの素材を活かした商品開発にも力を注ぎ、付加価値の高い製品を生み出していくつもりです。これまでの伝統を守りながらも、新しいことへの挑戦を恐れず取り組み、会社全体の成長につなげていきたいと思っています。
競争の激しい食品業界で生き残るための戦略はありますか?
大切なのは「差別化」と「開発力」です。
弊社は、出汁やつゆの分野でも保存料やエキス不使用といったこだわりを持ち、うどんやそばにも健康素材を練り込むなど、常に「他社が真似しにくい品質と価値」を提供しています。また、OEMにおいてもお客様の要望を具現化する開発力は当社の強みです。これらをさらに磨き、成長していきたいと考えています。
今、事業継承を考えている方に伝えたいこと
事業承継を考えている方に向けたアドバイスをお願いします。
事業を引き継ぐ際、一番難しいのは決断のタイミングだと感じました。
譲る側も引き継ぐ側も、それぞれ不安を抱えることが多く、慎重に進める必要があります。
ですが、きちんと準備を進めて、信頼できる相手と何度も話し合いを重ねていけば、きっと自分に合った答えが見えてくると思います。
特に第三者承継を考えている場合は、できるだけ多くの出会いの場を作ることが大切です。
事業承継支援機関やマッチングプラットフォームを活用することで、選択肢はぐっと広がります。ただ、考えすぎて動けなくなると、せっかくのチャンスを逃してしまうことも。
「迷ったら行動してみる」という気持ちで、自分に合う承継方法を見つけていくことが大事だと思います。